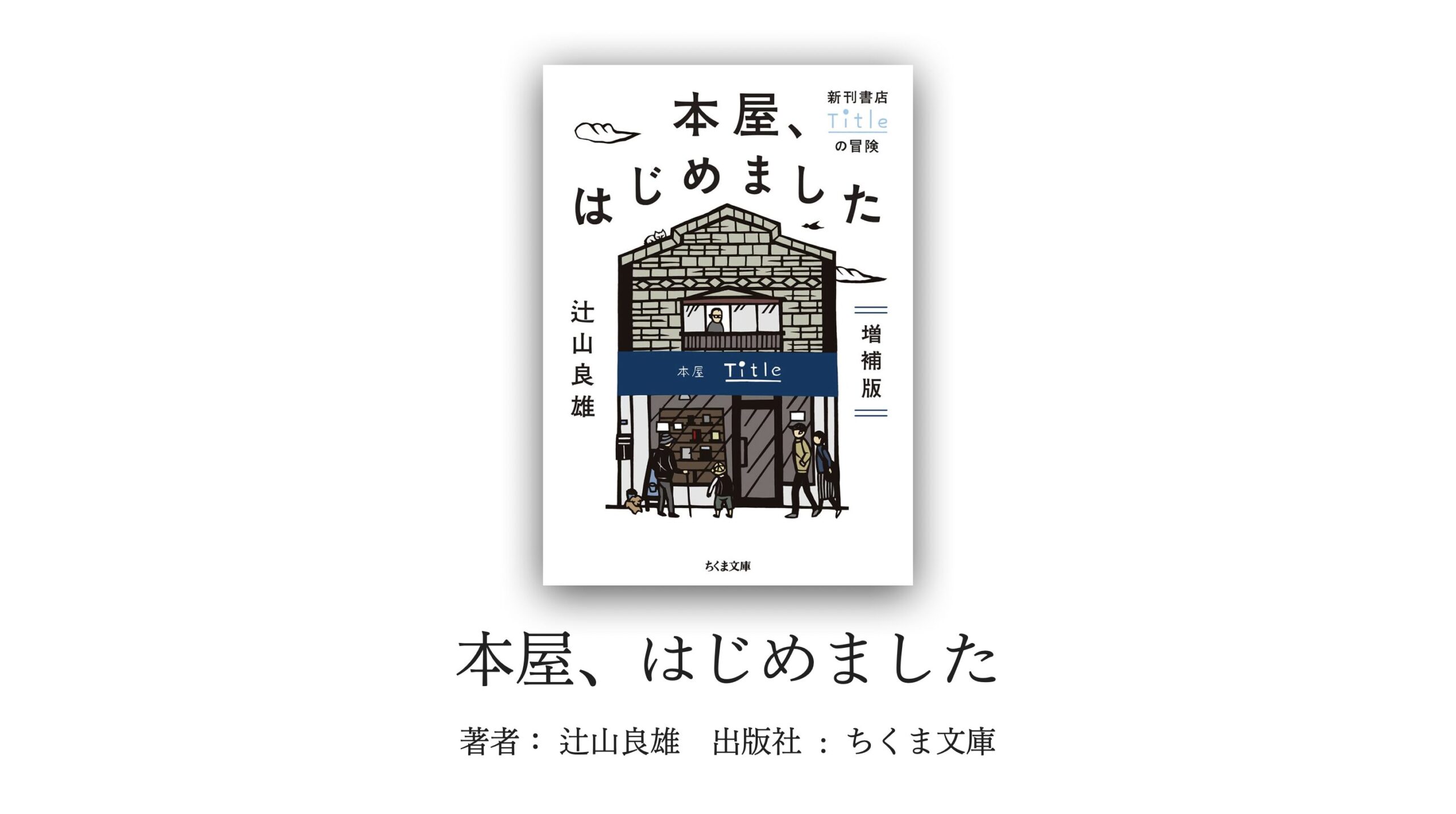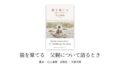めちゃめちゃいい本。本屋経営者、本屋をやりたい人、本とか本屋が好きな人にグサグサ刺さる。
元リブロ池袋本店副店長だった著者が独立して荻窪に開いた書店「Title」の軌跡を通して、本屋という仕事の真髄と哲学を綴ったエッセイ。
書店経営の現実的な話から、本と人との出会いの意味まで、包み隠さず語られている。
以下、心に残った箇所を引用。
古本屋を始めなかった理由ははっきりとしていて、その仕事の命である仕入・買取に必要な知識がないということと、自分は新刊書店でずっとやってきたので、その世界になじみがあるし、何より「今を生きている人に対して本を売りたい」という思いがあるからでした。「こういう考え方もあるよ」「これは知っておいたほうがよい」などという思いを、本を通して店に来る人に届けたいのです。古本屋でも昔と違い、内装に気を配っている店や、店の一角に新刊本や雑貨などを置くような店が増えていますが、やはり(今)を扱うという意味では、新刊書店でなければならないと思います。
p76-77
自分は昔から全国にあるさまざまな街を歩き、そこにある店や歩いている人がつくり出す街ごとの雰囲気の違いを、散歩しながら体感するのが好きでした。街を見るときに、人がどれだけ歩いているのか、その年齢・性別・服装、物件の周りにどんな店・施設があるかといったことは、店舗を出すときにまず見るべきポイントでもあると思います。その街を歩いている人が、自分が出そうとする店に入りそうな人かどうかを考え、またその人が自分の店に行ったあとで立ち寄る店が他にあるかどうか、なるべく具体的に思い浮かべます。そうしたお店がたくさん思い浮かぶようであれば、その街とは相性が良いと判断します。飲食店は住んでいる人の数に比例してあるのに比べ、雑貨屋の数、それがある場所は限られます。そうした店がいくつかあれば、その周辺は生活必需品でなくてもモノを買ってもらえるような土壌があるのだなということがわかり、本屋が成り立つ可能性があります。
p84-85
これはセレクト書店に限った話ではありませんが、一〇〇冊の選ばれた本のなかから自分に合う一冊を見つけなさいということは、なかなか難しいものです。本は一冊一冊、その本の奥に秘められた世界を持っていますが、置いている本の種類が少ない、またはその種類が似通っているということは、総体としての世界が小さくなるということです。そうさせないためには、数多くの種類、世界観の違う本を、棚にぎっしりと一冊一冊並べて置いてみる。そうすることで、その店が小さくても、そのなかに多様な世界を抱え持つことになり、見る人にとっては「こんな知らないことがあったのか」という発見が多くなります。
p103-104
思うに、本屋に来て面白い本と出合うには、まず置いてある本に触れてみることです。「何をあたりまえな」と思うかもしれませんが、普段、本に慣れていない人は、本になかなか触ろうとしないものです。心理的な距離があり、いわば〈遠巻きに見ている〉という状態です。 本に触れてみることで、その手触りから、それが直感的に良いと思うものであるか、自分に合ったものであるかということが自然と伝わり、その本の内容までもが、読まなくても何となくわかります。そうしたことを繰り返していくうちに、自分が本当に求めている本が、すぐにこれだとわかるようになります。 こうした本との関わり方を続けていけば、そのとき自分が探していた本がなくても、他の面白そうな本が勝手に目に入ってくるようになるのですが、最近は探している本だけをずっと追いかけていき、それが見つからないとすぐに出ていく人のほうが多いような気がします。本当は出合うべきだったものに、出合う機会を自ら捨ててしまっているようで、そんなときは余計なことですが「もっとあたりをゆっくり見回してみれば、今まで気にもとめなかったことが目について、面白くなるかもしれないのにな」などと思ってしまいます。
p195-196
町の人の生活と身近な場所にありながら、そこに住むある一定の趣味や志向を持つ人には支持をされるような品ぞろえをして、その人たちの興味を惹く本やイベントを積極的に提供する。その本屋がある地域により求められることはさまざまなので、品ぞろえに決まった正解はないと思いますが、その土地のなかでどんな本屋にしたいのかというイメージが店を始める店主のなかにないと、どこで店を始めても難しいことになると思います。これからの町の本屋は、町にあるからこそ、その個性が問われていくのだと思います。
p212
以前の会社でも本を売る仕事はしていたが、Titleをはじめてから、自分は本に関して何も知らなかったと気づかされることが多かった。この本読んだとか、この作家はどういう人なのかと、店頭で尋ねられるのはいつものこと。そのようなときに名前を知っているだけでは、お客さんからの信頼は得られない。 本について知りたければ、自分でも数多く読んでみること以外ほかにはない。店に並べているなかに、読んだことのある本が増えてくると、そこにある本が自らの延長のように思えてくる。そのような状態にあれば、新刊が入ってきたとき仲間の本がすぐに思い浮かぶし、新しく入ってきた本をずっとそこにあったかのように、売場になじませることができる(その店になじんでいるように見える本ほど、よく売れる)。 同じように普段から本をたくさん読んでいれば、その日入った本でもページをめくって少し読んでみるだけで、その本のエッセンス(内容、文体、刊行の意義など)は見当がつくようになる。それがわかれば、問い合わせ内容に適した本を自信をもって答えられるようになるし、自分の実感がこもったことばで本も紹介できる。
p231-232
情報があふれかえる現在、人は自分の実感からは遠ざけられ、本を選ぶという体験は、かえって貧しいものとなってしまった。それに抗うには、他人やインターネットだけを頼りにするのではなく、自分の時間をそこに費やし、こころに響いたものをじて、少しずつ自分の世界を拡げていくしかない。
p234
わたしはこれからも本を売って生計を立てていく、ひとりの〈bookseller〉でありたいと思っている。本屋の数が減りその内実も変わりつつあるいまだからこそ、リアルな場所としての本屋の価値、本を知っている人物への重要性が高まってくると思うからだ。 本はどこで買っても同じとはよく言われることだが、実はどこで買っても同じではない。価格やポイントでお客さんを釣るのではなく、本の価値を〈場〉の力で引き立てることにより、その本は買った店とともに、記憶に残る一冊となる。 情報技術が発達し、世のなかが更に便利になったとしても、人の感情を動かすのは、人の手が感じられる仕事である。Titleはまだそうしたレベルには達していないし、職人的な技術と対価を得る商売とを、どのように結びつけていけばよいのかいまだ答えは出ていないが、その先に自分が進んで行くべき道があると思っている。
p242
感想
本は私にとって大事な存在である。
「⚪︎⚪︎によって人生が変わりました!!」みたいな表現は好きではないが、自分の人生を変えてくれた本はいくつも思いつくし、6年前から始めたブログも方向性を二転三転しつつ「書を読み思考せよ。」というタイトルで、読んだ本を紹介する形に落ち着いている。
本屋が厳しいと言われて久しいが、やはりその場が好きだ。昨年、運良く徒歩数分のところに本屋ができて、そこのシェア型書店で棚主にもなった。気づけば本と本屋の世界に、じわじわ沼ってきつつある。
そうこうしているうちに、あと数年で40代突入。本業の仕事はいつからか卒なくこなせるようになり、家庭は子ども中心で慌ただしいものの、あたたかくて幸せだ。客観的に見れば順風満帆である。
だが、順風満帆だからこそ悩む。このまま穏やかに年を重ねていくのが正解なのだろうか。自分の一度きりの人生、本当にこれでいいのだろうか。
はい、ようこそ「中年の危機」へ。
本業で培った専門性、もう学んで10年以上たつアドラー心理学や哲学、そして大好きな本。これらすべてを結実できるような仕事をつくれないものかと、密かに模索している最中に出会ったのが『本屋、はじめました──新刊書店Titleの冒険』だった。
この本、書店経営者の間では「バイブル」と呼ばれているらしい。その評価に偽りはない。後半には売れ筋商品から細かな収支まで、普通なら企業秘密にするような数字も包み隠さず公開されている。
これだけでも価値があるが、それ以上に心を打つのは辻山さんの職人としての矜持だ。引用した箇所を読んでもらえば、その真摯さが伝わるはずだ。
奇妙な偶然もあった。この本を読了した数日後、著者の辻山さんが地元でトークイベントを開催するという情報が SNS で流れてきた。これも何かの運命とばかりに足を運んだが、参加者の大半は書店関係者。場違いな自分は遠巻きに大人しく聞いているだけだったが、辻山さんの佇まいに強い印象を受けた。
物静かでありながら、芯の通った「気骨のある方」。職人気質の人、と言い換えてもいいだろう。
本屋という商売がいかに過酷かは、『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』(飯田一史)に詳細に書かれている。利益率の低さ、業界構造の歪み——まさに「無理ゲー」である。生き残るためには、カフェ併設やイベント開催といった「本屋×ナントカ」的な多角経営が欠かせない。
しかし、ここに大きな落とし穴がある。「どうすれば採算が合うか」という算盤勘定が先行し、「本がある場としての本屋」の魅力が低下してしまう。
イベントでの辻山さんの話によれば、書店 Title もカフェを併設しているものの、売り上げの9割は本だという。比較対象はないのだけれども、いまのご時世、きっとすごい数字なのだろう。(それでも年々、本は売りづらくなっていると著書で語られていたが)
それを可能にしているのは、本に関する膨大な知識と、1冊1冊の本に込めた愛情だろう。この本を読むと、辻山さんが棚に魂を込めている様子がひしひしと伝わってくる。
自分がこれからどのような道を歩むにせよ、辻山さんのような「気骨」を持ち続けたい。妥協することなく、自分が信じるものに向き合い続ける姿勢を。
考えてみれば、辻山さん自身も大手書店チェーンの副店長という安定したポジションから独立して書店を開いたのだから、きっと何かしらの「中年の危機」を経験されたのではないだろうか。
そうした意味で、この本は書店関係者のみならず、キャリア論としても、特に人生の転換点に立つ人々に刺激を与えてくれる本だ。
▼ このツイートも刺さった