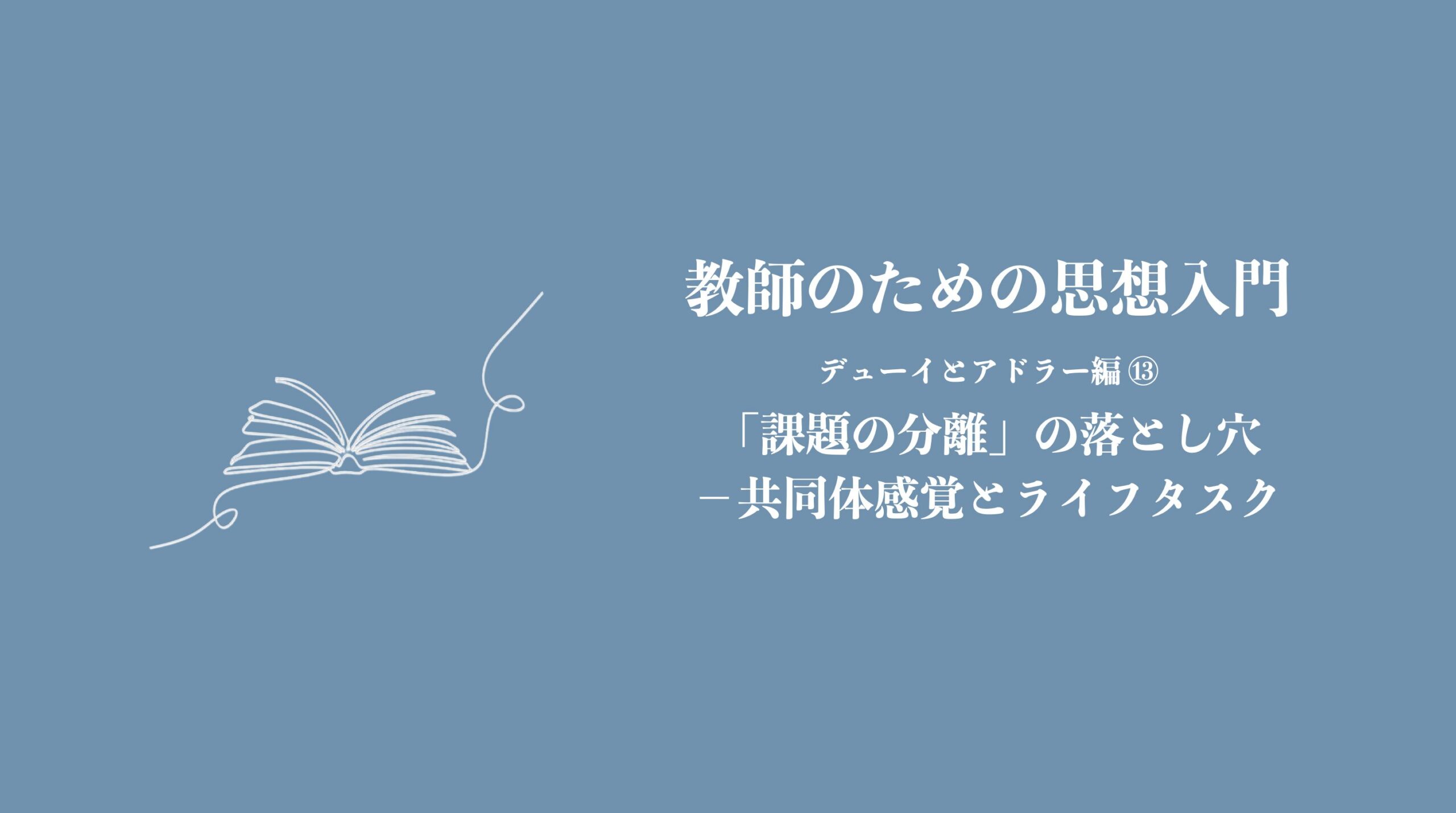▼ 前回の記事はこちら
前回、ことははアドラー心理学の鍵概念「共同体感覚」について学んだ。それは「つながりの感覚」と「他者への関心」という2つの要素から成り立っていた。身近な人から始まって、やがては宇宙にまで広がっていく—そんな壮大なスケールに驚きつつも、日常の実践と結びついた「壮大で身近なもの」としてことはは理解していた。ところが、その後アドラー心理学をさらに学ぶうちに、ある疑問が心に生まれてきた…
数週間後、ことはは前回とは少し違った表情であつゆる書房を訪れた。
ことは:
こんにちは!あの後、アドラー心理学の本を何冊か読んでみました。
あつゆる:
おお、それは良かった。どうだった?
ことは:
(椅子に座りながら、興奮気味に)とても勉強になりました!特に「課題の分離」という考え方に、すごく影響を受けまして…。
あつゆる:
どんなところに影響を受けたの?
ことは:
「これは私の課題、あれは相手の課題」って分けて考えるんですよね。目から鱗でした!すごくスッキリして、余計な悩みが一気に減って…。でも…(表情が曇る)
あつゆる:
でも?
ことは:
(困ったような顔で)あれ?って思ったんです。前回あつゆるさんとお話しした「つながり」や「関心」の話と、何だか正反対のような気がして…。「それはあなたの課題だから」って境界線を引いちゃうと、相手との距離ができてしまって…。
あつゆる:
(興味深そうに)具体的にはどんな感じかな?
ことは:
クラスで困っている子がいても、「それは本人の課題だから私が過度に介入してはいけない」って思うようになったんです。以前なら「何とかしてあげたい」と思ったのに、今は一歩引いてしまう自分がいて…。
何だか前回お話しした「共同体感覚」とは逆の方向に向かっている気がするんです。つながりじゃなくて、分離の方向に…。
あつゆる:
(深くうなずいて)とても鋭い観察だね。実は、ことはさんが感じた違和感には、とても重要な理由があるんだ。
ことは:
どんな理由ですか?
あつゆる:
「課題の分離」という考え方は、確かにアドラー心理学の中で語られることが多いんだけど、実はアドラー自身が使った言葉ではないんだよ。
ことは:
(驚いて)え!?そうなんですか?
あつゆる:
むしろ、後の研究者や実践家たちが、アドラーの思想の一部を取り出して強調したものなんだ。アドラー自身が最も大切にしていたのは、君が感じた通り「つながり」や「協力」だった。
ことは:
(ハッとして)だから違和感があったんですね…。
あつゆる:
そう。アドラーの原点を理解するには、彼がどんな人生観を持っていたかを知る必要がある。『人生の意味の心理学』の中で、彼はこう言っている。
人生とは、仲間に関心を持つこと、全体性の部分となること、そして、人類の幸福へと貢献することを意味する。
ことは:
人類の幸福への貢献…。課題の分離とは真逆の発想ですね。
あつゆる:
まさに。アドラーが本当に注目していたのは、人生で避けられない困難や悩みがあるとき、それを「あなたの問題だから」と切り離すことではなくて、むしろ「一緒にどう向き合っていけるか」を考えることだったんだ。
あつゆる:
アドラーは、人生には避けて通れない3つの課題があると考えたんだ。「ライフタスク」と呼ばれるものなんだけど、ことはさんの読んだ本にも出てきていたんじゃないかな?
ことは:
(少し考えて)あ、出てきました!確か「交友」「仕事」「愛」の3つでしたよね。人間関係をどう築くか、社会の中でどう働くか、親密な関係をどう育むか…みたいな。
でも正直、課題の分離を学んだ後だと、これらも「自分の課題」「相手の課題」って分けて考えるものなのかなって思ってたんです。
あつゆる:
なるほど、そう捉えていたんだね。でも実は、これらは分離するものではなく、「ライフタスク」こそが私たちが共同体感覚を実現するための「場」なんだよ。
ことは:
(考え込んで)課題を分離するのではなく、課題を通じてつながるということですか?
あつゆる:
その通り!例えば、ことはさんがクラスの困っている子を見た時、課題の分離では「それは本人の課題」となる。でもアドラーの交友のタスクでは、「どうやってその子と共に歩んでいけるか」を考えることになる。
ことは:
交友のタスクとして考えると、私が感じた「何とかしてあげたい」という気持ちは間違いじゃないんですね…?
あつゆる:
むしろ、それこそが共同体感覚の現れだと言える。アドラーは「常に他者を考慮に入れ、他者に自分を適応させ、他者へと関心を持つようにしなければならない」と言っている。
ことは:
でも、それって境界線がなくなって、相手の問題に巻き込まれすぎてしまいませんか?
あつゆる:
そう!だから「課題の分離」という考え方が出てくる。「課題の分離」は、アドラーの共同体感覚を実践するための手段なんだ。相手を突き放すためではなく、健全な関係性を築くためのものなんだよ。
ことは:
手段…ですか?
あつゆる:
そう。例えば、困っている子に対して、その子の問題を全部背負い込んでしまったら、どうなると思う?
ことは:
(考えて)私も疲れ切ってしまいますし、その子の自立する機会も奪ってしまいますね…。
あつゆる:
まさに。アドラーが言う「関心を持つ」というのは、相手の問題を肩代わりすることじゃない。「誰の課題なのか」をはっきりさせることで、むしろ相手の自律性を尊重できる。そして、その上で「一緒にこの困難を乗り越えていこう」という姿勢を持つことなんだ。
ことは:
(目を輝かせて)なるほど!課題の分離は、つながりを切るためではなく、健全なつながりを作るためのものなんですね。
あつゆる:
その通り!「それは君の課題だから知らない」ではなく、「それは君の課題だから、君が主役。でも君一人じゃない」という感じかな。
ことは:
(深く納得して)分かりました!課題の分離と共同体感覚は対立するものではなく、むしろ補完し合うものなんですね。
あつゆる:
「仕事のタスク」も同じで、アドラーは、仕事というのは社会全体で協力して取り組むものだと考えていた。
ことは:
確かに!みんなが役割を分担して社会を支えていますよね。
あつゆる:
だから仕事も「私の課題」「あなたの課題」って分けるものじゃなくて、みんなで協力して社会に貢献するものなんだよ。ことはさんの教師としての仕事も、社会全体の一部なんだ。
ことは:
(納得して)なるほど!そう考えると、仕事にも全然違う意味が出てきますね。
(少し考えて)ということは…「愛のタスク」も、やっぱり個人の問題じゃないってことですか?
あつゆる:
気づいたね。その通りなんだ。アドラーは、愛情関係も「2人だけの幸福」を超えた意味があると考えていた。
ことは:
2人を超えた…ですか?
あつゆる:
恋愛や結婚、子育てを通じて、私たちは「人類全体の未来」に参加しているということなんだ。愛する人との協力は、同時に社会全体への貢献でもある、と。
ことは:
えー!愛情関係がそんな壮大な意味を持つなんて…。でも確かに、子どもを育てるって、次の世代を作ることですもんね。(感動して)なんだか…すべてがつながって見えてきました。
あつゆる:
そう。これら3つのタスクには、共通する根拠があるんだ。アドラーは「3つの絆」と呼んでいる。
ことは: 3つの絆?
あつゆる:
- 地球という厳しくも限られた環境で生きていること→仕事のタスク
- 人間は弱さゆえ他者と結びついて生きること→交友のタスク
- 人間がやがては将来へ命をつなげる生物であること→愛のタスク
そしてこれらは人間がこの世に生を受けた瞬間から逃れることができない結びつきだというわけさ。
ことは:
確かに…これって、私たちの運命というか宿命というか…。でも、だからこそつながらざるを得ない。
あつゆる:
共同体感覚も、ライフタスクも、この3つの絆も、すべてつながっている。アドラーにとって、これらは単なる心理学理論じゃない。人間がどう生きるべきかという、大きな物語なんだよ。
ことは:
(しみじみと)なるほど…私たちの日常も、そんな大きな流れの一部なんですね。
あつゆる:
その通り。だから私たちは、1人で生きているように見えても、実は常に誰かとつながっていて、誰かの役に立っている。
ことは:
(静かに)協力する意味が、前よりもずっと深く見えてきた気がします。