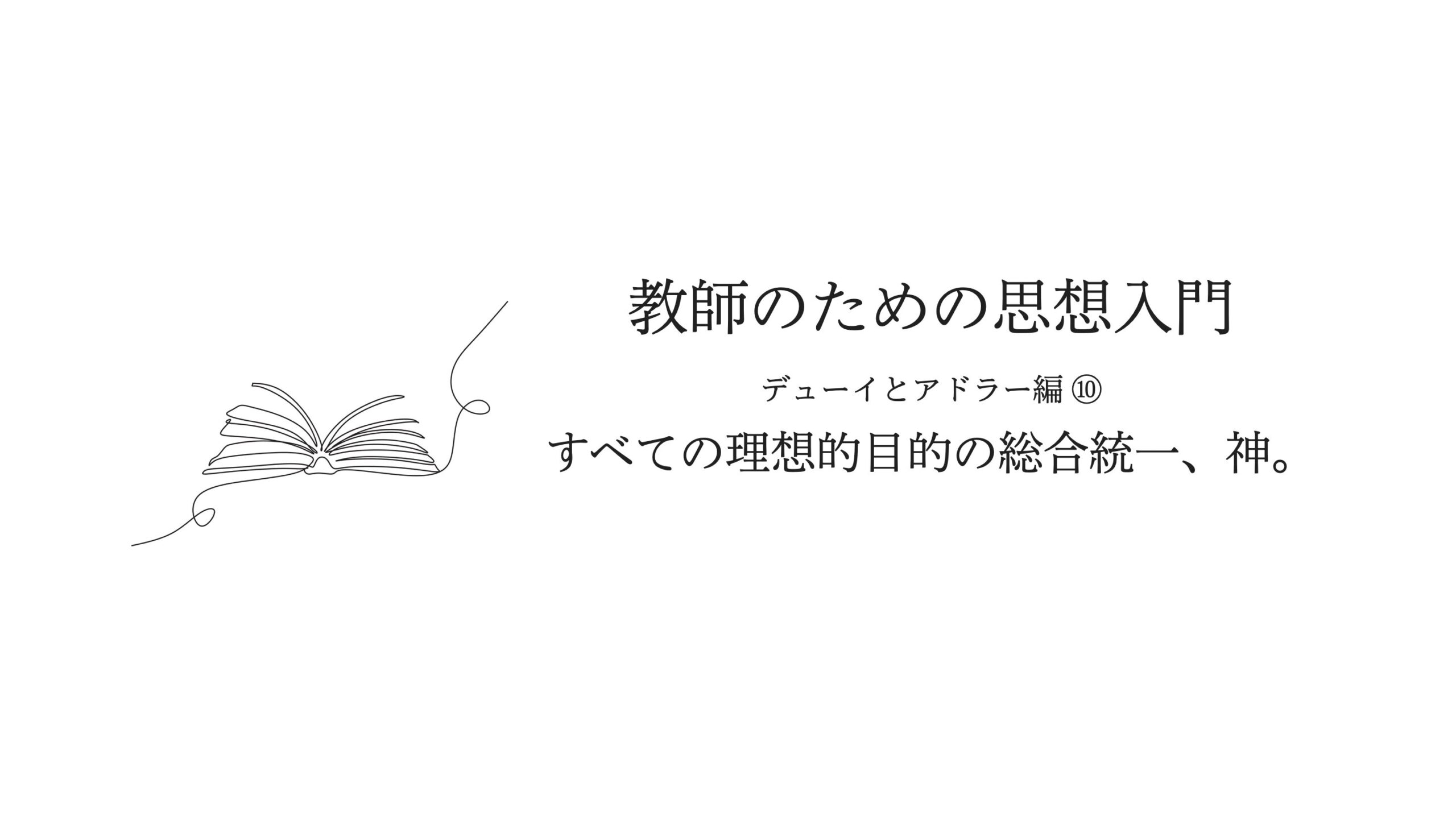▼ 前回の記事はこちら
理想のパワーについて語り合う中で、デューイの『人類共通の信仰』における「宗教的な性質」について学んだことは。理想が人を動かす強い力を持っていることに驚きながらも、さらなる疑問が浮かび上がる—個人の理想を超えた、より大きな理想とは何か…。
ことは:
すべての理想的目的の総合統一!?なんですかそれは!?
あつゆる:
(微笑みながら)驚いたかい?デューイにしては少し大げさな言葉だよね。でも、彼が言いたかったことを少しずつ紐解いていこう。
ことは:
お願いします。なんだか、とても重要なことのように感じます。
あつゆる:
じゃあ、具体例から考えてみよう。駅前再開発の話を覚えてる?
ことは:
はい。商店街の人たちは「歩行者天国」を望み、大型店舗は「駐車場の拡張」を求めて、高齢者は「休憩スペース」を希望して、若者は「インスタ映えスポット」を…みんな違う理想を持ってました。
あつゆる:
(うなずきながら)で、話し合いを続けるうちに何が起きた?
ことは:
最初はバラバラだったのに、「高齢の母が買い物に行けない」とか「子どもの通学路が危ない」といった具体的な課題に目を向けていくうちに、「みんなが使いやすい街」という大きな方向性が見えてきたんです。
あつゆる:
そうそう。「商店街の賑わい」も「利便性」も「安全」も「楽しさ」も、どれも否定されるべきものではない。それらが互いに影響し合いながら、より大きな「みんなが生き生きと暮らせる街」という理想に統合されていった。これが小さな規模での「理想的目的の総合統一」なんだ。
ことは:
なるほど…。でも、「世界平和」と「力による支配」のような、まったく相容れない理想同士でも統合できるんですか?
あつゆる:
(少し考え込んで)本質的な問いだね。デューイの考え方には繊細な部分があるんだ。彼は、人間の具体的な経験から生まれた多様な理想の間には、対話と相互作用を通じて少しずつ近づいていく可能性があると考えていたんだよ。
必ずそうなるという保証はないけれど、そうやって共通点を探していくプロセス自体が、民主主義として大切だってことなんだ。
ことは:
でも、現実的には難しそうですね…。
あつゆる:
(静かに)その通り。だからこそデューイは、抽象的な理想論よりも日々の具体的な課題解決を大切にしたんだと思うよ。
「すべての理想的目的の総合統一」は、すでにどこかに存在する完成品というより、私たちが一緒に目指していく方向性みたいなものだったんだろうね。そして面白いことに、彼はこれを別の言葉でも表現しているんだよ。
ことは:
別の言葉?
あつゆる:
「神」だって。
ことは:
え?(驚いて)神ですか?でも、デューイって宗教的な人じゃないって言ってませんでしたっけ?
あつゆる:
(頷きながら)その驚きは当然だよ。デューイはこう言っているんだ。「神という語は、一つの意味としては、或る特定の存在者を意味することができるだけである。しかし、もう一つの意味としては、『すべての理想的目的の総合統一』を意味する」って。
ことは:
(理解しようと努めて)つまり、超越的な存在としての神ではなくて、私たちの理想が統合されたものを「神」と呼んでいるということですか?
あつゆる:
(手を叩いて)そのとおり!しかも彼が言う理想的目的とは、「我々にそれを願望し、実行することをうながす力をもつ目的」なんだ。つまり、私たちが前回話した「理想の不思議なパワー」を持つものなんだよ。
ことは:
(少し考えて)でも、なぜあえて「神」という言葉を使ったんでしょう?宗教を否定しながら…。
あつゆる:
(背中の本棚から本を引き出しながら)それはね、デューイが宗教から「宗教的な性質」を救い出そうとしたからなんだ。制度としての宗教は批判しつつも、人間が理想に導かれて全身全霊を捧げる経験の価値は認めていたんだよ。
ことは:
ああ、だから『人類共通の信仰』というタイトルなんですね。
あつゆる:
そうなんだよ。翻訳者の解説によれば、「すべての理想的目的の総合統一」の具体的内容は、「個々の人間が現実社会にもとづき、コミュニケーションを介して、共同して創りあげていく『社会の理想』」なんだって。
ことは:
(目を輝かせて)あ!それって、前に話した民主主義とつながりますね!
あつゆる:
(笑顔で)おや、そこに気づいたか!まさに「民主主義の実現」そのものなんだ。
公衆が具体的状況や課題を踏まえて、「よりよい社会を目指すにはどうすればよいか」と、コミュニティの仲間とコミュニケーションしながら考え、課題を解決していく…。そのプロセスで実現される理想が、「すべての理想的目的の総合統一」なんだよ。
ことは:
(少し悩み気味に)でも…それって結局、どこかにある「理想の完成形」に向かっているってことじゃないですか?
あつゆる:
(首を横に振って)ここが理解の分かれ道だね。デューイは一貫して、現実から切り離された超越的な理念や理想を否定している。
ことは:
でも、「神」と言うからには、何か超越的なものが…。
あつゆる:
(両手を広げて)その誤解を避けるため、デューイは何度も強調しているんだ。たとえ「神」という言葉を使っても、それは現実との相互作用の中にあるべきもので、いわゆる「神の計画」のような、人間経験に先だって決まっている超越的なものではないってね。
ことは:
(考え込んで)実際の生活の中から生まれる理想であって、空から降ってくる理想じゃない…ということですね。
あつゆる:
(うなずいて)その通り。デューイは社会の発展も、偶然の産物だと考えているんだ。例えば産業革命。今では大きな社会変革として語られるけど、最初は繊維産業の小さな技術改良から始まったんだよ。当時の人々は「産業革命が起きている」なんて意識してなかった。
ことは:
ああ、確かに歴史の教科書では「産業革命」って大きく扱われてますけど、当時の人は日々の小さな変化を生きてただけなんですね。
あつゆる:
そう。「人間のつながり(社会)のほんらいのあり方と、それが制度として現実に展開した形態とのあいだには、『偶然の』関係しかない」とデューイは言っているんだ。
ことは:
でも、何か大きな計画があった方が安心できるような…。
あつゆる:
(共感を込めて)その気持ち、よく分かるよ。多くの人がそう感じるね。だからこそ「超自然的なもの」に頼りたくなる。でもデューイは、そういう考え方を「かつて無知のゆえに、超自然的なものをもとめた古い憶断の焼きなおしであるにすぎない」と批判しているんだ。
ことは:
憶断?
あつゆる:
根拠のない思い込みってことだよ。例えば、かつては雷が鳴ると「神の怒り」だと考えられていた。でも科学が発展して自然現象だと分かった。
デューイは、「分からないことがあると超自然的なものに頼るのは、知るための努力をさまたげる確実な方法だ」と言っているんだ。
ことは:
(少し戸惑いながら)でも、そうすると私たちは何を信じて生きていけばいいんでしょう?何の計画もない社会で…。
あつゆる:
(優しく)その問いこそ、デューイが真剣に向き合っていたものなんだ。彼はこう考えていたよ。「社会の発展とは、その瞬間の”よりよさ”を生きること、その繰り返しの結果なのである」と。
ことは:
その瞬間の…よりよさ?
あつゆる:
うん。彼の言葉を借りれば、「こんにち生きている我々は、はるか遠い過去からつづく人類の一部分である」。私たちが大切にしているものは、過去から連々と続く人間共同社会の営みのおかげで存在しているんだ。
そして「我々は、その共同社会を連続させる一つの環であるにすぎない」。
ことは:
一つの環…。
あつゆる:
だからデューイは、私たちの責任は「遺産としてうけついだ価値を保存し、伝達し、修正し、発展させる」ことだと言うんだ。
そして「我々の後にくる人たちに、我々がうけついだ遺産より、もっとゆたかで確実な、もっと多くの人が利用でき、もっとたっぷり分かちあえる遺産を、伝えること」。これが彼の言う、世代を超えた責任感なんだよ。
ことは:
(考え込みながら)でも、それって何か方向性があるんじゃないですか?デューイが言う「ゆたかで」「たっぷり分かちあえる」というのは、ある種の理想的な方向ですよね?完全にランダムな変化ではないような…。
あつゆる:
(少し考え込んで)うーん、その問いは本質を突いているね。デューイの考えでは、確かに人類の歴史には大きな流れというか、方向性らしきものはあるんだよ。
でも、それは天から与えられた設計図のようなものじゃなくて、人々の具体的な苦しみや課題への応答から少しずつ形作られてきたものなんだ。
ことは:
人々の応答から…?
あつゆる:
(身を乗り出して)そう。例えば、奴隷制度が廃止されたのは、何か超越的な計画があったからじゃなくて、奴隷の苦しみという現実と、それに対する人々の道徳的感覚が呼応した結果なんだ。
その意味で、理想と現実は常に対話している。理想は現実から生まれ、現実に働きかけ、また新しい現実が新しい理想を生む…この循環の中で、少しずつより良い方向へと進んでいく。
ことは:
なるほど…。固定された「こうあるべき」という理想ではないけれど、「より多くの人が幸せになれる方向」みたいな大きな流れはあるんですね。
あつゆる:
その通り!デューイはそれを「より良い社会」と呼んでいたよ。ただし、何が「より良い」かは、前もって決まっているわけじゃなくて、その時代の具体的な問題に取り組む中で見えてくるものなんだ。だから理想は常に現実と呼応しながら、絶えず更新されていく。
ことは:
(深く考え込んで)…あ!だから理想が必要なんですね。私たちが今を生きる中で、現実を見て「もっとこうなればいいのに」と理想を描く。そして理想のパワーを借りて行動し、少しでも社会をよくしていく…。そうやって、目に見えない大きな流れの一部になっていくんですね。
あつゆる:
(静かに頷いて)その通り。脈々と続いている社会をよりよくしようとする連続的な運動の結果として今があるんだ。
ことは:
(目を輝かせて)理解できました!きっとこれが、デューイの言う「人類共通の信仰」なんですね。神といっても超越的な存在ではなくて、私たち自身がコミュニケーションを通じて作り上げていく理想…それを信じて行動することで、少しずつ社会が変わっていく…。
あつゆる:
(微笑んで)その通り。現実から生まれ、現実に対して実践的に働く、プラグマティックな理念・理想だというわけだね。
ことは:
プラグマティック?それって何ですか?
あつゆる:
(楽しそうに)おっと、専門用語を使ってしまったね。デューイはプラグマティズムという哲学の重要な思想家なんだ。簡単に言うと、「理論が正しいかどうかは、実際の経験の中でうまく機能するかどうかで判断する」という考え方だよ。
ことは:
実際の経験の中で…機能するかどうか?
あつゆる:
(教室を想像するように)そう。例えば教育方法でいうと、どんなに立派な教育理論でも、実際の教室で子どもたちの学びにつながらなければ意味がないよね?
プラグマティズムでは、理論と実践は切り離せないものなんだ。理論は実践の中で検証され、実践は理論によって導かれる…その相互作用こそが大切なんだよ。
ことは:
(ハッとして)あ!それって、これまで話してきた「理想と現実の相互作用」と同じですね!
あつゆる:
(感心したように)その通り!デューイのプラグマティズムでは、「絶対的な真理」や「不変の理想」を否定して、むしろ状況に応じて変化し、具体的な問題解決に役立つ考え方を重視するんだ。
ことは:
だから「プラグマティックな理想」というのは…?
あつゆる:
(両手でジェスチャーしながら)簡単に言えば、「現実に役立って初めて価値がある理想」ということだね。世の中には立派な言葉で飾られた理想や目標がたくさんあるけど、実際の問題解決に役立たなければ「絵に描いた餅」にすぎない。
ことは:
あ、それは分かります!学校の「校訓」とか「教育目標」とか、立派なことが書いてあるけど、実際の教室では忘れられてるってことよくありますよね。
あつゆる:
(うなずいて)そうそう。デューイの言う理想は、現実の問題から生まれ、実際の行動を通じて検証され、状況に応じて変化していく…そんな実践的で柔軟なものなんだ。
「こうあるべき」という固定された理想ではなく、「この状況でどうすれば良くなるか」を常に問い続ける。それがデューイの理想なんだよ。
ことは:
(感慨深げに)なるほど…。学校でも、地域でも、それぞれの場所で人々が現実に根ざした理想を持って行動する。それが全部つながって大きな流れになっていく…。
(ふと)あ、それって「総合統一」ということですね!
あつゆる:
その通り。「すべての理想的目的の総合統一」…つまり、みんなの理想が織りなす大きな物語なんだ。
ことは:
(決意を持って)私も教師として、子どもたちと一緒に、現実の課題から出発して、少しずつでも理想のクラスに近づいていきたいです。それが、大きな社会の流れの一部になるんですね。
あつゆる:
デューイの考え方は、教育者にとって特別な意味を持つよね。彼は教育こそが民主主義を実現する鍵だと考えていたから。
ことは:
(深呼吸して)デューイの思想、とても深いですね。最初は「個」と「協働」の両立という単純な疑問から始まったのに、民主主義の本質、理想とコミュニティの関係、そして理想のパワーまで…。
あつゆる:
(本棚から別の本を取り出しながら)でも、デューイだけが「個」と「協働」について考えていたわけじゃないんだ。実は、前に少し話したアドラーという心理学者も、似たような問題に別の角度からアプローチしていたんだよ。
ことは:
(興味深そうに)アドラー…。そういえば、最初に少し話してくださいましたね。デューイと関連があるんですか?
あつゆる:
(頷きながら)同時代に生きた2人には、驚くほど響き合う部分があるんだ。どちらも「個」と「協働」の問題に真剣に向き合った。特にアドラーの言う「共同体感覚」という概念は、これまで話してきたデューイの思想と深くつながっている。でも、それはまた今度の話にしようか。
ことは:
(明るい表情で)はい、ぜひ聞かせてください!今日はデューイの思想をじっくり噛みしめて、また来ます。
窓から差し込む陽の光が少し傾きかけた頃、ことはは新たな気づきと疑問を胸に、あつゆる書房を後にした。デューイとの対話は終わったが、「個」と「協働」をめぐる探究の旅は、まだ続いていく—。
▼ 続きはこちら