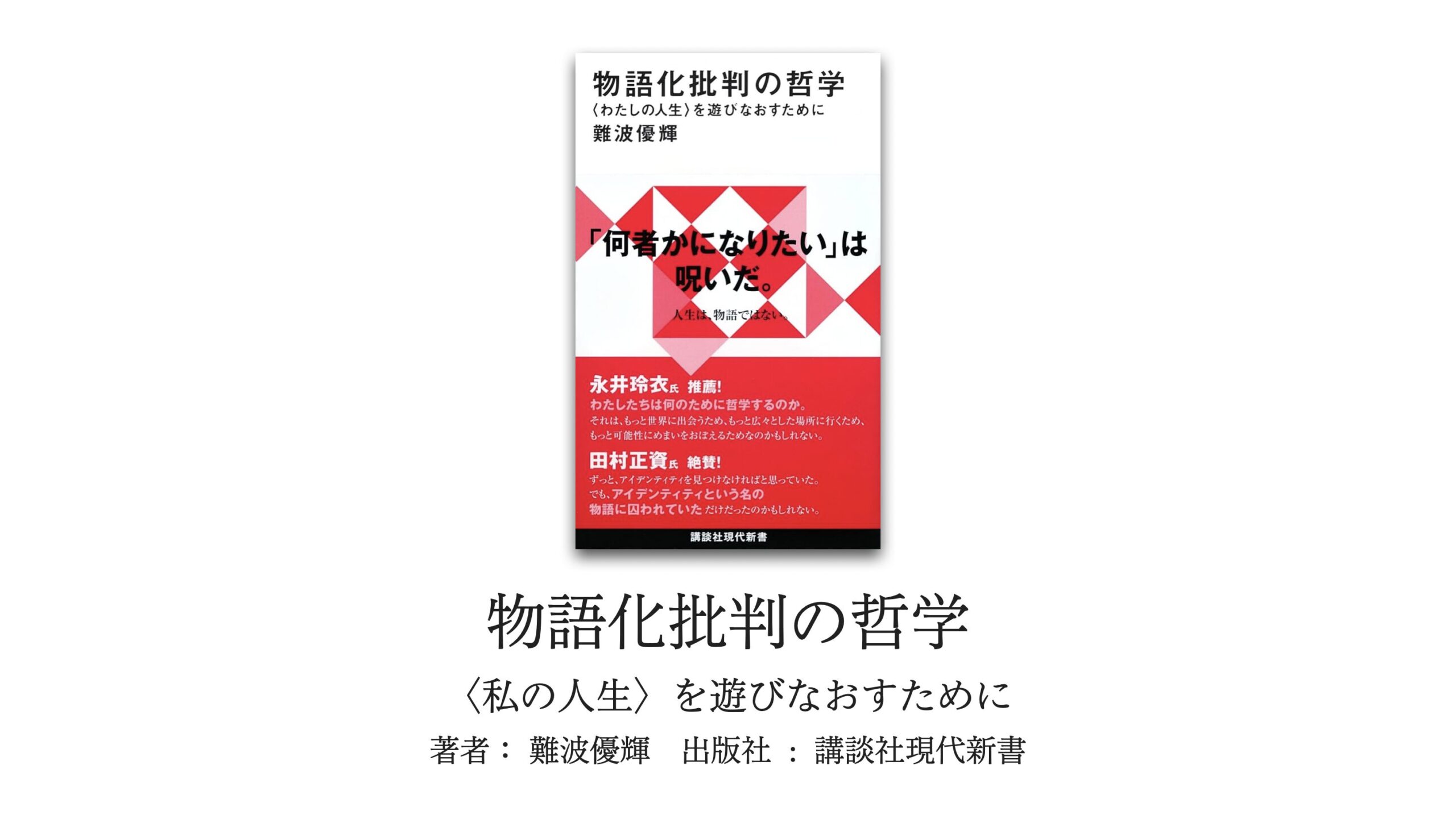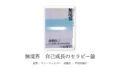あらゆるところで「物語」がもてはやされている。私はそれが不愉快である。物語を愛しているがゆえに。
この挑発的な一文で始まる『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』(講談社現代新書、2025年7月)は、現代社会のあらゆる領域で要求される「物語化」への、愛情に基づく批判を展開した話題作だ。
著者の難波優輝は1994年兵庫県生まれ。会社員として働きながら、立命館大学と慶應義塾大学で研究員を務める。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学で、特に VTuber や SF 研究で知られる。本書は講談社の Web メディア「現代ビジネス」での連載をベースに大幅加筆したもので、現代社会に蔓延する物語化現象に哲学的メスを入れる。
なぜ私がこの本を手に取ったのか。それは現在、アドラー派のカウンセリングを学ぶ中で、日々「物語」の力と危険性の両面を実感しているからだ。
カウンセリングを通じて、クライアントが無意識のうちに生きている個人的な物語に触れる機会が多い。物語化によって人は自分を理解し、意味を見出すが、同時にその枠組みに縛られて苦しむこともある。
だからこそ、物語を愛する美学者による「物語批判」がどのような新しい視座を提供してくれるのか興味を持った。
現代の「物語圧力」への鋭い診断
本書は二部構成になっている。
第一部「物語篇」では、就活のガクチカ、推し活の成功譚、SNS での自己ブランディング、MBTI による性格類型化など、現代社会の「物語化圧力」を分析する。
第二部「探究篇」では、「ゲーム」「パズル」「ギャンブル」「おもちゃ」という4つのオルタナティブを通じて、物語的ではない生き方の可能性を探る。
難波の問題意識は明確だ。「私は端的にこう思う。何かがおかしい、と」——この率直な違和感から出発し、現代人が「何者かになりたい」という願いのもとで、テンプレート化された物語に自分を当てはめることの危険性を浮き彫りにする。
ポカリの CM の「青春」、推し活の感動エピソード、就活の挫折と成長の物語。これらは複雑で矛盾に満ちた人間経験を、単純化された枠組みに押し込める装置として機能している。
この診断には深く共感する。カウンセリングの現場でも、「こうあるべき」という物語に自分を無理やり合わせようとして苦しんでいるクライアントを数多く見てきた。物語の固定化やテンプレート化は、確実に人を縛り、本来の可能性を狭める。
物語の「レベル」を問い直す
ただし、読み進めながら1つの疑問が生まれてきた。著者が批判する「物語」とは、いったいどのレベルの話をしているのだろうか。
ハラリが『サピエンス全史』で指摘したように、人間は「虚構」を共有することで大規模な協力を可能にした唯一の種だ。国家、宗教、企業、貨幣——これらはすべて「共同幻想」としての物語によって成り立っている。このような集合的レベルから完全に逃れることは、現実的に不可能だろう。
一方、個人レベルでも物語性は深く根ざしている。私が学んでいるアドラー心理学の観点から言えば、私たちは幼少期から無意識のうちに「ライフスタイル」という個人神話を獲得し、それを通じて世界を認識し、行動を決定している。
実際、カウンセリングで実感するのは、この無自覚な物語を意識化することで、多くのクライアントが楽になるということだ。重要なのは「物語からの脱却」ではなく、「物語との意識的な関係構築」なのではないか。
著者が提示する「ゲーム」「パズル」「ギャンブル」「おもちゃ」という4つの生き方も興味深い。しかし、これらを選好すること自体、その人なりの深い価値観に基づいている。
ギャンブル的生き方を好む人は「人生は予測不可能で、リスクにこそ価値がある」と考え、パズル的思考を好む人は「世界は論理的に解決可能だ」という信念を抱いているかもしれない。
こうして見ると、物語の階層性や根本的な定義をもう少し掘り下げた上で議論を展開していれば、さらに説得力のある分析になったかもしれない。
「仮固定」と「脱構築」の循環として
こうした理論的な課題を脇に置いても、本書には重要な洞察があると思う。
著者が本当に批判しているのは「物語そのもの」ではなく「物語の固定化」なのだと気づく。
そして、その固定化を崩すものとして提示される「ゲーム」「パズル」「ギャンブル」「おもちゃ」という4つのオルタナティブは、単なる理論的概念ではなく、実際に読んでいて面白く、役立つ視点を提供している。
たとえば、芸人・岡野陽一のギャンブル体験についての引用。
そうして抽選を楽しんでいるうちに、徐々に当たり外れなんてどうでもよくなって、本質がずれていき、「どっちだろう?」とひりひりする時間を軸にして生きるようになってしまった人間、それが私でございます。
ここには、従来の成功や失敗という物語を完全に超越した、純粋な体験の瞬間がある。著者は学術的な文献にとどまらず、こうした生きた証言を通じて、物語に依存しない生き方の可能性を具体的に示している。
こうした事例が示すのは、何事も固まってしまってはダメだということだ。重要なのは仮固定とそこからの脱構築の繰り返し。そして時には、仮固定もない遊びの領域に身を委ねること。
「〈わたしの人生〉を遊びなおすために」という副題に込められた著者の真意は、まさにここにあるのではないだろうか。
完全な物語からの脱却ではなく、物語との柔軟で開かれた関係性の構築。これは、物語を愛するがゆえの批判から導かれた、実に建設的な提案だ。
現代社会の息苦しい物語圧力を感じている読者にとって、この本は新しい自由への扉を開いてくれる。生きた知恵がそこにある。