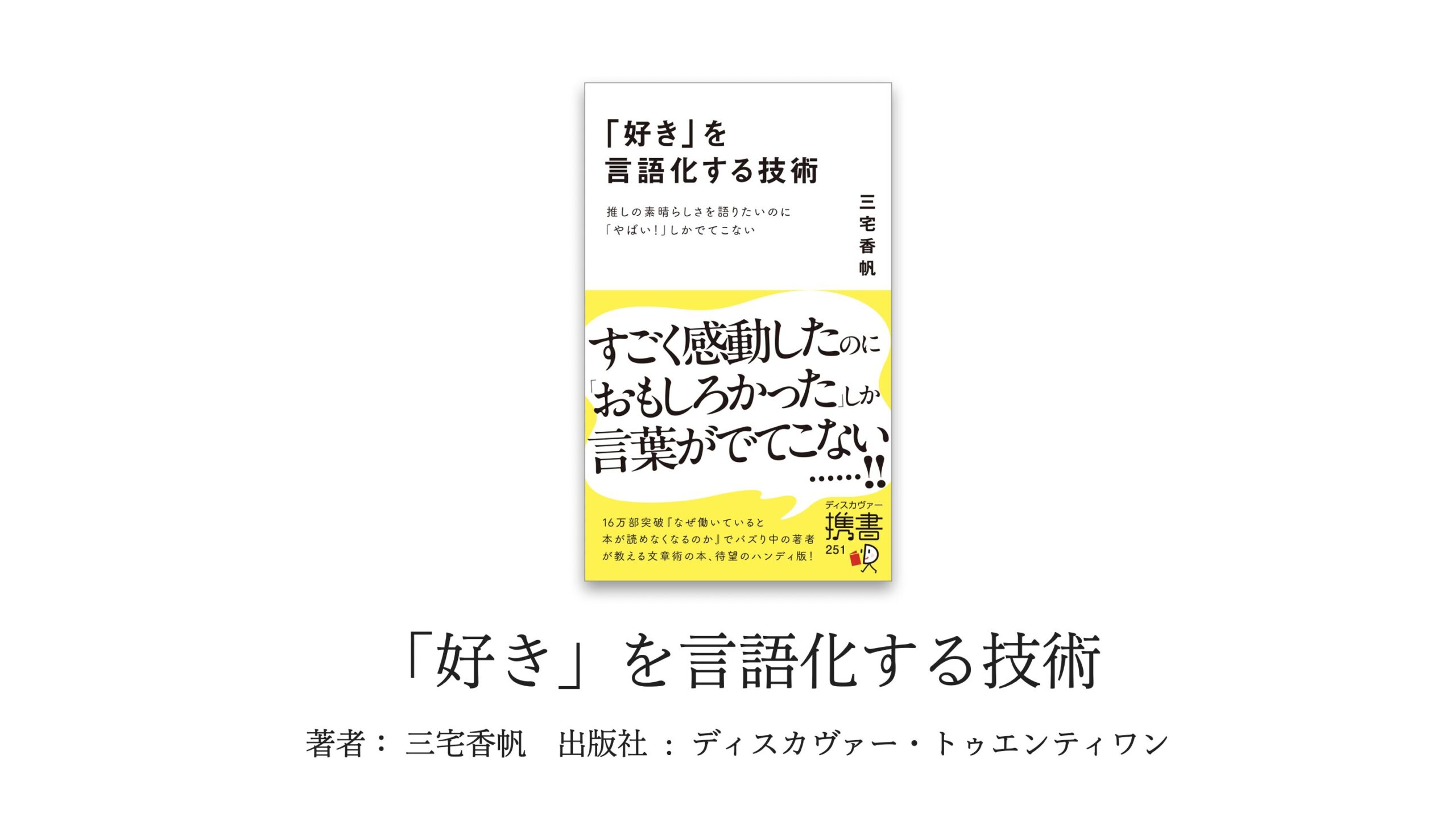「この作品すごくいいよね」
「うん、本当にやばい!」
そして、そこから先の言葉が出てこない――。
誰もが経験したことのあるこの歯がゆさ。
写真家がレンズを通して世界を切り取るように、私たちも言葉で世界を切り取っていきたい。
けれど実際には、推しのことを語ろうとすると「最高!」「神!」という言葉で止まってしまう。
SNS でも、友人との会話でも、いざ推しの素晴らしさを伝えようとすると、言葉に詰まる。
最近では、その言葉探しさえも AI に委ねてしまう。「〇〇の感想を書いて」とプロンプトを入力すれば、それらしい文章が即座に生成される時代。
でも、本当にそれでいいのだろうか?
そんな悩みに向き合うヒントを与えてくれたのが、『「好き」を言語化する技術』(三宅香帆著)だ。
文芸評論家でありながら、自身も熱心な「オタク」として様々な対象への愛を発信している著者による、実践的な言語化の技術書である。
自分の言葉にこだわる
「言語化とは細分化である」——本書が示すこの原則は、私たちの曖昧な感情を言葉に変えていく具体的な道筋を示してくれる。
「このキャラクターの表情が印象的」という漠然とした感想を、まず「どの瞬間の」「どんな表情が」と問いかけ、さらに「緊張の中にある優しさ」「強がりの中の弱さ」というように分解していく。
「考えさせられた」「泣けた」「圧倒された」といったクリシェ(常套句)は、実はより深い言葉への入り口なのだ。
そして、この細分化の前提として本書が強調するのが、「自分の言葉をつくる前に、他人の感想を見ない」という原則だ。これは現代では特に重要な意味を持つ。
先入観なしで向き合い、自分の中から言葉を紡ぎ出す。その過程で、推しへの理解は確実に深まっていく。
このように「言語化とは細分化である」という本書の示す方法は、シンプルでありながら説得力がある。しかし、実際にこの方法を実践しようとすると、思いのほか難しいことに気づかされる。
そう。自分の言葉を丁寧に紡ぎ出すプロセスには、時間がかかるのだ。
時間をかける覚悟を持つ
読書アカウントを運営していると、SNS の誘惑に日々さらされる。
「今月は20冊読破!」という投稿。本を美しく並べた「#読了」や「#今日買った本・届いた本を紹介する」の写真。
それらが大量の「いいね」を集め、フォロワー数を増やしていく。その数字の上昇に陶酔し、もっと読まなければ、もっと投稿しなければと追い立てられる自分がいる。
そこに AI という新しい可能性が加わった。感想文を求めれば、数秒で質の高い文章が生成される。
かつては時間に余裕のある人だけが丁寧な感想を書けた。今では、忙しい仕事の合間でも、AI の支援があれば自分の思いを整理された形で表現できる。
アウトプットの民主化。表現の可能性を大きく広げる変化だと思う。
しかし、この利便性は両刃の剣でもある。
私たちは「すぐに書ける」という誘惑に流され、本来なら時間をかけるべき言語化のプロセスを省略しようとする。
それは AI であれ、SNS の「いいね」への執着であれ、私たちは常に「より早く」「より多く」という誘惑にさらされている。
だが、それでは本当の意味での表現者にはなれない。じっくりと向き合い、咀嚼し、言葉を紡ぐ時間を確保する覚悟がやはり必要なのだという事実に、本書を読んで気づかされた。
“自分の言葉” など本当にあるのか?という問いと、対話の可能性
ただ、ここで1つの問いが浮かぶ。
そもそも「自分の言葉」など、本当にあるのだろうか?
私たちの言葉は結局のところ、過去の経験や出会いの積み重ねの中で形作られてきたものではないか。
そして実際、自分の言葉にこだわって必死に紡ぎ出そうとしても、時として陳腐な言葉しか出てこないことに気づく。ならば、どこまで自分独力の言葉にこだわる必要があるのだろうか。
ブーバーが示唆したように、言葉は対話の中で育まれていく生きたものだ。
それは淀んだ池ではなく、流れゆく川のように、生成し、変化していく。
読書会やカウンセリングの勉強会での経験が、この感覚を鮮明に教えてくれた。
「この小説のこのシーンが印象的だった」という漠然とした感想が、「どんなところが印象的だったの?」という問いかけを通じて、より深い解釈へと育っていく。
この対話のプロセスは、既にある言葉を拾い上げることではなく、新しい言葉が生まれ出でる瞬間との出会いである。
つまり、これは誰かの意見を借りてくることでもなく、かといって完全な独創を目指すことでもない。
対話を通じて自分の中に眠る言葉が呼び覚まされ、新しい発見として立ち現れてくる。
それは過去の経験が結実する瞬間でもあり、同時に新しい理解が生まれる瞬間でもある。
こうした対話は、人との間だけでなく、AI との間にも生まれうる。
「ここがすごいと感じるんだけど、うまく表現できない」
そんな模索から始まる対話を通じて、自分の中の漠然とした思いが少しずつ形を成していく。AI は単なる文章生成の道具ではなく、私たちと共に言葉を探していく対話のパートナーとなる。
言葉は対話の中で磨かれ、深まっていく。写真家がレンズを通して世界を切り取り、画家が絵筆で世界を切り取るように、私たちも言葉で世界を切り取っていく。
それは必ずしも1人で成し遂げる必要はない。むしろ、様々な対話を通じて、自分の言葉は豊かに育っていくものだから。
大切なのは、その過程で安易な近道を選ばず、じっくりと時間をかけて言葉と向き合う覚悟を持つこと。
「この人が語ると世界が違って見える」。そう思われる表現者になることは、容易な道のりではない。
しかし、推しを語ることは、そうした固有の視点を磨いていく、かけがえのない練習の場なのだ。
三宅香帆さんの著書『「好き」を言語化する技術』『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、“聴く読書” Audible(オーディブル)の無料体験に登録すると、無料で視聴できます。