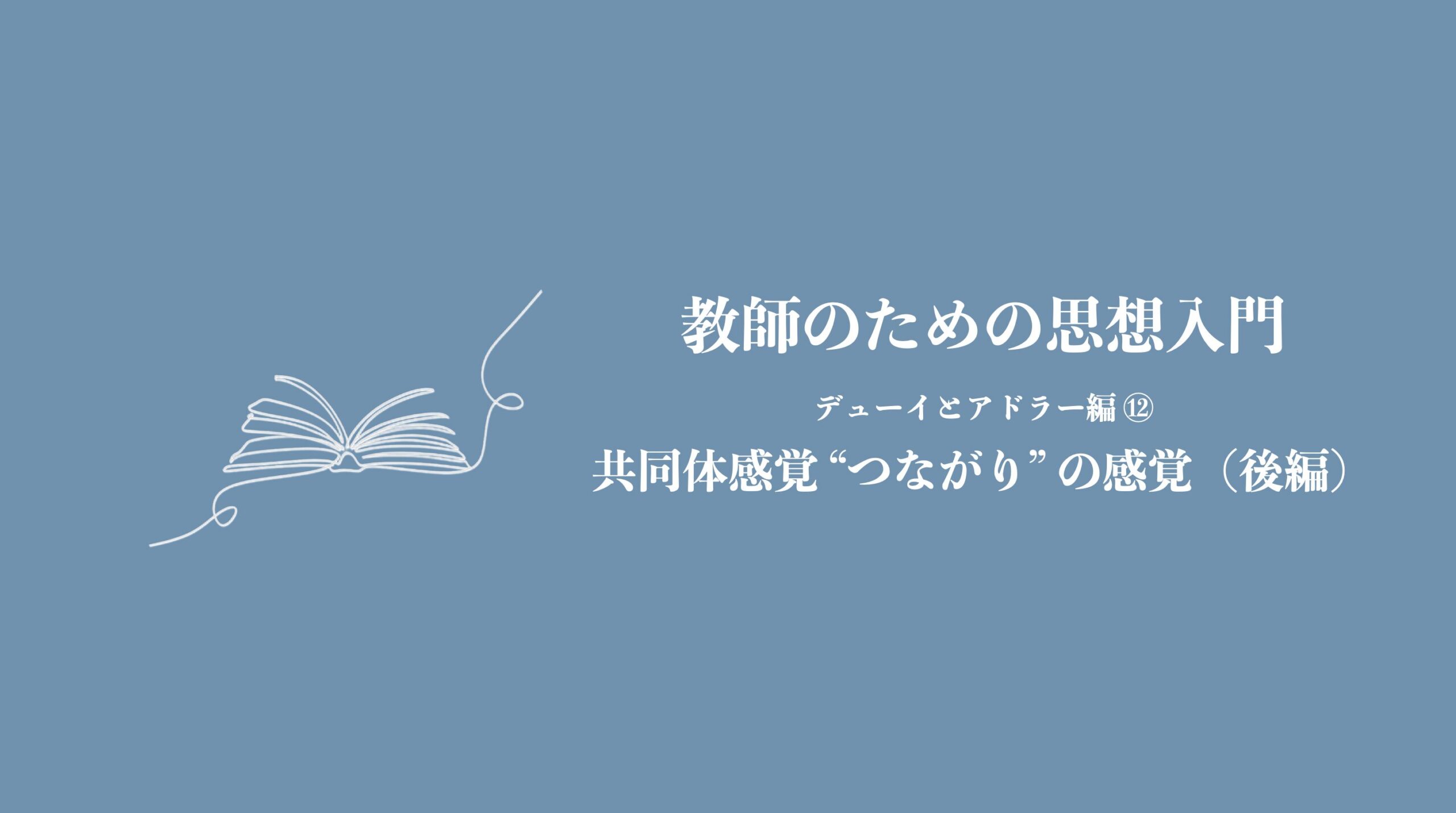▼ 前回の記事はこちら
デューイの実践で新たな課題に直面したことはは、「つながろうとする気持ち」の根源を求めてアドラーの「共同体感覚」について学んだ。それは「つながりの感覚」と「関心」という2つの要素から成るものだった。しかし、仲良しグループのように身内だけに限定された関係では真の共同体感覚とは言えない。では、アドラーの描く共同体感覚には、どんな特徴があるのだろうか…
あつゆる:
アドラーの共同体感覚は、身内だけの「仲良しクラブ」では終わらない特徴があるんだ。
ことは:
え…それってどんな特徴なんですか?
あつゆる:
その前に1つ聞いてみよう。ことはさんは環境問題について考えていることはある?
ことは:
(少し驚いて)環境問題ですか?急に話が変わりましたね。でも、気になります。プラスチックゴミとか、地球温暖化とか…。
あつゆる:
なぜ気になるんだろうね?
ことは:
(考えながら)うーん…将来の子どもたちが困るからでしょうか。今の子どもたちが大人になった時に、住みにくい地球になってたら可哀想だなって。
あつゆる:
その「将来の子どもたち」って、ことはさんの生徒だけかな?
ことは:
(ハッとして)あ…いえ、世界中の子どもたちです。会ったこともない子たちも含めて。
あつゆる:
ほら、ことはさんも既に仲良しグループの枠を超えて考えているじゃないか。
ことは:
(驚いて)本当ですね!確かに、地球全体のことを考えてました。
あつゆる:
それがアドラーの共同体感覚の特徴なんだよ。最初は身近な人から始まるけど、やがて境界を超えてどんどん広がっていく。母親から始まって、家族、そして一族、国家、全人類…「良好な状態の時には、家族だけではなく、一族、国家、全人類にまで拡大」し、この限界を超え「動物、植物や無生物まで、ついには、宇宙にまで広がる」ものなんだね。
ことは:
(目を丸くして)宇宙まで!?それってちょっと…スケールが大きすぎませんか?
あつゆる:
最初はそう感じるよね。でも、ことはさんが環境問題を心配するとき、地球全体の未来を考えているのと同じことかもしれない。
ことは:
(なるほどという表情で)ああ…確かに、そう考えると繋がってますね。
あつゆる:
そう。アドラーが描いた共同体は、家族・学校・職場・国家みたいに “境界線を引いて内側と外側が決まる閉じた全体” ではない。むしろ外へ外へと開かれる「全体性」なんだ。
ことは:
開かれた全体性…。(考え込んで)でも、そうすると何が正しいかって、どうやって判断すればいいんでしょう?みんながそれぞれ違う「正しさ」を持っていたら…。
あつゆる:
いい着眼点だね。実際、歴史を見ると、ある時代に「正しい」とされていたことが、後から見ると間違いだったということがよくある。
ことは:
ああ、確かに…戦争中なんかも「お国のため」が絶対的に正しいとされていましたよね。
あつゆる:
まさにそう。アドラー自身もそうした体験をしている。彼は第一次世界大戦を経験し、その後ナチスが台頭する中でユダヤ系として迫害を受けた。
歴史が証明しているように、既存の共同体は時に間違うものであることを身をもって感じたんだろうね。だからこそ、既存の枠に縛られない「まだ見ぬ共同体」を目指すべきだと考えたのかもしれない。
ことは:
まだ見ぬ共同体…。
あつゆる:
アドラーは「人類が完全なる目標へと到達した時に考えることができるような、永遠に適用できるもの」として共同体を捉えていたようだね。つまり、今ここにある完成品ではなく、私たちが目指し続ける方向性のようなものだろう。
ことは:
(安堵して)それなら、完璧になる必要はないんですね。でも…
あつゆる:
でも?
ことは:
(少し困った顔で)そんな壮大な「まだ見ぬ共同体」の話を聞いていると、私みたいな一教師が日々細々とやっていることなんてちっぽけだし、意味があるのかな…って思えてきちゃいます。
あつゆる:
でも実は、ことはさんの日々の実践こそが、その大きな流れの一部だと言える。アドラーは「全体の部分として生きる」という表現をよく使うんだけど…
ことは:
(少し身構えて)全体の部分!?ちょっと怖い感じもします。「個人よりも全体が大事」みたいな…?
あつゆる:
確かに!アドラーのこの表現は全体主義に誤解されかねないと僕も思う。でも、ここでアドラーが言う「全体」は、学校・職場・国家みたいに閉じた全体ではなくって….
ことは:
そうか!「境界なく膨張・変化を続ける全体性」でしたね。
あつゆる:
その通り!つまり、固定された枠組みじゃない。そして重要なのは、アドラーにとって個人というのは、全体性の部分(part of the whole)として、他者と結びつきながら生きる社会的・関係的な存在だということなんだよ。
ことは:
社会的・関係的存在…1人では生きていないということですか?
あつゆる:
まさに。関係の網の目の中で個はつながり合い、そのつながりが全体性を作り出す…。ことはさんと私がここで対話している、これも小さなつながりの1つだね。
ことは:
(考え込んで)そうか…私が学校で子どもたちと関わって、子どもたちも家族や友だちと関わって…それがどんどんつながっていって…
あつゆる:
その通り!そしてそれは身近な関係から始まり、やがては時空をも超え、宇宙にまで広がっていく…。
ことは:
(目を輝かせて)ああ、なるほど!一人ひとりの関係が網のように広がって、大きな全体性を作り出すんですね。
あつゆる:
そう。そして、つながりによって作り出される全体性には、厳密に境界を引くことはできず、閉じた全体はどこにもないというわけ。
ことは:
(深く考え込んで)それで…共同体感覚というのは、その大きなつながりの中で自分の位置を感じ取ることなんでしょうか?
あつゆる:
だいぶ掴めてきたね。これまでの話をまとめつつ共同体感覚を定義すると「広大なつながりの中、全体性の部分として自分があるという感覚、そしてつながり先の他者、自分の属する全体性へと向けられた関心」だと言えるだろう。
ことは:
つながりの感覚と関心…前回学んだ2つの要素が、こんなに大きな世界の中での話だったんですね。
あつゆる:
そうなんだよ。最初は身近な「人ごとじゃない」という感覚から始まって、それが世界全体、宇宙全体にまで広がっていく可能性を持っている。
ことは:
(決意を込めて)私の教室での1つ1つの関わりも、きっとその大きなつながりの一部になっているんですね。
あつゆる:
その通り!ただ、共同体感覚がどう具体的に実現されるかについては、もっと詳しい話があるんだ。
ことは:
(興味深そうに)ぜひ聞かせてください!
あつゆる:
(本を閉じながら)それはまた今度、じっくりと話そう。きっとことはさんの教育実践にも役立つと思うよ。
ことは:
(明るく)楽しみにしています!今日は共同体感覚が、こんなに壮大で、でも身近なものだということが分かりました。
あつゆる:
壮大で身近…いい表現だね。それがアドラーの共同体感覚の本質かもしれない。
▼ 続きはこちら