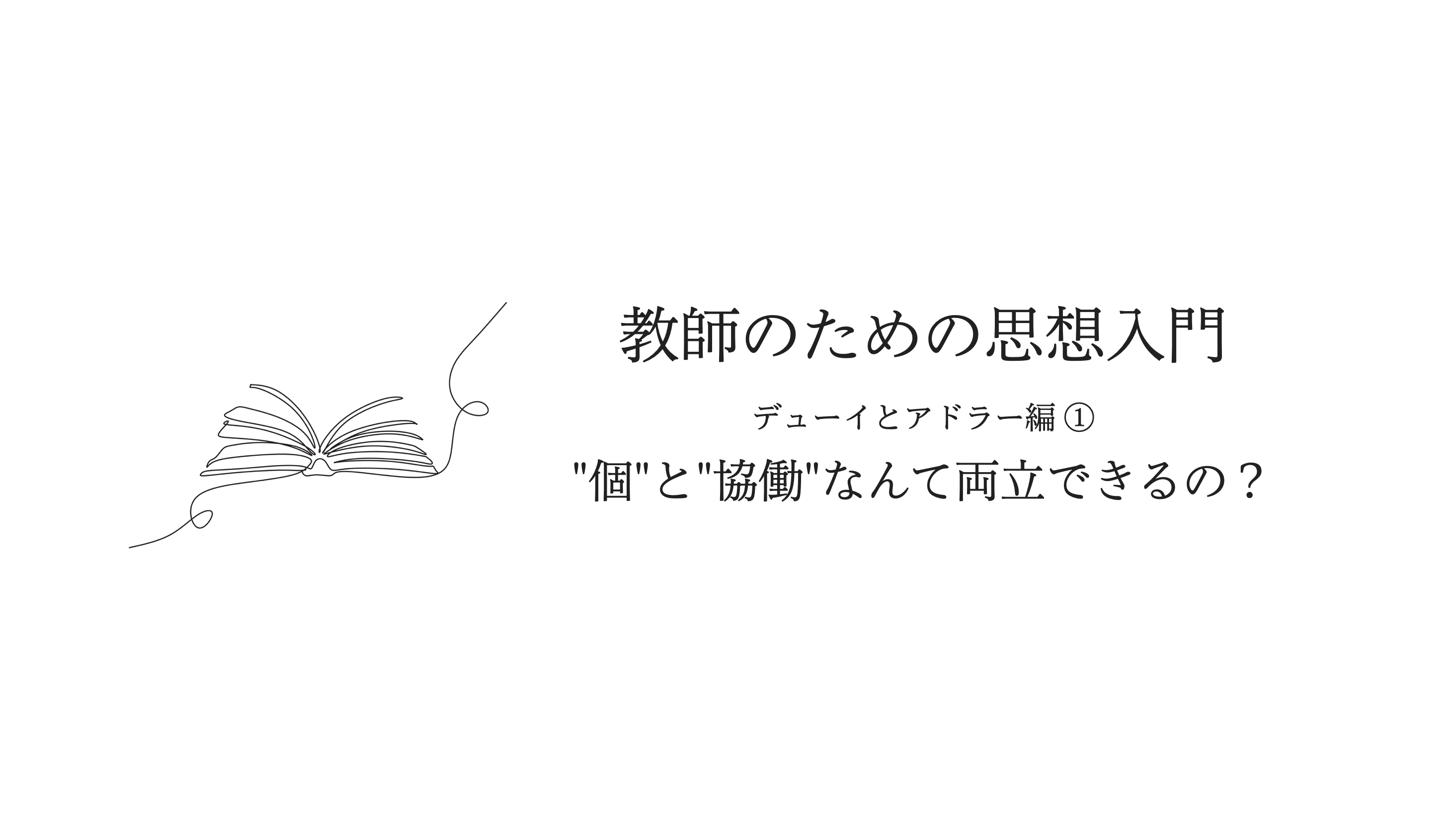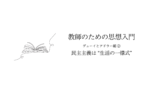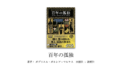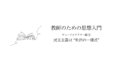登場人物紹介
ことは:公立中学校の教員3年目。熱心で行動力のある性格で、生徒思いの若手教師。新しい教育方法に興味があり、様々な実践にチャレンジしているが、理想と現実のギャップに悩んでいる。中学時代の恩師との出会いがきっかけで教師を志した。
あつゆる:「あつゆる書房」店主。教育や哲学、心理学などに幅広い知識を持ち、本屋に訪れる様々な人々の相談相手となっている。かつて教壇に立った経験を持ち、その経験が今の仕事に活きている。
春の陽気が漂う4月のある日、ことはの行きつけの本屋「あつゆる書房」にて。教科書や参考書が並ぶ教育書コーナーの前で、ことはは立ち尽くしていた。
あつゆる:
本の整理をしながら、おや、ことはさん。珍しく静かだね。何か探してるの?
ことは:
あ、あつゆるさん…。その…うまく言葉にできないんですけど…。
あつゆる:
今日の授業のこと?
ことは:
(驚いて)え!?どうして分かったんです?
あつゆる:
この時期の若手教師さんによくある表情だから。それに、私も昔教壇に立っていた時は…。
ことは:
あつゆるさんも教師だったんですか!?
あつゆる:
ああ、でもそれはまた今度の話。それで、今日はどんなことがあったの?
ことは:
ICT を活用した「個別最適な学び」を実践してみたんです。生徒1人1人にタブレットを持たせて、自分のペースで学習を進められるように…。でも…。
あつゆる:
でも?
ことは:
確かに、全員が自分のペースで進められて、理解度も上がったみたいなんです。でも…教室の空気が変わってしまって。
あつゆる:
教室の空気?
ことは:
はい。みんな黙々とタブレットに向かって…。休み時間も、SNS でメッセージを送り合ってるのに、となりの席の子と口をきかない。「グループで話し合おう」って声をかけても、表面的な意見交換で終わっちゃう…。
あ!でも、面白いことがあったんです。昨日、システムのトラブルでタブレットが使えない時間があって…。
あつゆる:
それで?
ことは:
不思議と、生徒たちの会話が増えたんです。「ここ、どう解くの?」って自然に聞き合って…。でも、それって本当に不思議で…。
(少し考え込んで) あつゆるさん…。私、最近本当に悩んでるんです。
あつゆる:
うん、どんなこと?
ことは:
(真剣な表情で)授業で「みんなで協力することが大切だよ」って言うんですけど…。ある生徒が言ったんです。「先生、最近の AI の進歩ってすごいじゃないですか。これからの時代、本当に人と関わる必要あるんですか?」って…。
あつゆる:
なるほど。難しい質問だね。
ことは:
私なりに説明しようとしたんです。「協力することで新しい発見があるよ」とか…。でも、自分でも心に落ちない感じがして。
だって、考えてみてください。今って本当に “個の時代” ですよね。自己実現、自己責任…。「あなたはあなた、私は私」が当たり前の価値観で。SNS だって、結局は同じ考えの人とだけつながって、違う意見の人は最初からブロック。テクノロジーの進歩で、確かに個人でできることはどんどん増えていって…。
(静かに) 本当に、協働って必要なんでしょうか?
あつゆる:
(少し驚いたように)…その問い、とても大切だと思う。
ことは:
他の先生に相談したら、「それは当たり前でしょう」って。でも、「当たり前」って言われても、今の子どもたちに説明できなくて…。
あつゆる:
私も教員時代、似たような壁にぶつかったことがあるんだ。
ことは:
え?あつゆるさんも?
あつゆる:
うん。必死に理論を学んで、それを実践しようとして…。でも、生徒の目の前で言葉が詰まっちゃって。「なんでそんなに協力が大事なの?」って聞かれて、答えられなかった。
ことは:
それで、どうされたんですか?
あつゆる:
その時に出会ったのが、この本なんだ。1916年に書かれた…。
ことは:
え?そんな古い本が何か…?
あつゆる:
ちょっと読んでみて。
ことは:
(息を呑んで)「個人の独立性の増大が個人の社会的能力の減少をもたらすことになる危険がつねにある。個人がより自立的になるにつれて、その個人はより自己満足的になる…」
…これ、まさに今の私のクラスの…!でも、なんでこんな古い本に…?
あつゆる:
ジョン・デューイという教育哲学者の言葉なんだ。彼の時代も、産業革命で社会が大きく変わる中で、人々の関係性が変化していった。そして、もう一人…アルフレッド・アドラーという心理学者も同じような危機感を持っていた。
ことは:
アドラー…名前は聞いたことがあります。確か…アドラー心理学?
あつゆる:
そう。彼はこう警告したんだ。「孤立した生活を送っているために、人間の本性については誰も知らない。〔…〕我々は同胞たちとの接触を十分に見つけることができないために、彼らは我々の敵となってしまうのである。」
ことは:
(深く考え込んで)…私、ずっと悩んでたんです。「個」を大切にしろって言われる一方で、「協働」も大事だって。AI や ICT で個別最適化が進む中で、どうやってバランスを取ればいいのか…。でも、その悩みって、100年も前から…?
あつゆる:
そうなんだ。テクノロジーは変わっても、人間の本質的な課題は変わらないのかもしれない。でも、彼らは単に問題を指摘しただけじゃない。もっと積極的な意味での「協働」の可能性を見出そうとしたんだ。
ことは:
(目を輝かせて)積極的な意味での「協働」…?
あつゆる:
うん。デューイの「民主主義」とアドラーの「共同体感覚」という考え方なんだけど…。
ことは:
その考え方…今の教育現場でも活かせるんでしょうか?
あつゆる:
それを一緒に考えてみない?きっと、ことはさんの実践にも新しい光が見えてくるはずだよ。
春の柔らかな日差しが本屋の窓から差し込み、新しい本の匂いが漂う中、教育の本質を探る旅は、ここから始まる。
▼ 続きはこちら
参考文献
Adler, A. (1926) Menschenkenntnis. Leipzig: Hirzel. = (1927) Understanding Human Nature. Translated by Wolfe, W. B. New York: Greenberg, Publisher, Inc.=(2008)『人間知の心理学』岸見一郎訳 アルテ
Dewey, J. (1916) Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education. In: Boydston, Jo Ann (ed) (1980) Collected Works of John Dewey, The Middle Works, 1899-1924(9) Carbondale: Southern Illinois University Press. =(1975)『民主主義と教育(上)(下)』松野安男訳 岩波文庫