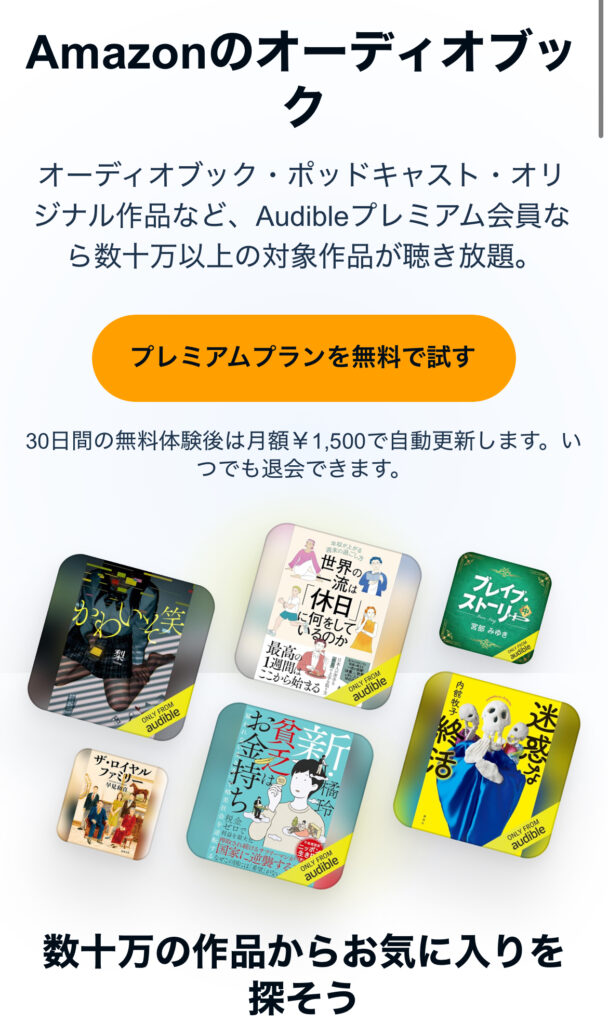「ソクラテスの教育思想・哲学について知りたい」
そんなあなたのために、ソクラテスの教育思想について“無知の知”や“問答法”徹底解説します。ソクラテスは対話を通じて真理を追究することで、1人1人が「善く生きる」ことを目指しました。
この記事はつぎの書籍を参照し、大学院でホリスティック教育、哲学を専攻してきた執筆者によって書かれています。 『教育の哲学―ソクラテスから“ケアリング”まで』ネル・ノディングス 著、宮寺晃夫訳 『西洋教育思想史』眞壁宏幹著 『時代背景から読み解く西洋教育思想』藤井千春編著 『西洋の教育の歴史と思想』山﨑英則・山本達夫編著 『史上最強の哲学入門』 飲茶著 『プロタゴラス―ソフィストたち』プラトン著、藤沢令夫訳 『ソクラテスの弁明・クリトン』プラトン著、久保勉訳
ソクラテスの教育思想をわかりやすく解説(無知の知・問答法とは)
ソクラテスの人物像
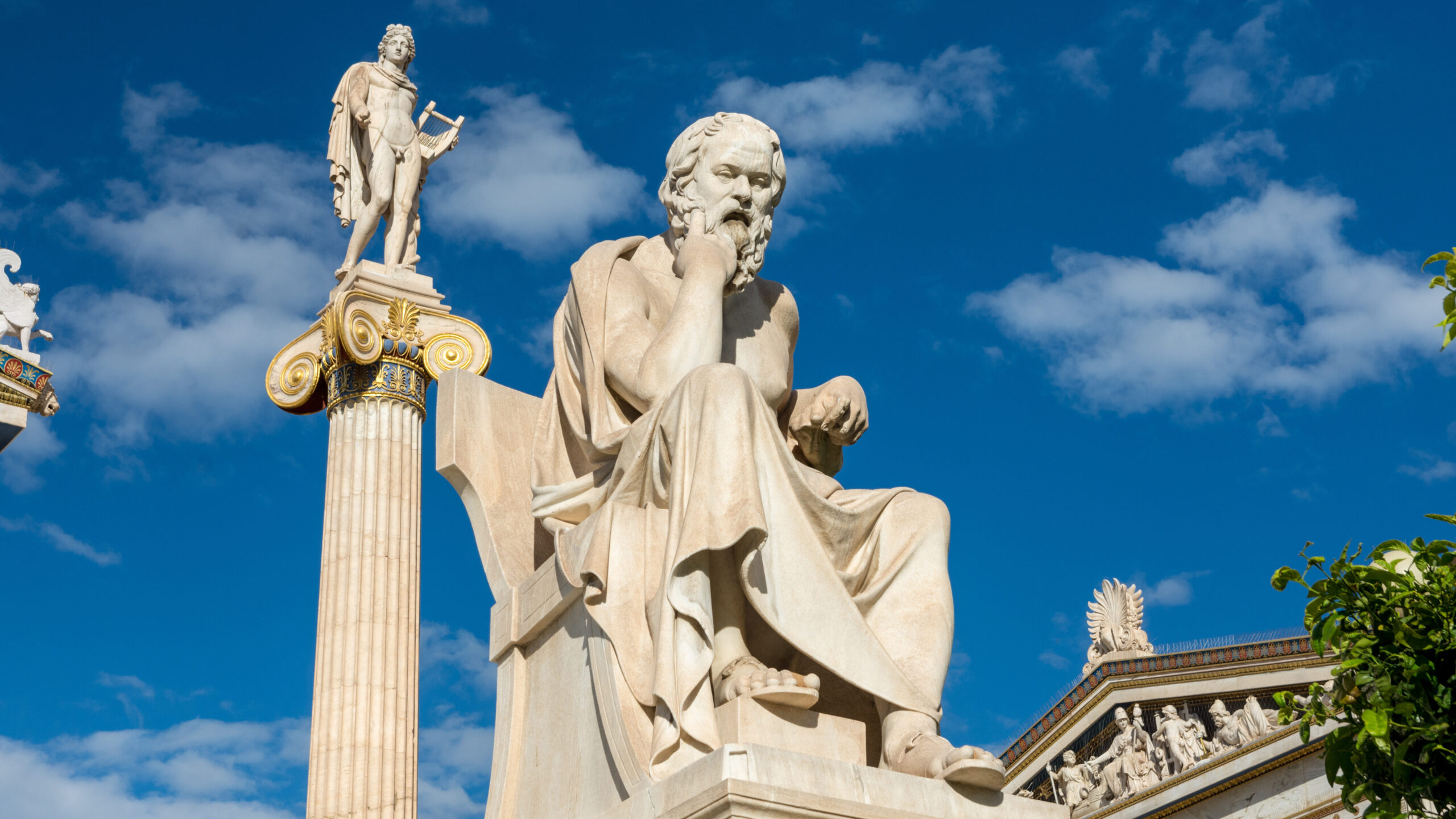
ソクラテス(Socrates, BC469-BC399)は、古代ギリシア、アテナイの全盛期から斜陽期にかけて生きた哲学者・教育者。釈迦、孔子、キリストと並んで四聖(しせい)に数えられることもあるほどの、すごい人です。
ただしソクラテスについてわかっていることの全ては、ソクラテスの弟子、特にプラトンが書いた内容によるもの。ソクラテス自身は著書を残していません。彼は書くことによってではなく、ほかの人々を対話に巻き込むことによって教えました。

ソクラテスの妻クサンティッペは”悪妻”として有名。ソクラテスは「結婚したまえ。良妻を得れば幸福になれるし、悪妻を得れば哲学者になれる」という名言を残したそうです。
ソクラテスと対比されるソフィストと相対主義
ソクラテスを理解するためには、まず彼が生きた時代背景を知らなければなりません。ソクラテスの生きた古代ギリシアのアテナイでは、経済的繁栄の一方、ポリスの人々を結びつけてきた伝統的な価値観が揺らいでいました。
そんな中で力を持っていたのは、ソフィスト1と呼ばれる職業的教育家でした。ソフィストたちの得意技は相対主義。相対主義とは「絶対的な真理などない、真理とは相対的なもの」だという立場。つまり「価値観・考え方なんて人それぞれだ」という主義・主張のことです。
最初のソフィストと言われるプロタゴラス(BC490頃-BC420頃)は、
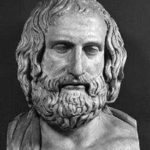
人間は万物の尺度である
という言葉を残しています。これはつまり、ある事柄がよいか悪いか、肯定か否定かなど、その基準は1人1人の中にある…。逆にいうと、事柄そのものに価値があるわけではないということになります。
この相対主義は、当時のアテナイではとても重宝されました。なぜなら、相対主義はとにかく議論に強いという特徴があるからです。
たとえば「君のこの考えは間違っている」と言われたとき、相対主義なら「考え方は人それぞれだから、価値観を押しつけるものではないよね」と伝えることができます。どれだけ悪いことを企んでいても、相対主義なら「それはあなたの見方であって、見方を変えればよいことだよね」と反論することもできるでしょう。
当時のアテナイの民主政治は、とにかく口の上手い奴が勝つ世界。つまり、人々を自分の見解に引き込む説得力をもち、自分の意見に相手を同意させる力をもつ者こそが、正しい判断をする者であり、有徳な者であると考えられていました。
そこで、相手を議論に打ち負かす弁証法や弁論術を求め、多くの人がソフィストに相対主義を教えてもらおうとしたのです。

こうしたソフィストの教育は、家系・財産などを問わず、社会的・政治的に活躍できる可能性があるとして、若者たちの野心を煽ったといいます。
また、若者の背後には教育熱心な親たちの存在もあったようです。

「いい学校」に入り「いい仕事」に就くために、教育に高いお金を払うというのは、現代でもよくある話な気がするね〜
ただし、相対主義の考えを推し進めてしまうと、

どうせ絶対的なことなんてないのだから、適当でいいのでは?
といった具合に、一生懸命考えることを放棄してしまうことにつながります。そして、人々が考えることを放棄したとき、採用されるのは口の上手い雄弁な政治家や、もっともらしく話をするだけの煽動政治家の意見ばかりになってしまうのです。
「このような社会でいいのだろうか?」そんな問題意識をもったのがソクラテスでした。彼は、対話を用いて“普遍的な真理”を探究することを通して、ポリスの市民としての“善い生き方”を自覚させようとしたのです。
ソクラテスの教育の特徴

ソクラテスの教育の特徴として、
- ソクラテス法、産婆術
- 無知の知
- 普遍的な知、絶対的な徳の追究
- より善く生きること
について解説していきます!
ソクラテス法(対話法)・産婆術
ソクラテスの得意技、それはソクラテス法とも呼ばれる対話法でした。これは問答の中で相手の知を吟味し、無知を自覚させていく方法です。青年の魂の誕生に立ち会う産婆の役割を果たしたという意味で、産婆術とも言われています。
ソクラテスはこの対話法を用いて、えらい政治家やソフィストたちを次々と論破していきました。ソクラテスはまず、政治家やソフィストの前にバカのふりをして出て行き、
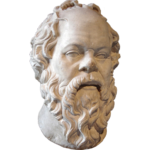
今、正義って言ったけど、正義って何ですか?
という具合に相手に質問をします。それに対し相手が

それはみんなの幸せのことだよ
などと答えたら
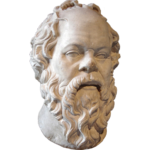
じゃあ、幸せってなんですか?
という具合に、さらに質問を続けていきます。これをくり返せば、相手は

え〜…う〜んと…そ……それは〜
という具合に、いつか答えに詰まるようになります。そこで、すかさず
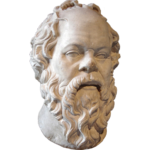
答えられないってことは、あなたはそれを知らないんですね。知らないのに今まで語っていたんですね(笑)
と、思い切り馬鹿にするのです2。
プラトンの著書に、対話編『プロタゴラス』があります。
この中では「徳」を知っていると自負するソフィストのプロタゴラスに対して、ソクラテスが問いを重ねて相手の答えを丁寧に吟味していく様子が描かれています。
徳についての問答を通して明らかにされるのは、ソフィストが実は徳が何であるかについて無知であるということ。それをさも知っていると自負し、自分は徳を教えることができると主張するソフィストの矛盾を、ソクラテスは問答を通して浮かび上がらせるのです。
また、ソクラテスは誰とでも分けへだてなく対話しました。参加者は出入り自由、ソクラテスの問いに答えても答えなくてもOK。対話において、ソクラテスは引き込み、問い詰め、質問という形で知識を与え、聞き手に対し自身の思考の誤りにやんわりと気づかせていきます。
ソクラテスの役割は「教師」と見ることはできるでしょう。ただし、ソクラテスは自らを「教師」や「ソポス(知者)」ではなく、「ピロソポス(知を求める者、哲学者)」と呼んだのです。
彼は誰かに何かを教えるというよりも「知を探究したい!共に知を探究しよう!」という思いだったのかもしれません。事実、ソクラテスは対話の相手に対価を求めるようなこともなかったので、職業的な教師でもありませんでした。
なお、ソクラテスの方法は、現代的にいえば、教える(teaching)というより、学習(learning)や探究(inquiry)であるといえます。また、ソフィストの方法が注入主義と呼ばれるのに対し、ソクラテスの方法は開発主義というように分類されることもあります。
無知の知

ソクラテスといえば「無知の知」という言葉が有名です。ソクラテスにとって「真の知恵」の探究の第1歩は、自分自身の無知を自覚すること(無知の知)でした。
なぜなら人は「自分は知っている」と満足しているとき「もっと知りたい」とは思わないから。“知らない”ことに気づいたとき、つまり「無知の知」によって初めて人は“知りたい”と思い、そこから探究が始まるのです。
また「真の知恵」は教師から生徒に直接的に教えることはできず、1人1人が自ら探究するしかないと、ソクラテスは考えていました。そのためソクラテスは、まず第1段階として相手との問答によって、相手に自分が無知であることに気づかせます。(無知の知)
その上で、第2段階としてさらに問答を積み重ね、相手がみずから“真の知恵”を発見する手助けをしたというわけです。
普遍的な知、絶対的な徳の追究
社会の中で巧みに生き抜く方便を伝授したソフィストに対して、ソクラテスは本質的なもの、普遍的なものを追究する人間を育てようとしました。
彼が関心を寄せていたのは、例えば、
- いかにして真理を見出すことができるのか?
- 何かを知るというのはどういうことなのか?
- 悪とは何か?
- 私たちは国に何を負っているのか?
- 国は私たちに何を負っているの?
などの、人生の大問題ばかり。この中でソクラテスは人生を相対的にとらえるのではなく、絶対的な道徳、徳を追究したのです。
ただ、絶対的な徳を知ることなんて可能なのでしょうか?『ソクラテスの弁明』の中で、ソクラテスは「神だけが本当の知者なのかもしれない」と述べています。しかし、それでもなお彼は「吟味のない生活は、人間の生きる生活ではない」と考え、探究することを止めませんでした。
より善く生きること
一番大切なことは単に生きることそのことではなくて、善く生きることである。
『ソクラテスの弁明・クリトン』プラトン著、久保勉訳 p86
ソクラテスは “普遍的な知・絶対的な徳” を探究することで、“より善く生きる”ことを目指しました。当時のアテナイの人々は、金銭・地位・名声など、自分の外面を飾り立てるものに傾く風潮がありました。このことを、ソクラテスは次のように嘆きます。
アテナイ人でありながら、最も偉大にしてかつその智慧と偉力との故にその名最も高き市の民でありながら、出来る限り多量の蓄財や、また名聞や栄誉のことのみを念じて、かえって、智見や真理や自分の霊魂を出来得る限り善しすることなどについては、少しも気にもかけず、心を用いもせぬことを、君は恥辱とは思わないのか。
『ソクラテスの弁明・クリトン』プラトン著、久保勉訳 p43-44
ソクラテスは活動を通して、アテナイの政治的混乱状況からポリスとして本来あるべき秩序や機能を回復させることを目指していました。そして、そのために市民として正しい在り方について反省することを人々に求めたというわけです。
ソクラテス裁判
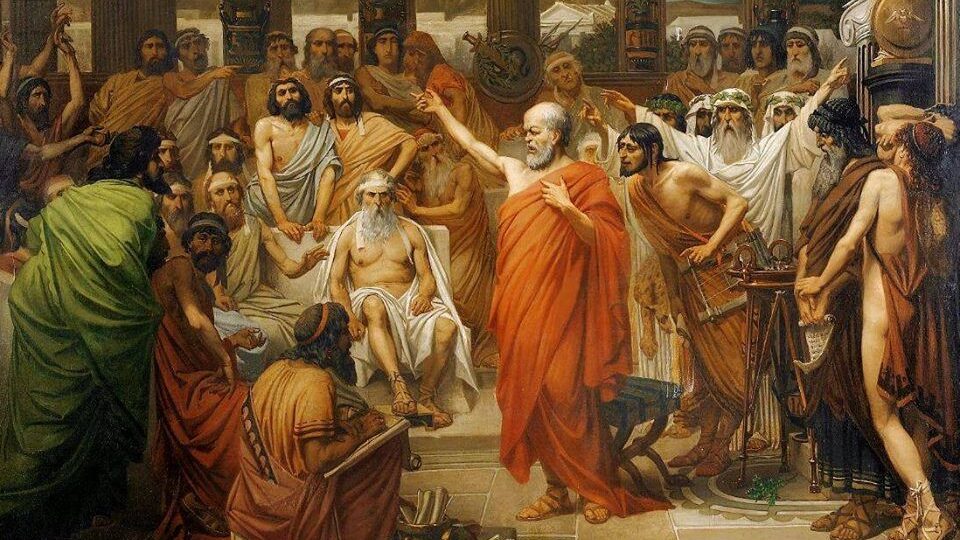
ソクラテスは自らについて「アテナイという名馬にまとわりつく虻」であったと述べています。
彼は活動を通して、公的生活、私的生活の場面でも、無知な思考や行為をしている人々、明らかに悪意のある思考や行為をしている人々を批判するようになっていたのです。
ソクラテスは長い間、国家や国家の卓越した市民への批判をすることを許されていました。
しかし、やがて政治的不安が広がってくると、国家の神を信じず、アテナイの青年を堕落させたとして罪に問われてしまいます。
このときの、裁判の様子(ソクラテス裁判)が描かれているのが、プラトン著『ソクラテスの弁明』です。
ソクラテスは告発に対し反論しますが、最終的に有罪とみなされ、死刑を宣告されてしまいました。
ソクラテスの友人たちは金銭を支払って他国に亡命することを勧めました。
しかし、ソクラテスは「悪法といえども法である」と述べ、拒否しました3。
そして最終的にソクラテスは、アテナイの市民としてアテナイの裁判の判決に従い、毒杯を飲み、死を選択しました。
真理のためには自らの命をも投げ出すソクラテスの生き方に、彼の弟子たちは衝撃を受けたことでしょう。
彼らはソクラテスの遺志を受け継いでいくことを決意します。その中には、若き日の哲学者プラトンの姿もありました。
プラトンは、ソクラテスが求めた「絶対的な理想」があると信じ、それを追究する哲学体系として「イデア論」を生み出していくのでした。
まとめ
ソクラテスの教育について書いてきました。まとめると以下の通りです。
- 相対主義的な思想が蔓延する古代ギリシアのアテナイで、普遍的な真理や徳を追究
- ソクラテス法とも呼ばれる対話法を用いた
- 「無知の知」を自覚するところから学びは始まる(知らないと知っているから、知りたいと思う)
- 活動を通して、アテナイ市民が「より善く生きる」ことを目指した

当時のギリシアの事情
- 相対主義の大流行
- もっともらしく話をするだけの煽動政治家
- 金銭、地位、名声などに流れる風潮
- 社会の中で巧みに生き抜く方便を伝授したソフィスト
今の社会と、ソクラテスが生きた時代はあまり変わらないと感じたなぁ。

そう思っちゃうよね…。
ソクラテスの時代から2000年以上経っているわけだけど、社会を渦巻く問題ってそんなに変わらないところもあるのかも。
そうすると、ソクラテスの生き方から学べることもまだまだあるのかもしれないね。
▼ ソクラテスを始め哲学入門書として超オススメ。
『史上最強の哲学入門』は聴く読書”Audible(オーディブル)の無料体験で聴き放題。この本以外にも、哲学関連の書籍が入門書〜古典的名著までが多数聴き放題です。
>>哲学ジャンルのAudible “聴き放題”対象本を見てみる
オーディブルは30日間無料で体験できます。オーディブルで、あなたの日常に刺激とインスピレーションを。
\『史上最強の哲学入門』も“聴き放題”/