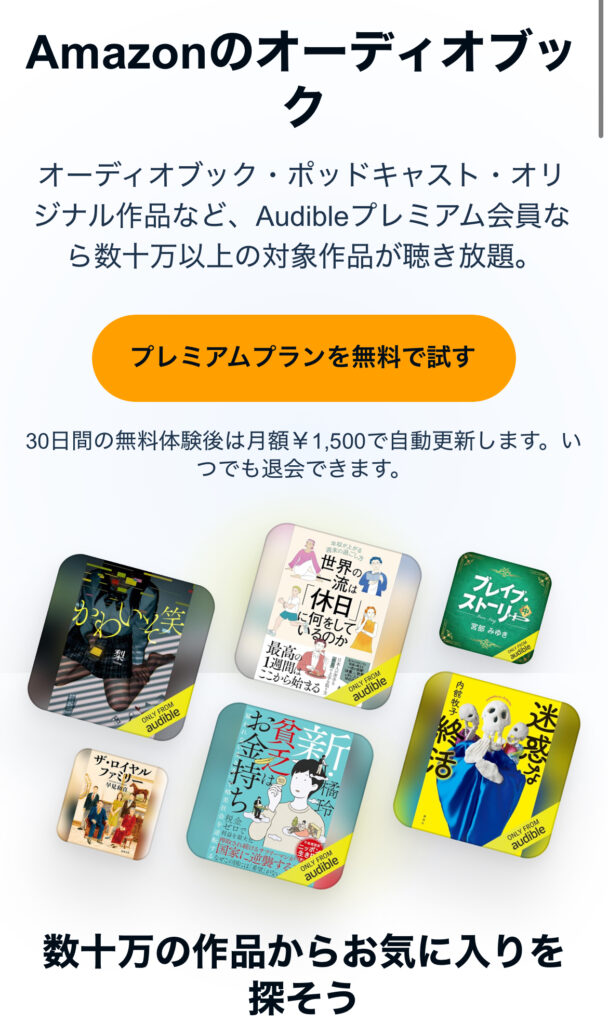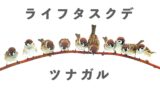「“課題の分離” をくわしく学びたい」
「“課題の分離” って冷たく感じる」
「“課題の分離” がうまくいかない」
そんなあなたへ、この記事を読めば「課題の分離」を専門家レベルで理解できます。
課題の分離をわかりやすく解説。冷たいのか?コツは?
「課題の分離」とは?
課題の分離は、問題が起きたときに「その問題の結果を最終的に引き受けるのは誰か」を考え、課題の当事者を見極める方法です。
例えば、「子どもが宿題をしない」という問題に、親は怒ったり、子どもの宿題を代わりにやってあげたりしがち。でも、そのやり方では課題は分離できていません。
「課題の分離」の考え方では、まず「宿題をしないのは誰の課題か?その結果を最終的に引き受けるのは誰か?」と問います。
宿題をしないことで成績が下がったり、先生に注意されたりするのは子ども自身。つまり、これは「子どもの課題」だと判断できます。だからこそ、親は過干渉を避け、基本的に子ども自身に問題の対処を任せるべきなのです。
アドラー心理学講座『SMILE』によると、親が子どもの課題に土足で踏み込み、甘やかしたり過保護になったりすると、以下のような弊害が生じます。
親が子どもの課題に口を出すと、次の4つの弊害が生じます。
『SMILE 愛と勇気づけの親子関係セミナー』テキスト p55
1)子どもが自分の力で問題を解決する能力を伸ばせなくなり、自信を失う。
2)子どもが依存的になって、責任を親に押し付けようとする。
3)子どもが感情的に傷つけられ反抗的になる。
4)親が忙しくなる。
アドラーは「甘やかされた人は評判が悪い。よかったことは一度もない1」といいます。アドラー心理学では甘やかし・過保護・過干渉は断固として反対します。「課題の分離」は、そうした状態に陥らないようにする重要な技法なのです。
「課題の分離」から「共同の課題へ」
さて、大事なのはここから。「課題の分離」には続きがあります。それは、「他者の課題」を「共同の課題」として部分的に引き受けるという考え方です。つまり、課題を分離したからといって、完全に本人任せにするのではなく、困っているなら助け合おうと考えます。
先ほどの例でいえば、宿題をするのは子どもの課題ですが、親は「困ったことがあれば相談に乗るよ」と伝えておきます。そして、子どもが実際に相談してきたら、親は「宿題をする」という課題を「共同の課題」として部分的に協力することができます。
ただし、協力するタイミングは相手から相談があったときのみで、必要最低限のサポートにとどめましょう。2
「課題の分離」→「共同の課題」の手順を示します。
①だれの課題かを考える(課題を分離する)
原則として、課題は誰か1人に帰属します。ただし、責任範囲や仕事の分担があいまいだと、誰の課題かわかりにくくなることがあります。
②共同の課題にするかどうか検討する
課題の当事者から相談や依頼があって初めて、共同の課題に向けて動き出します。ただし、必ずしも共同の課題にする必要はなく、個人の課題として独力で解決してもらうこともあります。
共同の課題には、次の3ステップがあります。
SMILE 愛と勇気づけの親子関係セミナー』テキスト p61
- 言葉に出して、相談・依頼する。
- 共同の課題にするか討議する。
- 共同の課題として取り上げれば、協力して解決策を探す。
子どもが宿題を前にしてメソメソしています。
『SMILE 愛と勇気づけの親子関係セミナー」テキスト p61~62
子:「今日中に宿題できそうにないの」(子どもの課題)
親:「そう。困っているのね」(まだ、共同の課題として取り上げない)
子:「だからお母さん手伝ってほしいの」(共同の課題にしてほしいという依頼)
親:「でも、宿題はあなたが自分でするものだと思うのよ。お母さんが手伝わなくとも自分でできると思うわ」(共同の課題にすることをことわる)
子:「お母さん待って。じゃ、わからないところだけ教えてもらえない?今日のところは難しいの」(共同の課題にしてほしいという依頼)
親:「そうね、あなたがよほど困っているなら手伝ってもいいかな」(共同の課題としてひきうける)
③共同の課題として引き受けたら、責任を持って取り組む
あくまでも本人が中心で、サポートは必要最低限にとどめます。「相手は自分の力で解決する力がある!」と信じましょう。
以上、「課題の分離」→「共同の課題」の手順について説明しました。
一連のプロセスは、対等のパートナーとして共に取り組むことが重要です。上下関係ではなく、横の関係で協力的に進めていくことが求められます。
アドラー心理学の目的は、よりよい共同・協力関係を築くことです。課題の分離は、そのための第一歩であり、最終目標ではありません。バランスを取りつつ、必要に応じて共同の課題として助け合っていくことが大切なのです。
「課題の分離」は冷たいのか?—「課題の分離」のよくある誤解
最後に「課題の分離」によくある誤解を解いておきます。
課題の分離は「相手の課題には一切干渉せず、自分の課題だけ考えて生きていけばいい」という冷たい考え方に思われがち。でもそれは完全に誤解です。
確かに『嫌われる勇気』には、「他者の課題には介入せず、自分の課題には誰ひとりとして介入させない3」とかなり印象的に書かれています。その後、「課題の分離は、対人関係の最終目標ではありません。むしろ入り口なのです4」とも一応書かれてはいますが…
『嫌われる勇気』を読んで、
「今まで自分は他人の課題に振り回されていたんだ!!嫌われる勇気を持って、他人を切り捨て、自分の課題に集中して生きていこう!!」
と思う人がいるかもしれません。そう考えることで、しがらみから解放され、本当の自分を生きられるようになったと感じる人もいるでしょう。
しかし、アドラー心理学の本来の目的は、他者とよりよい協働・協力関係を築くことです。課題の分離は、そのための入り口に過ぎません。個人と個人がほどよい距離感を保つのはいいですが、バラバラになってはいけません。
「課題の分離」は、個人の個性を尊重しつつ、助け合いの関係を目指す技法なのです。決して、個人主義的に生きることを推奨するものではないことを理解しておいてください。
▼関連記事
まとめ
「課題の分離」は、だれの課題かを見極め、過干渉を避けることで、良好な人間関係を築くための第1歩です。ただし、それで終わりではなく「共同の課題」として助け合うことも大切だと、アドラー心理学は教えてくれます。
なお、「課題の分離」が使えるのは、自己決定の余地があり、相談的・共同的な関係が築ける場合に限ります。立場的に弱く、強制的に支援を求められたり、過干渉を受けたりしている状況では、「課題の分離」をしたくてもできないことがあるでしょう。
(いつも親からガミガミ言われる子どもや、上司から常に監視される部下を思い浮かべてください。弱い側の立場からは「課題の分離」を提案するのは困難だとおわかりいただけると思います)
では、過干渉に悩まされている場合、アドラーならどうアドバイスするでしょうか?
おそらくアドラーは相手が恐ろしい上司や嫌いな親であっても、「勇気を出して関係の見直しを提案しなさい」とアドバイスするでしょう。これは心理学的テクニックというよりは、よりよい協働・協力の関係(=共同体感覚)に向かって一歩踏み出すことを促す、道徳的な励ましと言えます。
そこまでして他者と関係を築く必要があるのか?と疑問に思う人もいるかもしれません。しかし、アドラーの思想はどこまでも理想的です。よりよい関係性に向けて前進するためにベストを尽くすよう、提案し続けます。
「課題の分離」も、アドラー心理学の本質である共同体感覚、つまり協力し合える関係を築くことに役立つ形で使わなければなりません。人と人をバラバラにするような使い方は、本来の目的から外れてしまうことを、ぜひ知っておいてください。
【課題の分離をより深く学ぶためのおすすめ本】
①嫌われる勇気
『嫌われる勇気』には、言い過ぎている部分や、「共同の課題」について触れていないという問題点はあります。しかし、それでも「他人の課題を引き受けすぎて困っている」という悩みを持つ人に対し、「あなたは、あなた自身の人生を生きる権利がある」と力強いメッセージを送ってくれる名著です。
②もしアドラーが上司だったら
この本は、仕事が上手くいかずに部下のリョウくんが、上司のドラさんのサポートで成長していく物語を通して、アドラー心理学を日常生活に活かす方法を分かりやすく伝えています。第八章では「課題の分離」についても、わかりやすく説かれており、おすすめです。
『もしアドラーが上司だったら』ほか、アドラー心理学の名著が “聴く読書” Audible(オーディブル)の無料体験でも視聴可能です。
オーディブルは30日間無料で体験できます。オーディブルで、あなたの日常に刺激とインスピレーションを。