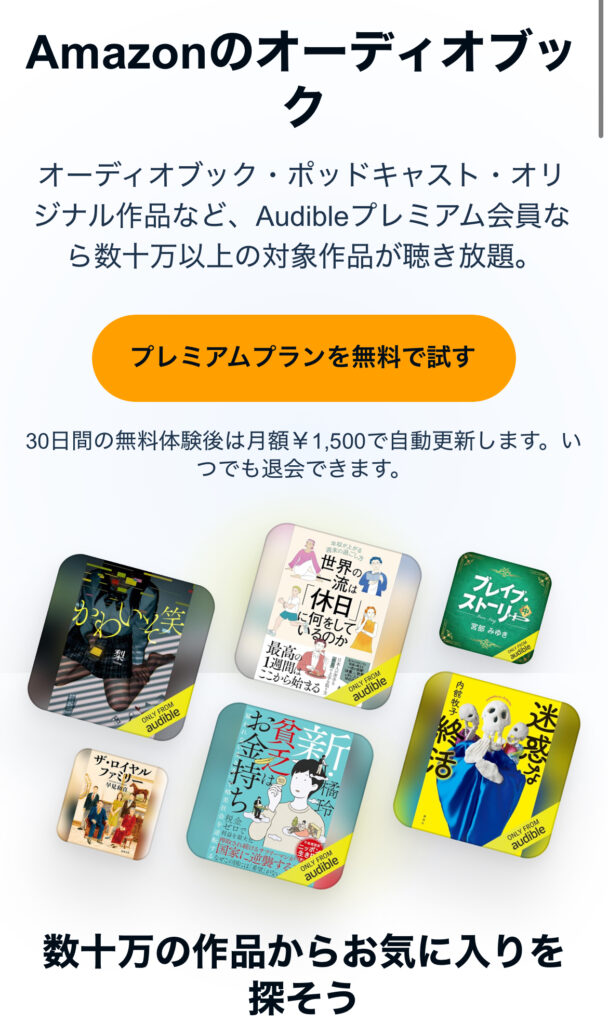アドラー思想の根幹にある「ライフタスク」について、アドラーの原著から紐解きます。
【アドラー心理学】3つの「ライフタスク」から考える人と人のつながり
交友、仕事、愛の3つのライフタスク
アルフレッド・アドラーは、人生において誰もが直面する3つの課題を「ライフタスク」と呼びました。
- 交友(共生)のタスク
人は1人で生きているわけではなく、他者とどのように共生するか - 仕事のタスク
地球という有限な環境で、どのように仕事を見つけ、分業するか - 愛のタスク
恋愛、結婚、出産、子育てなどを通じて、人類の存続にいかに貢献するか
なお、現代アドラー心理学では、これらに「自己(セルフ)」と「スピリチュアル」のタスクを加えた5つのライフタスクが提唱されています。
さて、3つのタスクをアドラーはどのように説明しているのでしょうか?アドラーの原著から紐解きましょう。
交友のタスク
交友のタスクについて、私たちは1人で生きているのではなく、「常に他者を考慮に入れ、他者に自分を適応させ、自分を他者に関心を持つようにしなければならない1」とアドラーはいいます。
つまり、交友のタスクとは、単なる友情関係にとどまらず、他者とどのようにともに生きていくかという基本的なテーマに取り組むことを意味します。
このことから交友のタスクは「共同体生活2」のタスクとも呼ばれ、次に説明する仕事・愛のタスクの基礎になるとされるのです。
仕事のタスク
仕事のタスクとは、地球や宇宙における資源や気候などの条件が、「われわれに提示する問題への正しい答えを見出すこと3」であるとアドラーはいいます。
人間は、さまざまな条件のもと社会を成り立たせ、生活していかねばなりません。そのためには、他者との役割分担(労働の分業)が必要です。つまり仕事のタスクとは、社会を成り立たせるための他者との協働作業に、いかに参加・貢献するかという課題なのです。
愛のタスク
愛のタスクとは、「身体的に引きつけられること、交際、子どもを生む決心において表される異性のパートナーへのもっとも親密な献身4」であると定義されます。
そして、「その協力は二人の幸福のための協力であるだけでなく、人類の幸福のための協力でもある5」とアドラーはいいます。これは彼が、人類の存続のために子孫を残すことの必要性から、愛のタスクについて言及しているからです。
当然、子どもを産めない人や、性的マイノリティーなどのケースはあるでしょう。しかしながら、自分が子どもを作るかどうかは別としても、人類の未来のためには誰かが子孫を残さねばならないのもまた事実。こうした事実や課題にいかに向き合うかを、アドラーは愛のタスクと呼びました。
3つの絆→3つのタスク
人がライフタスクに取り組むのは、人がつながり(絆)の中で生きているからだとアドラーは考えました。
すべての人は、三つの主要な絆の中に生きている。これを考慮しないわけにはいかない。それが人の現実を構成する。なぜなら、人が直面するすべての問題や問いは、そこから生じるからである。これらの問いに答え処理することが常に強いられる。
『人生の意味の心理学(上)』A・アドラー著 岸見一郎訳 p.10
3つの絆とは、
- 地球という厳しくも限られた環境で生きていること
- 人間は弱さゆえ他者と結びついて生きること
- 人間がやがては将来へ命をつなげる生物であること
これらは人間が生きていく限り逃れられない結びつきであり、3つの絆は順に(1)仕事のタスク、(2)交友のタスク、(3)愛のタスクの根拠とされます。
| 3つの絆 | 3つのライフタスク |
| 地球という厳しくも限られた環境で生きていること | 仕事のタスク |
| 人間は弱さゆえ他者と結びついて生きること | 交友のタスク |
| 人間がやがては将来へ命をつなげる生物であること | 愛のタスク |
人間は身体的に弱い生き物。厳しい地球環境で生き抜くには、仲間と助け合わねばなりません。そのことをアドラーは「3つの絆」と「3つのライフタスク」から物語ったのです。
ライフタスクから考える「共同体感覚」の意味
最後に「ライフタスク」から、アドラー思想の根幹にある「共同体感覚」について考えます。まず「共同体感覚」のドイツ語(原語)とその英訳から、共同体感覚には以下の2つのニュアンスがあるとわかります。
- ドイツ語:”Mitmenschlichkeit” →「人と人とが共にあること」というニュアンス
- 英語:”social interest”→「他者への関心」というニュアンス
これらに加えて、アドラーは「ライフタスク(人生の課題)」について、こんなことを言います。
個人が人生の課題と深く結びついていることを示している。即ち、個人の全体は人生―おそらく共同といった方がいいだろう――の連関から引きずり出されることはできないということである。
『生きる意味を求めて』A・アドラー著 岸見一郎訳 p.32
アドラーはこの一節で、個人は他者とライフタスクで深くつながっていて、人生とは(他者との)共同であるといいます。
他にもアドラーは個人を「生活領域の問題(ライフタスク)と緊密に結びついた「分割できない」全体として生きる存在6」として捉えていることがわかります。
つまり、共同体感覚の根拠にアドラーはライフタスクという物語を用いたのです。
「共同体感覚」とは、ライフタスクを通じた人と人とのつながり(Mitmenschlichkeit)を感じ、つながっている他者へ関心(social interest)をもっていることだと整理できます。
まとめ - 人はつながりながら生きていた。では今は?
アドラー思想の土台には、「人は1人では生きられない」「他者とつながりあって生きている」という熱いメッセージがあり、その根拠になるのが「ライフタスク」です。
さて、みなさんはアドラーのメッセージにどれくらい共感できるでしょうか?「他者とのつながり」とか、正直面倒臭い!と感じる人も少なくないでしょう。
いや、他者と生きていくって、実際面倒臭いことなんです。けれども「面倒臭い」とは言ってられなかった。
- 村で農業をして暮らす
- 商店街で家族経営のお店を営む
- 会社でサラリーマンとして生きていく
これまでは、生きていくために他者とつながることがほぼ必須であり、「生きていく=他者とつながること」という構図があったからです。
でも、今はどうでしょうか?
「買い物は amazon ですべて完結。結婚も子どももいらない。だって、人とつながるのって面倒臭いから。だし、そっちの方がだれにも迷惑かけないでしょ?1人で生きていくのが気楽で一番!もしくは数人の気の合う仲間と、面倒くさくない範囲で関わればいい」
究極、こんな生き方だって十分可能なわけですよね。
アドラーが「ライフタスク」や「共同体感覚」を唱えたのは、1900年代前半のこと。当時はインターネットもありませんでした。あれから時代は大きく変わりました。
他者とのつながりを前提とした、ライフタスクや共同体感覚。その現代的な意味とは?
アドラー思想をそのまま現代に当てはめると、「暑苦しい!今はそんな時代じゃない!」と言われてしまう日が来ているのかもしれません。
【参考文献】
『人生の意味の心理学』A・アドラー著 岸見一郎訳/アルテ
『生きる意味を求めて』A・アドラー著 岸見一郎訳/アルテ