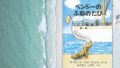「メモをとってもよろしいでしょうか。あなたの一言一言を聞き逃さないことが私にとって重要なことなのです」
マリーナ・ブルフシュタイン博士は、デモンストレーションの冒頭からクライアントへの敬意を丁寧に示していく。
クライアントが提案に同意すると、「ルールをきちんと守ることを大事にされているんですね」と、些細なことにも肯定的に意味づけていく。
最初は緊張気味だったクライアントの表情が、あっという間に和らぎ、安心感に満たされていくのが見て取れた。
アドラー心理学のライフスタイル分析を学び始めて数ヶ月、私は1つの疑問と向き合っていた。相手のライフスタイルが読めるようになると、むしろ課題の方が鮮明に見えてくる。
強みよりも「ここを直せばもっと良くなるのに」という改善点が目につきやすい。
- 本当の成長には自己否定や課題への直面が必要なのではないか?
- でも、それを直接伝えれば相手を傷つける可能性がある…
この葛藤を胸に、マリーナ・ブルフシュテイン博士(国際個人心理学会会長、アドラーユニバーシティ教授)による『ライフスタイル・アドバンス編』の3日間のデモンストレーションに参加した私を待っていたのは、想像をはるかに超えるポジティブアプローチだった。
マリーナ博士のセッションで特に印象に残ったのは、クライアントの長い人生の物語を聴いた後、だれも気づいていなかった本質を言い当てる場面。
「あなたは公平性を大切にされているのですね。それはあなたの強みでもあると感じます」
それまでバラバラに語られていたエピソードが1本の糸でつながったかのように意味を持ち始める。
表面的な言葉だけでなく、小さな行動の奥に隠れた価値観を見抜き、それを肯定的に言語化する——マリーナ博士の洞察力に、思わず息をのむ。
講座では、クライアントの強みを引き出すためのグループワークも行われた。
私たちは「もしかしたら…」で始まる文で、クライアントの可能性を提案していく。このプロセスについて、マリーナ博士は興味深い観察を共有した。
「カウンセラーがクライアントに提案する変化の方向性は、実はカウンセラー自身のライフスタイルを映し出す鏡です。クライアント自身が望む変化と、カウンセラーである私たちが望む変化には、往々にして違いがあります。その違いに気づくことが大切です」
つまり、私たちカウンセラーが「こう変わるべき」「こうかもしれない」と思う方向性は、実は自分自身の価値観や信念の投影である。
そのときに、クライアントが本当に望む変化と、カウンセラーが望む変化の方向性が異なれば、そこに無用な軋轢が生まれる。
この言葉に、私は立ち止まった。
もちろん、カウンセラーは自分自身のライフスタイルから完全に自由になることはない。
けれども、自分のライフスタイルをあまりに無自覚的にクライアントに押し付けてはいないだろうか?
それはときに、カウンセリングにおける「権力闘争」を生み出す原因にさえなりえるのだ。
懇親会で、私はマリーナ博士に質問する機会を得た。
「クライアントのライフスタイルのネガティブな側面に気づいたとき、どう処理し、伝えるべきですか?」
マリーナ博士の答えは、シンプルながら新鮮な視点を提供してくれた。
「ネガティブに目を向けることは容易ですが、それだけでは変化は生まれません。ネガティブな側面は、強みの過剰投与(overdose)として捉えるといいでしょう」
「過剰投与された強みを、ほんの少し緩めるイメージで考える。そんなに大きく変化する必要はありません。それはセラピスト側のメンタルにとってもよいことです」
「いまこの瞬間のクライアントではなく、あたかも明日の未来のクライアントであるかのように相手を見て、そして語りかけてみてください」
「強みの過剰投与」——この言葉は単なるリフレーミングを超える深い意味を持っていた。
ネガティブな特性を単に別の言葉で言い換えるのではなく、その根底にある価値や能力を認識し、その「度合い」だけを調整するという考え方。ここには人間の本質を肯定的に捉える姿勢が貫かれている。
完璧主義は「高い基準」という強みの過剰投与。
心配性は「先見性」の過剰投与。
頑固さは「一貫性」の過剰投与。
過度な親切は「思いやり」の過剰投与。
この視点に立てば、アプローチも自ずと変わる。ネガティブな側面を直接指摘するのではなく、その根底にある強みを最大限に認め、「少し緩めてみては?」と提案するだけでいい。それは否定ではなく、調整の提案なのだ。
マリーナ博士の通訳を担当された水野美津子さんは、「マリーナ直伝のアドラー心理学では、基本理論に “楽観主義” を加えたいくらいだ」とおっしゃっていた。
自分自身を振ってみる。
日本で教育を受ける中で、また自身の成長過程で、「批判的に自己を見つめることが成長につながる」という考え方をあまりに内面化しすぎてきたのではないか?
「痛みを伴わない成長はない」という思い込みが、カウンセリングの姿勢にも影響していたのかもしれない。
そして、自分の最近の実践も省みた。
ライフスタイル分析が少しばかりできるようになり、読み取ったことをすべて伝えたくなる気持ちが強くなっていたのではないだろうか?
「分析力」は自分の強みかもしれない。けれどもそれが過剰投与(overdose)になってしまうと、相手の成長を願う熱意が、皮肉にも相手を圧倒し、変化を妨げてしまう可能性へとつながりかねない。
アドラー自身も「人間を理解するのは容易ではない。われわれは、他の人の眼で見て、他の人の耳で聞くことができなければならない」と述べる。
カウンセラー自身のライフスタイルを押し付けるのではなく、クライアントの視点から世界を見ることの重要性を説いているのだ。
ときには、ネガティブな側面を指摘することが必要な場面もあるかもしれない。改善点をズバリ伝えれば、短時間で大きな変化につながることもあるだろう。
しかし、その前に問うべきは——本当に私たちは、ポジティブなアプローチの可能性を徹底的に探求したのだろうか?少なくとも私自身は、その可能性をまだ十分に試していない。
安易に答えを出す前に、まずポジティブなアプローチの可能性をもっともっと追求してみたいと思う。相手の強みを丁寧に言語化し、過剰投与された強みを「少し緩める」という繊細なアプローチを自らの実践で試してみたい。
マリーナ博士のデモンストレーションから、私は技法だけでなく、クライアントと向き合う姿勢そのものを学んだ。
ヒューマンギルドの岩井俊憲先生はブログ記事でマリーナ博士のことを「ウォーキング・エンカレッジャー」(勇気づけて生きる人)と表現されていたが、まさにそのとおりだと私も思う。
マリーナとの出会いで私は、単なる心理技法を超えた人としてのあり方の学んだのである。