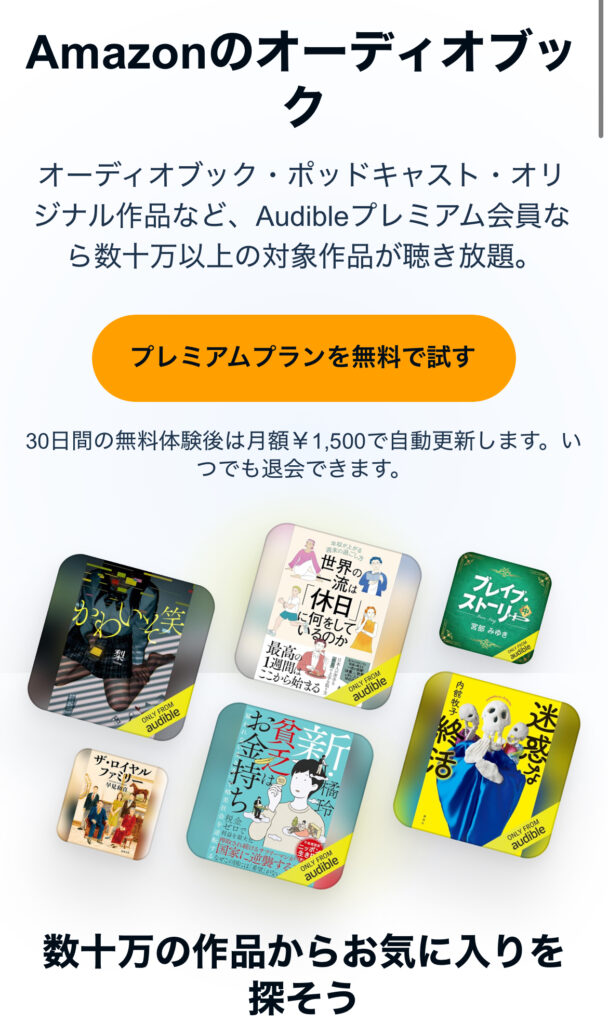カウンセリング道場で出会った「状況・相手役・目的」という3点セット。この人間行動を紐解くフレームワークは、シンプルながらも深い洞察をもたらしてくれる。
前回の記事では、この3点セットの「状況」に焦点を当て、クライアントが各状況にどのような意味を与えているかを理解することが、その人のライフスタイルを読み解く鍵となることを探った。
今回は「目的」という要素に光を当て、「行動の背後にある目的には、どのようなパターンがあるのか?」という問いに取り組みたい。
アドラー心理学の文献を紐解くと、人間行動の目的にはいくつかの基本的なパターンが浮かび上がってくる。
ここでは主な4つのパターンを紹介するが、あらかじめ断っておきたい点がある。
これらのパターンは人間行動のすべてを網羅しているわけではなく、また必ずしも互いに独立した概念とも言い切れない。
例えば「力と制御の獲得」は「優越性の獲得」の一形態と見ることも可能だろう。
しかし理解のしやすさを優先して、今回はこれらを並列的に扱っていくことにする。
「なぜ」ではなく「何のために」——「状況・相手役・目的」3点セットが明かす人間行動の本音
① 所属と重要性の獲得—「ここに居場所がある」という感覚
人間の根っこにある欲求の1つは、「どこかに所属したい」「誰かに大切にされたい」という思いだ。アドラー心理学では、これをとても重視している。
Adler Graduate Schoolの資料によれば、「アドラーは私たち全ての基本的な欲求と目標は、所属することと重要だと感じることだと信じていた1」と記されている。
日常のどんな場面で見られるだろうか?例えば—
- 会議で積極的に発言する(「この場で私は価値ある一員だ」と感じたい)
- SNSで「いいね」を求める(「私の存在が認められている」という確認)
- 流行を取り入れる(「この集団に属している」という安心感)
一見、異なる行動に見えても、その奥には「認められたい」「所属したい」という同じ願いが潜んでいることがよくある。
② 優越性の獲得—「より良くなりたい」という上昇志向
アドラーの人間観の中心にあるのが「優越性追求(striving for superiority)」という概念だ。これは単なる競争心ではなく、人間に内在する「より良くなりたい」という根源的な欲求を指している。
われわれは、すべての人間の中に、人の人生を通じて流れているこの主要なテーマ ー 劣等の位置から優越した位置へ、敗北から勝利へ、下から上へと上昇する闘いを常に見出すだろう。それは、われわれのもっとも早い子ども時代から始まり、われわれの人生の最後まで続く。
『人生の意味の心理学(上)』A・アドラー著 岸見一郎訳 p61
この「優越性の獲得」という目的は、様々な表れ方をする。
建設的なものとしては自己啓発や技術向上への努力、一方で破壊的な形では他者批判や過度な競争心として現れることもある。
同じ根っこから生える枝でも、伸びる方向によって実り方が変わるのだ。
③ 回避—「傷つきたくない」という自己防衛
人間行動の多くは、何かを得るためではなく、何かを避けるために行われている。失敗、批判、拒絶、恥といった不快な経験からの逃避だ。
Verywell Mindによれば、アドラー派のセラピストは、クライアントの不適応行動を「勇気の欠如」や「回避行動」として捉えることが多い。これらは恐れる結果(失敗、拒絶など)を避けるための戦略だと考えるのだ2。
一見消極的に思える回避だが、心理的安全を守るという点では積極的な自己防衛でもある。日常では、こんな形で現れる:
- 人前での発言を控える(批判を避けるため)
- 決断を先延ばしにする(間違える不安から)
- 親密な関係を避ける(傷つくリスクを減らすため)
④ 力と制御の獲得—「自分でコントロールしたい」という欲求
不確実な世界で、少しでも予測可能性を高めたい—この願いも人間の根源的な目的の1つだ。
Counseling Theories のサイトによれば、特に子どもの不適切行動の文脈でよく観察されるという3。
アドラー心理学を基にしたペアレントトレーニングプログラム『STEP』のテキストには、子どもの行動目標と本音が整理されている:
| 子どもの行動 | 目標 | 子どもの本音 |
| 怠惰、ムダ口、ぐずり、落ち着きのなさ、邪魔など | 関心引き | 私に注目して 私と関わりをもって |
| 頑固、不服従、反抗、非協力など | 主導権争い | 私にやらせて、選択させて あなたに支配されたくない |
| さらに強い反抗、攻撃、傷つく(身体、言葉)など | 仕返し・復讐 | 私は傷つけられた 私を助けて |
| 無反応、すぐに諦める、消極的、孤立 | 無気力な態度を示す | 独りにして、何もできない私を諦めないで |
この表は非常に示唆に富む。
子どものぐずりや注目を引く行動の裏には「私に関わって」という願いが、頑固さや反抗の背後には「私に選択させて」という自律への欲求が、そして攻撃性には「傷ついた私を助けて」という痛みがある。
表面的な行動だけでなく、その奥にある「本音」を理解することで、対応も変わってくるのだ。
興味深いのは、この表が「子どもの行動」として紹介されているものの、実は大人の行動にも驚くほど当てはまる点だ。
特にアダルトチルドレンのような、幼少期に健全な対人関係のモデルを得られなかった人々の行動パターンを理解する際に役立つことが多い。
例えば、職場で過度に注目を集めようとする行動、会議で頑なに自分の意見に固執する態度、批判に対して過剰に攻撃的になる反応—これらも同じ目的の表れかもしれないのだ。
こうした視点は、対人関係で「困った人」と感じるケースへの理解を深めるのに役立つ。
彼らの行動を単に「困った性格」と片付けるのではなく、その背後にある「関わってほしい」「自律性を守りたい」「傷ついている」といった本音を理解することで、より建設的な対応が可能になるのだ。
このように、子どもであれ大人であれ、「力と制御の獲得」という目的は人間行動の重要な動機となる。
それは時にリーダーシップや自己決定として建設的に表れることもあれば、支配欲や過度な操作として有害な形を取ることもある。
しかし、その根底には常に「無力感を避けたい」「予測可能性を高めたい」という、不確かな世界を生きる人間の基本的な願望があるのだ。
まとめ:目的を理解する意味—行動の奥に人間を見る
これらの基本パターンを知ることで、「問題行動」とされるものも、新たな視点で見えてくる。
例えば子どもの反抗も、単なる「困った行動」ではなく、「自律性を求める健全な欲求が不適切な方法で表現されている」と理解できる。
カウンセリングでは「なぜ」ではなく「何のために」を問うことで、表面的な行動ではなく、その人が本当に求めているものに近づける。
そして、より建設的な形でその目的を達成する方法を共に探ることが、本質的な支援になるのだ。
前回の「状況」とあわせて考えると、「状況・相手役・目的」の3点セットは、人間行動を深く理解するための鍵となる。これからのカウンセリングにおいて、これらの視点をより意識的に活用してみたい。