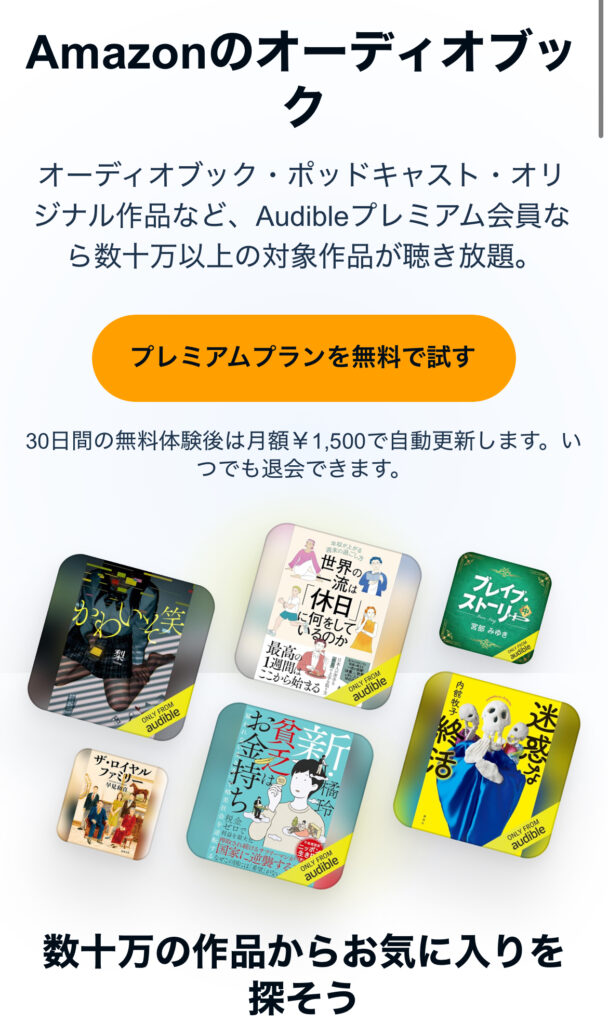先日、カウンセリング技術を磨くための講座「カウンセリング道場」に参加した。
これは十数名の参加者の前でリレー形式のカウンセリングを行い、その様子を観察した参加者や講師からフィードバックをもらうという実践的な場である。
前回の道場では自分がカウンセラー役を務め、多角的な視点からのフィードバックを通じて数多くの気づきを得た。
その中で特に印象に残ったのは、講師の岩井先生が強調していた「状況・相手役・目的」という行動理解のための “3点セット” フレームワークだ。
例えば「Aさんの、Bという行動に悩んでいる」という主訴に対して、3点セットを用いれば次のように掘り下げることができる:
- 状況:どのような場面・環境で Aさんは Bという行動をとるのか?
- 相手役:Aさんは誰に対してその行動をとるのか?その人とAさんの関係性はどうなっているのか?
- 目的:Bという行動によって何を達成しようとしているのか?行動の背後にある無意識の目的は何か?
この枠組みがカウンセリングの本質を捉えていることは直感的に理解できたものの、実際に活用するには理論的背景をより深く理解する必要があると感じた。
特に、次の2つの疑問が浮かび上がってきた:
- 疑問1 なぜ「状況」が重要視されるのか?
- 疑問2 行動の「目的」には、具体的にどのようなパターンがあるのか?
この記事では、1つ目の疑問『なぜ「状況」が重要視されるのか?』という問いから考えたことをまとめてみたい。
「状況・相手役・目的」行動理解のための“3点セット”フレームワークが、ライフスタイルの扉をひらく
対人関係論→「相手役」 目的論→「目的」 では「状況」は?
アドラー心理学の基本には「目的論」と「対人関係論」という2つの重要な考え方がある。
「目的論」は、人の行動には必ず何らかの目的があるという考え方だ。「なぜそうなったか」という原因にフォーカスするのではなく、「何のためにそうするのか」という目的に焦点を当てる。
もう1つの「対人関係論」は、「人間の悩みはすべて対人関係の悩みである」というアドラーの考えに基づいている。
つまり、人の行動は他者との関係の中で理解する必要があるということだ。
この2つの考え方から、「3点セット」の中の「目的」と「相手役」の重要性は簡単に理解できる。
行動には目的があり(目的論)、その行動は誰かとの関係の中で起きる(対人関係論)からだ。
しかし、「状況」については「目的」「相手役」ほどすんなりと理解できそうにない。
なぜ、「目的」「相手役」と並列して「状況」を掴むことも大切なのだろうか?
なぜ「状況」が重要視されるのか?
この問いの答えの1つは、カウンセラーが思い込みを捨て、クライアントの主訴をよりありありと理解するために「どんな状況で?」という問いが有効であるというものだろう。
具体的な状況を聴くことで、抽象的な悩みが鮮明な映像として浮かび上がり、カウンセラーとクライアントの間に共通の理解基盤が生まれるし、その中で見落としていた大事な視点が見えてくることもあるかもしれない。
しかし、「状況」の重要性はそれだけなのだろうか?
ここで、1つの思考実験をしてみたい。
同じ「相手役」に対して、同じ「目的」を持っていても、「状況」が変われば行動は変わるだろうか?
答えは明らかに「変わる」だろう。
たとえば、母親に愛されたいという同じ目的を持つ子どもでも、家族だけの食事の時と親戚が集まる場では異なる行動をとるかもしれない。
同様に、友人に理解されたいという目的でも、2人きりの時と集団の中では表現方法が変わる。
では、なぜこのような違いが生じるのだろうか?
この現象を理解する鍵は、アドラー心理学の認知論的アプローチにある。
アドラー心理学では、人は単に物理的環境をそのまま経験するのではなく、常に自分自身の主観的な意味づけを通して世界を認識することを重視する。
「客観的」という言葉を使うことがあるが、そもそも純粋な客観など存在するはずもなく、すべては私たちの解釈を通してのみ経験されるのだ。
アドラーは「意味は状況によって決定されるのではなく、私たちが状況に与える意味によって自分自身を決定する1」と述べている。
つまり、「状況」とは単なる物理的環境ではなく、個人が特定の意味を付与した心理的空間にほかならない。
家族だけの食事は「安全な場」かもしれないが、親戚が集まる場は「評価される場」と意味づけられるかもしれない。この意味づけの違いが、同じ目的・同じ相手でも異なる行動を生み出すのである。
さらに興味深いのは、「状況」の変化にともない「相手役」も微妙に変化するという点だ。
表面的には同じ相手(例えば母親)に対する行動でも、その場に他者(親戚)が加わることで、実質的な「相手役」は「母親」から「親戚も含めた観衆の前での母親との関係」へと変わる。
子どもが母親に甘える行動は、家族だけの時には「愛情表現」だが、親戚の前では「恥ずかしい行為」と意味づけられるかもしれない。
このように、同じ行動でも、状況の変化(他者の存在)によって、その行動の社会的意味が変わり、それに伴って行動パターンも変化するのである。
「状況」について掘り下げると、ライフスタイルが見えてくる?
ここまで書いてきて「状況」について深く掘り下げることは、結局はクライアントの「ライフスタイル」を理解するのに有効なのだなと思った。
同じ職場の会議でも、ある人にとっては「自分の能力を示す舞台」であり、別の人には「批判を受ける危険な場」かもしれない。
この違いは各人が持つ基本的な世界像や信念、つまりはライフスタイルの違いからくる。
「職場のミーティングでは発言できない」というクライアントに対して、3点セットを用いると:
- どのような状況を「発言できない場」と感じるのか(大人数の場合のみ?権威ある人がいる時だけ?)
- どのような相手役に対して萎縮するのか(表面的には上司だが、実際には「同僚の目があるから」かもしれない)
- その沈黙にはどんな目的があるのか(批判を避けたい?無能だと思われたくない?)
特に「状況」の捉え方に注目すると、「この人は世界をどう見ているのか」という深層が少しずつ見えてくる。
カウンセリングで「あなたはその状況をどう感じましたか?」と問うとき、クライアントの深層にある「ライフスタイル」への手がかりを探ることになるのだろう。
まとめ
カウンセリング道場での学びを通じて、「状況・相手役・目的」という3点セットが単なる情報収集の枠組みではないことに気づいた。これは、目に見える行動の奥にある、クライアントの内的な風景を探る地図なのだ。
特に「状況」への問いかけは、物理的環境の確認ではなく、クライアントが世界をどのような色で、どのような形で見ているのかを知る窓となる。
同じ場面でも人によって全く異なる意味を持つことを理解すれば、表面的な「問題解決」を超えた、その人の「あり方」に寄り添うカウンセリングが可能になるのではないだろうか。
これからのカウンセリングでは、この3点セットを意識的に活用し、クライアントのライフスタイルを理解するための入り口として大切にしていきたい。