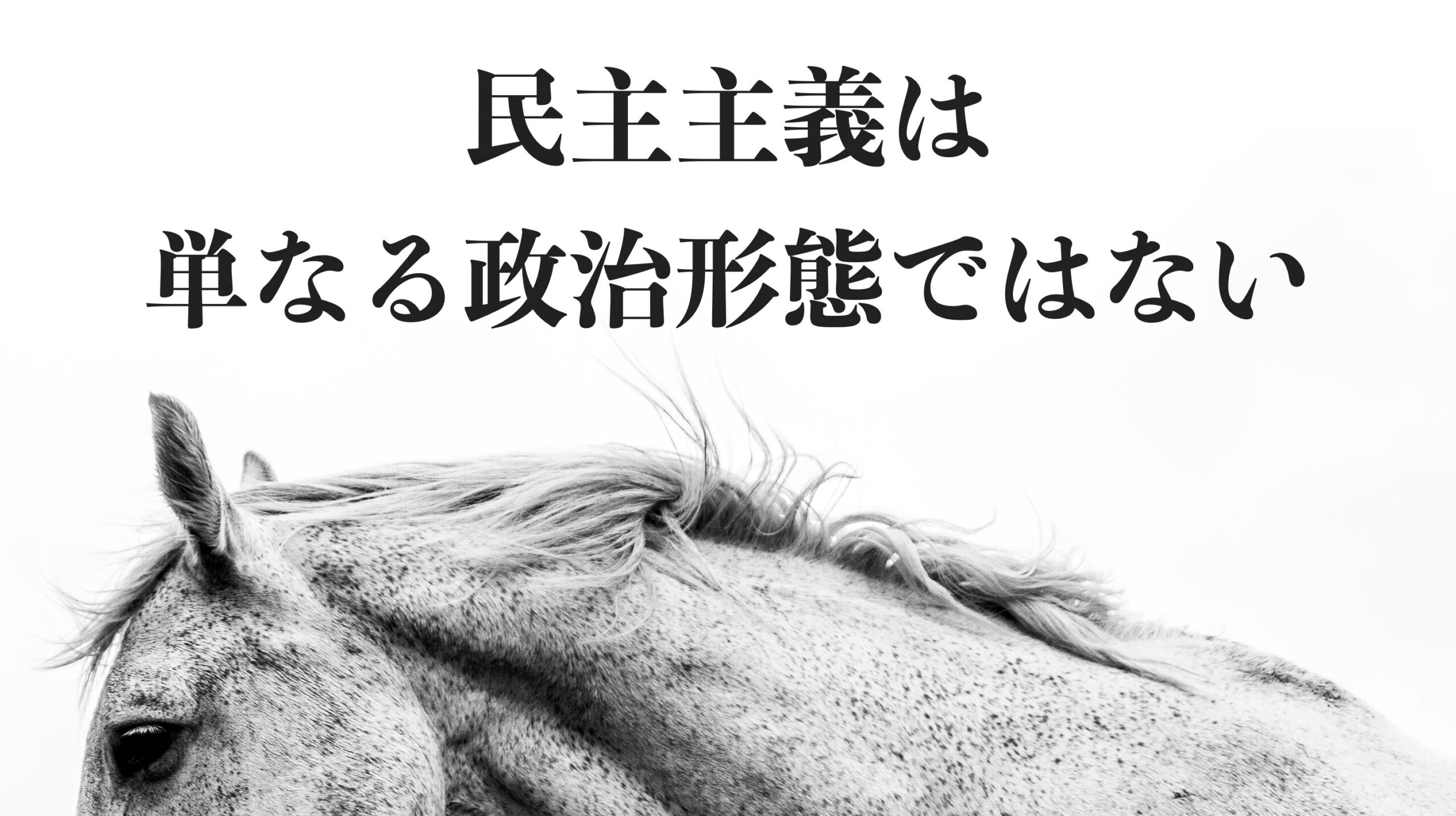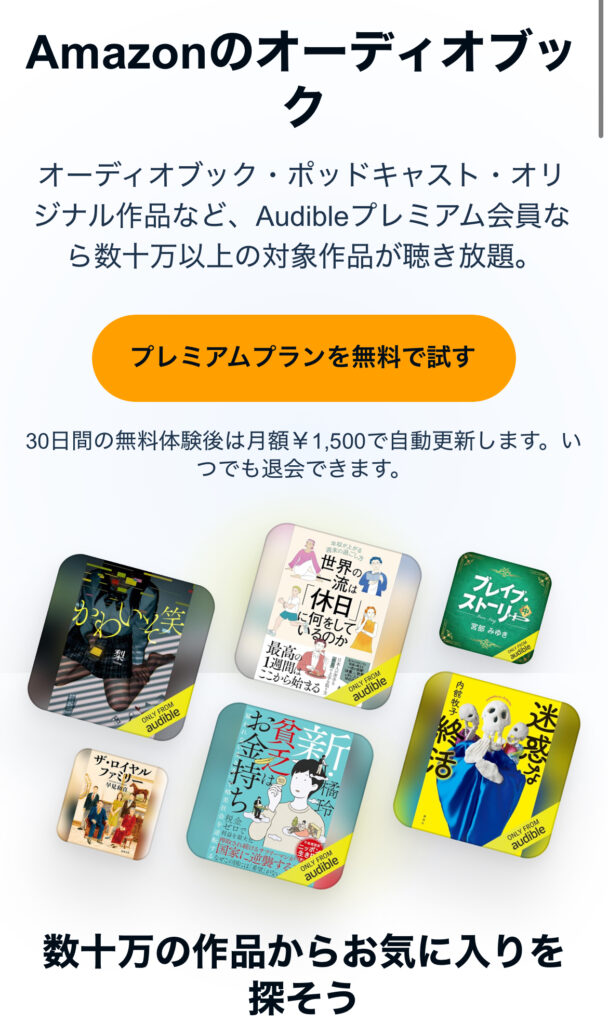『民主主義と教育』がわからない
デューイの民主主義論に関心がある
そんなあなたへ。20世紀の古典・名著である『民主主義と教育』から、デューイの民主主義論について書かれた箇所をピックアップし、わかりやすく解説・考察します。
- 書籍名:民主主義と教育 上
- 著者:J. デューイ (著), John Dewey (原名), 松野 安男 (翻訳)
- 出版社 : 岩波書店 (1975/6/16)
- 発売日 : 1975/6/16
- 言語 : 日本語
- 文庫 : 304ページ
教育とは直接的な経験から出発し,これを絶え間なく再構成・拡大深化してゆく過程である.従って,それは子供や学校の問題にとどまらない.とすれば民主主義社会における教育とは何か.教育に関する在来の学説をこの観点から根本的に洗い直し,デューイ自身の考え方を全面的に展開し世界の教育界の流れを変えた二十世紀の古典.
岩波書店 この本の内容より
デューイ『民主主義と教育』を読む(民主主義編)
【書を読む】要約・ポイント
本のなかで印象に残った箇所を5つ引用します。難しいと感じる人は、要約・ポイントだけでもお読みいただき、本書のアイデアにぜひ触れてみてください。
要約・ポイント①
共通の目的を持ち、その目的に向かってともに行動するとき、私たちは初めて共同体になる。そのためには、他者に開かれた真のコミュニケーション—— 単なる情報の伝達ではなく、自らの変容をもたらすような経験を共有することが不可欠なのである
人々は、ただ物理的に接近して生活することだけでは、社会を形成しはしない。〔…〕しかしながら、それらがすべてその共通の目的を知っており、それに関心をもっており、そのためそれらがその共通の目的を考慮しながら自分たちの特定の活動を調節するならば、それらは共同体を形成することになる。だが、このことは通信を必要とするのである。〔…〕
『民主主義と教育 上』デューイ著 p16〜18
社会生活が通信と同じことを意味するばかりでなく、あらゆる通信(したがって、あらゆる真正の社会生活)は教育的である。通信を受けるととは、拡大され変化させられた経験を得ることである。人は他人が考えたり感じたりしたととを共に考えたり感じたりする。そしてその限りにおいて、多かれ少なかれ、その人自身の態度は修正される。そして通信を送る側の人もまたこのままでいはしない。ある経験を他人に十分にそして正確に伝えるという実験をしてみると、とりわけその経験がいくぶん複雑な場合には、自分の経験に対する自分自身の態度が変化しているのに気づくだろう。さもなければ無意味な言葉を使ったり叫び声をあげたりすることになる。
要約・ポイント②
社会は、多数の小集団がゆるく結びついたものである。それぞれの小集団・小社会は多様な価値観・目的・物語をもって生活している
社会とは一つの単語であるが、それは多くの物を意味している。 人々は、あらゆるやり方で、あらゆる目的のために、互いに結びつく。一人の人間がたくさんの異なった集団に関与しており、それらの異なった集団では、その仲間が全く異なっていることが ある。しかも、それらは、共同生活の諸様式であるという点以外は、何ら共通なものをもっていないように見えることがしばしばある。比較的大きな社会組織の中には、どれにも、多数のより小さな集団がある。それらは、行政上の下位区分だけでなく、産業上、学問上、宗教上の結合でもある。互いに異なった目的をもつ政党、社交仲間、派閥、徒党、団体、組合、血縁によって堅く結びつけられた集団、等々、その他際限なく多様な集団がある。〔…〕
『民主主義と教育 上』 デューイ著 p133〜135
社会哲学では、〔…〕社会は、ただその本質だけによって一個の社会と考えられるのである。この統一体に伴う諸特質、すなわち目的や福利の見事な共有、公共の目的への忠誠、人々相互の同情心が強調されるのである。けれども、社会という用語の本質的な内包的意味だけに注意を局限しないで、その用語が外延的に指し示す諸事実にも注目するならば、われわれは、統一体ではなくて、 善悪さまざまの多数の社会の存在に気づく。〔…〕集団によって与えられる教育はどれもみなその集団の成員を社会化する傾向をもつが、その社会化の質および価値は、 その集団の習慣と目標によって決まるのである。
要約・ポイント③
民主的な社会集団であるかを判断する2つのチェックポイント
- 共有される関心が多様であること
- 他集団との多様で自由な接触点があること
それゆえに、ここで再び、任意の既存の社会生活の様式の価値を測る尺度が必要になる。〔…〕すなわち、意識的に共有している関心が、どれほど多く、また多様であるか、そして、他の種類の集団との相互作用が、どれほど充実し、自由であるか、ということである。〔…〕
『民主主義と教育 上』 デューイ著 p135〜141
われわれの判断基準の二つの要素はともに民主主義を指向している。第一のものは、共有された共同の関心が、より多くの、より多様な事柄に向かうことを意味しているだけでなく、相互の関心を社会統制の一要因として確認することにより深い信頼をおくことをも意味している。第二のものは、(分離状態を維持しようと思えばそうすることができたあいだ、かつては孤立していた)社会集団が互いにより自由に相互作用することを意味しているだけでなく、社会的習慣に変化が起こること——すなわち、さまざまの相互交渉によって産み出される新たな状況に対処することによって絶えずそれを再適応させること——をも意味しているのである。そして、これら二つの特徴こそ、まさに、民主的に構成された社会を特色づけるものなのである。
要約・ポイント④
民主主義とは、単なる政治制度ではなく、共同生活の一形態。それは人々の内面から育まれるものであり、そのために教育が必要とされる
いろいろな関心が相互に浸透しあっており、進歩すなわち再適応が考慮すべき重要問題になるような、そういう種類の社会生活を実現するために、民主的共同社会は、他の共同社会よりも、計画的で組織的な教育にいっそう深い関心を向けるようになる、ということである。〔…〕民主的社会は、外的権威に基づく原理を否認するのだから、それに代るものを自発的な性向や関心の中に見出さなければならない。それは教育によってのみつくり出すことができるのである。しかし、 さらに深い説明がある。民主主義は単なる政治形態でなく、それ以上のものである。つまり、それは、まず第一に、共同生活の一様式、連帯的な共同経験の一様式なのである。
『民主主義と教育 上』 デューイ著 p141〜142
要約・ポイント⑤
民主主義的な生き方によって、人々は新たな価値観や刺激にさらされる→個人の能力が開花する(民主主義とは教育的である)
人々がある一つの関心を共有すれば、各人は自分自身の行動を他の人々の行動に関係づけて考えなければならないし、また自分自身の行動に目標や方向を与えるために他人の行動を熟考しなければならないようになるのだが、そのように一つの関心を共有する人々の数がますます広い範囲に拡大して行くということは、人々が自分たちの活動の完全な意味を認識するのを妨げていた階級的、民族的・ 国土的障壁を打ち壊すことと同じことなのである。このように接触点がますます多くなり、ますます多様になるということは、人が反応しなければならない刺激がますます多様になるということを意味する。その結果、その人の行動の変化が助長されることになるのである。排他性のために多くの関心を締め出している集団では行動への誘因は偏らざるをえないのであるが、そのように行動への誘因が偏っている限り抑圧されたままでいる諸能力が、多数の多様な接触点によって解放されるようになるのである。
『民主主義と教育 上』 デューイ著 p142
【思考する】解説・考察
『民主主義と教育』は、20世紀アメリカを代表する哲学者・教育学者、ジョン・デューイの代表的著作です。
情報量は膨大で、手ほどきなしで読み進めるのは困難ですが、一度その扉を開くと、多様な読み方ができる奥深い本でもあります。教育論としても示唆に富みますが、今回は「民主主義」や「社会」について論じた箇所を中心に読み取っていきます1。
民主主義とは共同生活の一様式である
デューイの民主主義論の特徴は、人間の生き方そのものとして民主主義を捉えている点にあります。民主主義とは、多様な社会集団に属する人々の共同生活の中で、絶えず表現され続ける理念であり、単なる政治形態としての民主主義とは一線を画します。
また、デューイの民主主義論の前提となる社会モデルでは、社会を1つの大きなまとまりとしてではなく、多数の小さな集団のゆるい結びつきであると捉えます。それぞれの小集団・小社会は多様な価値観・物語をもって生活を送っており、デューイは民主主義の本質を、小集団の中に生きる人々の日常的な交わりの中に見出しました。
あなたの所属する集団は民主的か?
『民主主義と教育』で、デューイはそれぞれの小集団が民主的であるかどうかを測る2つの基準を提示しています。
- 共有される関心が多様であること
- 他集団との多様で自由な接触点があること
例えば、窃盗団という小集団は、盗品についての限定的な関心を共有しますが、それ以上に関心が多様になることはありません。また、窃盗団は他集団から自分たちを孤立させることによってしか行動できず、他集団との接触点が多様であるとは言えません。
このように限られた価値観しか認められず、別の価値観・物語をもつ外部との多様な接触点がない、外部に開かれていない社会は民主的とは言えないとデューイは考えました。
民主主義はあくまでも “方向性”。価値観は多様であっていい
先に示した2つの基準からわかるように、民主主義は多様な価値観に開かれており、単一の理想・価値観へと導く理念ではありません。
いうならば、民主主義とは “方向性” です。向かっている大きな方向は同じだけれども、細かいゴール・コース(価値観)は多様であっていいということ。
- “多様” な小集団
- “方向性” としての民主主義
これら2つを通して、デューイは多様性の尊重と社会の統合という、一見すると相反する価値を巧みに調和させようとします。
デューイは、「相互の関心を社会統制の一要因として確認することにより深い信頼をおく2」といいます。つまり、ただ価値観の多様性を強調するだけでなく、自分とは異なる価値観を認め、互いに関心を持つことでまとまりが生まれるような「多様でありながら統合された社会」を目指しているのです。
なぜ民主主義と「教育」なのか
すでに述べた通り、この本は教育論としても示唆に富んでいます。詳細は別記事に譲るとして、ここではなぜ民主主義と「教育」が結びつくのかという点だけを先出ししておきます。
デューイによると、民主主義は単なる政治制度ではなく、「生活様式」や「生き方」でした。
民主主義的な生き方—— 人々が自由に交流し、共に問題を解決していくプロセスを通して、私たちは多様な経験をし、変化を続けます。つまり、民主主義とはそれ自体がすなわち教育的な営みにほかなりません。
また、民主主義は上から与えられるものではなく、人々の内面から育まれていくもの。そこで鍵となるのが教育活動だということです。(デューイの著書『学校と社会』には「学校=小さな社会」という発想も見られます)
このような観点から、デューイの民主主義論は教育論へとつながっていきます。
まとめ
『民主主義と教育』から、デューイの民主主義論がわかる箇所をピックアップして紹介しました。
- “バカは相手にするな” 的言説の台頭
- SNS での “エコーチェンバー現象3”
- 多様性の旗印の下でくり広げられる “自己中”
- 政治的、文化的、宗教的対立の激化
グローバル化・情報化とともに急速に “分断” が進む現代社会。
「共通の目的を掲げて、民主的な対話をしよう」と声高に訴えるデューイの思想は、あまりに楽観的・理想的すぎると感じるかもしれません。
しかし、なかなか一枚岩になりづらく、しかも問題解決に政治が十分に機能を果たさない今だからこそ、「民主主義とは単なる政治制度ではなく、生活様式であり生き方そのものである」というデューイの思想に耳を傾ける価値があるとも言えると思います。
デューイが提示した民主主義のチェックリスト
- 共有される関心が多様であること
- 他集団との多様で自由な接触点があること
自分の属する集団や、自分自身はこのチェックリストに当てはまっているでしょうか?
デューイは、他者に開かれた民主主義的な生き方をすることで、人も社会も大きく成長していくと言います。生き方としての民主主義的への第一歩を踏み出し、自分自身がより大きく成長するきっかけとして、ぜひ一度振り返ってみてください。
【参考文献】
『民主主義と教育 上』デューイ著 松野 安男訳
【初心者向け デューイおすすめ本】
①ジョン・デューイ―現代を問い直す
教育論、民主主義論、宗教論など幅広くまとめられた1冊。デューイ思想の全体像を掴むのにおすすめ。
②ジョン・デューイ 民主主義と教育の哲学
2022年出版と比較的新しく、初学者でも読みやすいデューイ入門書。デューイ研究の第一人者が、デューイの生涯を辿りながら、その思想を丁寧に読み解きます。
『ジョン・デューイ 民主主義と教育の哲学』は “聴く読書” Audible(オーディブル)の無料体験でも視聴可能です。
オーディブルは30日間無料で体験できます。オーディブルで、あなたの日常に刺激とインスピレーションを。