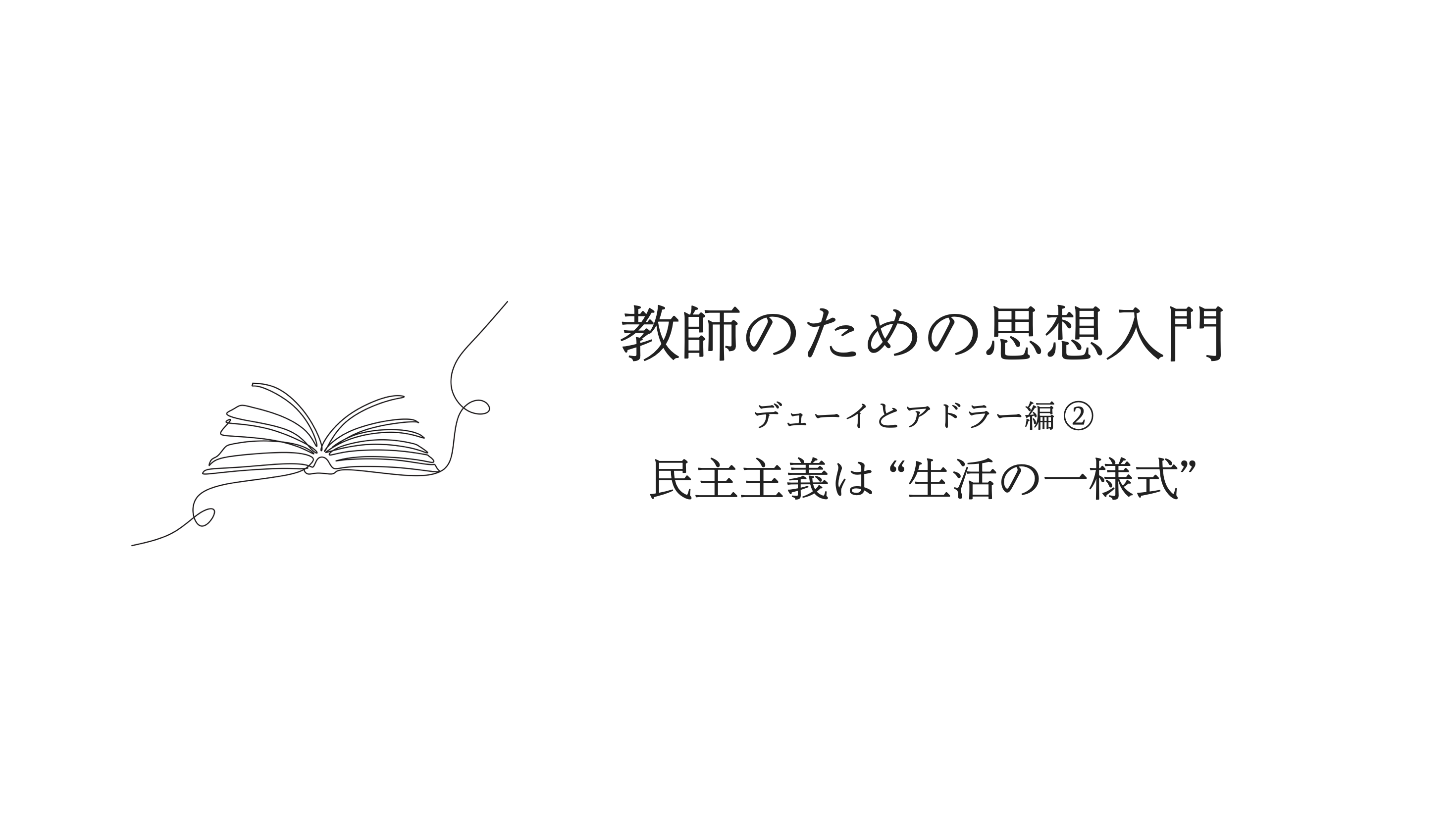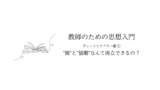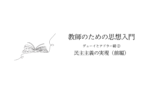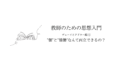▼ 前回の記事はこちら
新人教師のことはは、「個」と「協働」の両立に悩み、本屋「あつゆる書房」の店主あつゆるに相談を持ちかけた。あつゆるは、この問題に取り組んだ思想家としてジョン・デューイを紹介。デューイの著書『民主主義と教育』を手に取ったことはは、そこに書かれた「民主主義」の概念に興味を抱く。それは単なる政治制度ではなく、人々の「共同生活の一様式」だという。果たして、デューイの思想は現代の教育問題にどんな示唆を与えてくれるのか…。
あつゆる:
ほら、これがデューイの『民主主義と教育』という本だよ。
ことは:
うわ…。なんだか難しそう。思わず、採用試験の参考書を見てるときのトラウマが…。
あつゆる:
はは、分かるよ。私も最初この本を手に取った時は「これ、人類の言葉?」って思ったもの。でも、実は人間の生き方について、すごく面白いことが書かれてるんだ。
ことは:
本当ですか?でも民主主義って政治の話じゃ…。あ!そう言えば、最近、生徒会選挙の時に「これが民主主義だね」って話したばかりです。
あつゆる:
選挙は確かに民主主義の大切な要素だね。でもね、デューイの考える民主主義はもっと広い意味を持ってるんだ。彼は「共同生活の一様式」って言ってる。
ことは:
共同生活の一様式?なんだか難しそうですけど…あ、最近参加し始めた読書会のことを思い出しました。
あつゆる:
読書会?
ことは:
はい。本が好きで入ってみたんですけど、みんなの本の解釈が全然違うんです。最初は戸惑って…。でも、その違いが面白くて。ただ、時々悩むんです。自分の意見をどこまで言っていいのかとか…。
あつゆる:
それは興味深い例だね。実はデューイは、社会を多様な小集団の集まりとして見ていたんだ。家族、職場、趣味のサークル、地域のコミュニティ…。
ことは:
あ!確かに私も、読書会、地域の清掃ボランティア、学校、大学時代の友達…。いろんな集団に属してますね。
あつゆる:
そうそう。で、デューイはこれらの集団が「民主的」かどうかを判断する面白い基準を示してるんだ。
ことは:
基準?
あつゆる:
うん。2つあって…。
- その集団の中で共有している関心がどれだけ多様か
- 他の集団とどれだけ自由にやりとりしているか
ことは:
(少し考えて)あ…!読書会での経験、これに当てはまりそう。みんな「本を読むこと」は共通してるけど、その人の経験や考え方で全然違う世界が見えてくる。そして、それぞれが職場や家庭での経験を話してくれて…。
あつゆる:
なるほど。私も似たような経験があってね。昔、写真サークルに入ってた時、最初は「いい写真を撮ること」だけを考えてた。でも、メンバーの一人が地域の祭りの記録を始めて…。そこから、お祭りの実行委員の人たちと知り合って、写真の楽しさだけじゃなく、地域の歴史や人々の思いを知ることになったんだ。
ことは:
へぇ、素敵な経験ですね。でも、あつゆるさん。集団って、ある程度は「閉じて」ないと、その良さが薄まっちゃいませんか?
あつゆる:
いい指摘だね。ここで面白い例を考えてみようか。ちょっと極端だけど…窃盗団という集団を想像してみて。
ことは:
え?なんだか怖い例えですけど…。
あつゆる:
窃盗団って、「盗む」という限られた関心しか共有できないし、他の集団と自由に交流することもできない。これはデューイの言う「民主的」な集団からは遠いわけだね。
ことは:
なるほど…。でも、現実の集団って、そこまでではないにしても、やっぱり閉じる傾向にありますよね。読書会でも最初は「正しい読み方」みたいなのにこだわってて…。
あつゆる:
そうだね。デューイも完璧な開放性を求めているわけじゃないんだ。彼は「相互の関心を社会統制の一要因として確認することにより深い信頼をおく」って言ってる。
ことは:
また難しい…。
あつゆる:
うん、確かに難しい言い方だね。でも、さっきの読書会の例で考えてみない?
ことは:
はい。先週読んだ本の解釈で、私とまったく違う意見の人がいて…。最初は「どうしてそんな読み方になるの?」って思ったんです。
でも、その人が保育士としての経験を話してくれて。子どもたちに絵本を読み聞かせる時の話とか…。そこから、その人が関わっている地域の子育て支援の活動のことも知って…。
あつゆる:
なるほど。本を読むという共通の関心から始まって、でも話は自然と広がっていく。お互いの背景や活動に関心を持ち合う…。
ことは:
そうなんです!面白いことに、今度は子育て支援の活動に参加してる親御さんたちが、「子どもの本について語り合える場所があれば…」って言って。今度、読書会に来てくれることになったんです。
あつゆる:
その体験、まさにデューイの言う「相互の関心」かもしれないね。読書会という集団も、子育て支援という集団も、完全に閉じるわけでもなく、かといって無秩序に混ざるわけでもなく。
それぞれの活動を大切にしながら、自然とゆるやかにつながっていく…。
ことは:
あ…!それって、社会全体で見ると、いろんな集団が少しずつ重なり合って、でもバラバラにならず、なんとなくまとまりができていく、みたいな…?
あつゆる:
その通り!強制的なルールじゃなくて、お互いへの関心が自然と社会の調和を生んでいく。そして、その中で私たちは様々な異なる考え方や価値観に触れることになる。
デューイはそれを「行動への誘因が偏っている限り抑圧されたままでいる諸能力が、多数の多様な接触点によって解放される」って言ってるんだ。
ことは:
なるほど…。読書会と子育て支援のつながりみたいに、異なる活動や考え方に触れることで、自分の中の新しい可能性に気づける…?
あつゆる:
そうそう!それに、その気づきがまた新しいつながりを生んでいくんだよね。
ことは:
なんだか、目の前が少し広がった気がします。でも同時に、難しさも感じます…。この本、少し読んでみようかな。
あつゆる:
それはいいね!きっとことはさんの活動にもヒントが見つかるはずだよ。
ことは:
はい!分からないところがあったら、また聞きに来てもいいですか?
あつゆる:
もちろん。この本、私も何度も読み返してるんだけど、その度に新しい発見があるんだよね。一緒に考えていけたらいいな。
ことは:
ありがとうございます!…あ、でも、もし私が理解できなかったら、「デューイ先生に申し訳ない」って落ち込まないようにします!(笑)
あつゆる:
(笑)そうそう。デューイも「完璧な理解」より「学び続けること」の方が大切だって言ってると思うよ。
▼ 続きはこちら
参考文献
Dewey, J. (1916) Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education. In: Boydston, Jo Ann (ed) (1980) Collected Works of John Dewey, The Middle Works, 1899-1924(9) Carbondale: Southern Illinois University Press. =(1975)『民主主義と教育(上)(下)』松野安男訳 岩波文庫