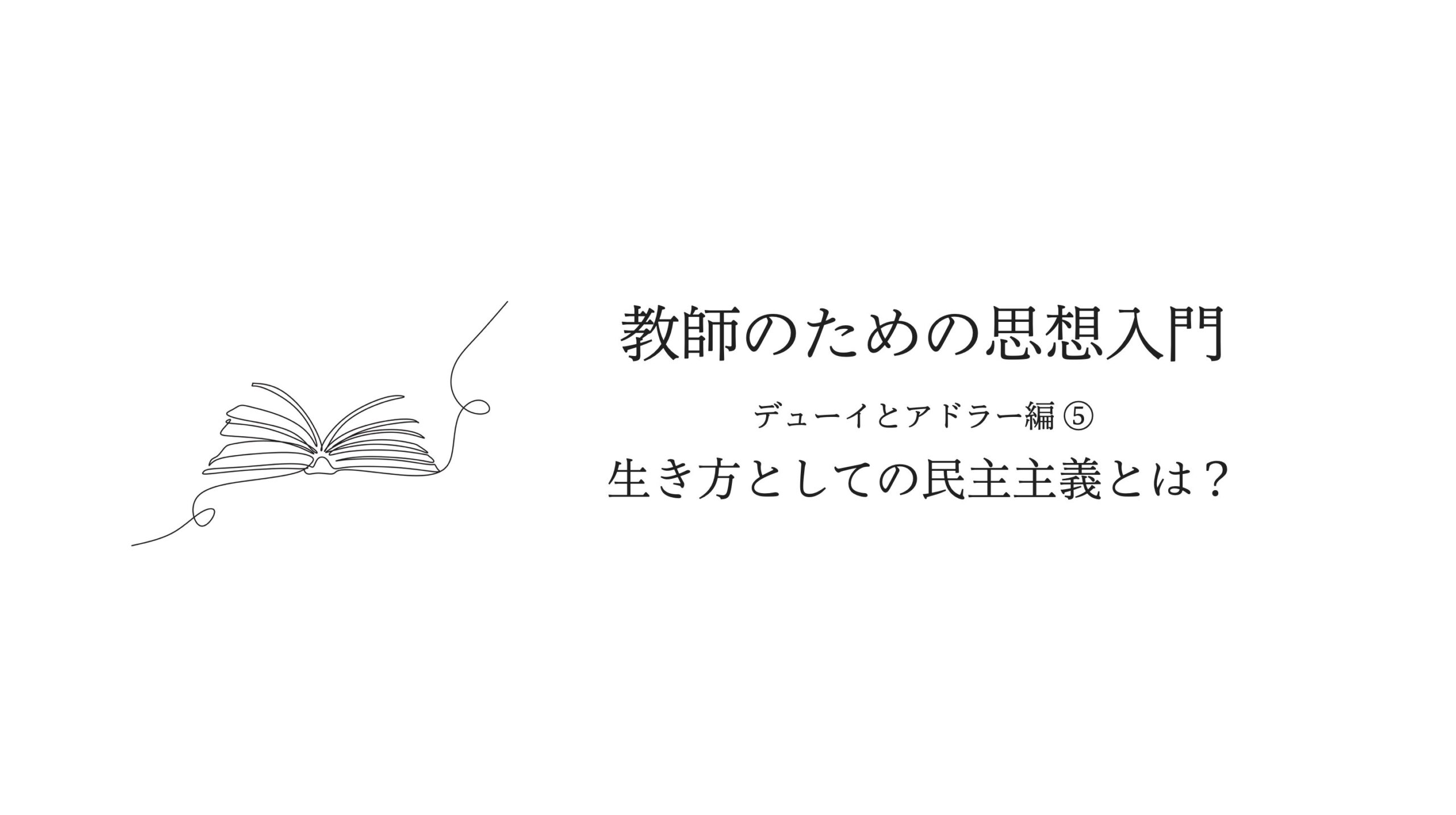▼ 前回の記事はこちら
あらすじ
教員3年目のことはは、本屋「あつゆる書房」の店主あつゆるとデューイの民主主義論について語り合っていた。現代社会の問題点と、それに対するデューイの「グレイト・コミュニティ」という考え方について学ぶ中で、ことははある気づきを得る—。
ことは:(少し考え込んで)あつゆるさん、気づいたんですけど。デューイさんの言う民主主義って、もはや人の生き方そのものみたいですね。生活様式だったり、コミュニケーションと直結していたり…。
あつゆる:おっ!鋭い気づきだね。実は、デューイの後期の論文『創造的民主主義』で、まさにそのことを扱っているんだ。
ことは:へぇ!でも、なんで「創造的」民主主義なんですか?
あつゆる:それはね、デューイが民主主義を「生き方」そのものとして捉え直したからなんだ。彼によれば、民主主義は「個人的な性格を形成し、生活のあらゆる関係における欲望と目的を決定するような、ある態度の所有と継続的な使用を意味する」んだって。
ことは:むずかしい…。つまり、民主主義は個人の性格や態度で、生活のなかで実践されるってことですか?
あつゆる:そうそう。例えば…デューイは「生き方としての民主主義」について、こんなことを言ってるんだ。
ことは:はい。
あつゆる:まず、人種、肌の色、性、生まれにかかわらず、だれにでも可能性があると信じること。
ことは:ふむふむ…。
あつゆる:それから、教育、表現の自由、オープンな情報など、条件が整えば、人間は知的な判断ができると信じること。
ことは:なるほど…。
あつゆる:そして、自分と異なる他者から学び、友好的に協働する。トラブルが起こっても対話で解決する。
ことは:(少し困ったような表情で)なんか…。
あつゆる:なんか…?
ことは:綺麗事というか、学校の道徳みたいですね!だって、「みんな仲良く」って言っても…。
あつゆる:(うなずきながら)その反応、すごくよく分かる。実はデューイ自身も、これが道徳的にありふれたことだって認めてるんだ。でも、彼はそれこそが重要だと考えたんだよ。
ことは:えっ?じゃあ、なんでデューイさんはわざわざそんなことを言う必要があったんですか?
あつゆる:それには、彼が生きていた時代背景が関係しているんだ。この論文を書いたのが1939年…。ヨーロッパではナチスが台頭し、ソ連ではスターリンの独裁が強まっていた。民主主義そのものが危機に瀕していた時代だったんだ。
ことは:ああ…。そう言えば、ナチスって民主的な選挙で権力を握ったんですよね?
あつゆる:そう。これは重要な点なんだ。たとえ制度としての民主主義があったとしても、1人1人が民主的な人格として成長しないと、本当の意味での民主主義は実現できない。デューイはそう考えたんだ。
ことは:(深く考え込んで)なるほど…。選挙だけじゃなくて、普段の生活の中でも、自分と違う意見を否定したり、暴力的な解決を求めたり…。そういう1つ1つの選択が、民主主義を脅かすことになるんですね。
あつゆる:その通り。「民主主義とは、自由で、充実した交流のある生活につけられた名前」とデューイは言っている。確かに理想に近いかもしれない。でも…。
ことは:でも?
あつゆる:日々の小さな実践の積み重ねが大切なんだ。さっきの例で言えば、異なる意見を最初から否定せずに、まずは相手の立場に立って考えてみる。対立が起きても、暴力ではなく対話を選ぶ…。
ことは:(少し明るい表情で)そうか…。理想は遠くても、今日、明日とできることから始めていく。それが「創造的」ってことなのかもしれませんね。
あつゆる:(微笑んで)民主主義は、そうやって私たちの手で少しずつ創られていくものなんだよ。
(続く)
参考文献
Dewey, J. (1939) Creative Democracy-The Task Before Us. In: Boydston, Jo Ann (ed) (1988) Collected Works of John Dewey, The Later Works, 1925-1953(14): 224-230. Carbondale: Southern Illinois University Press.