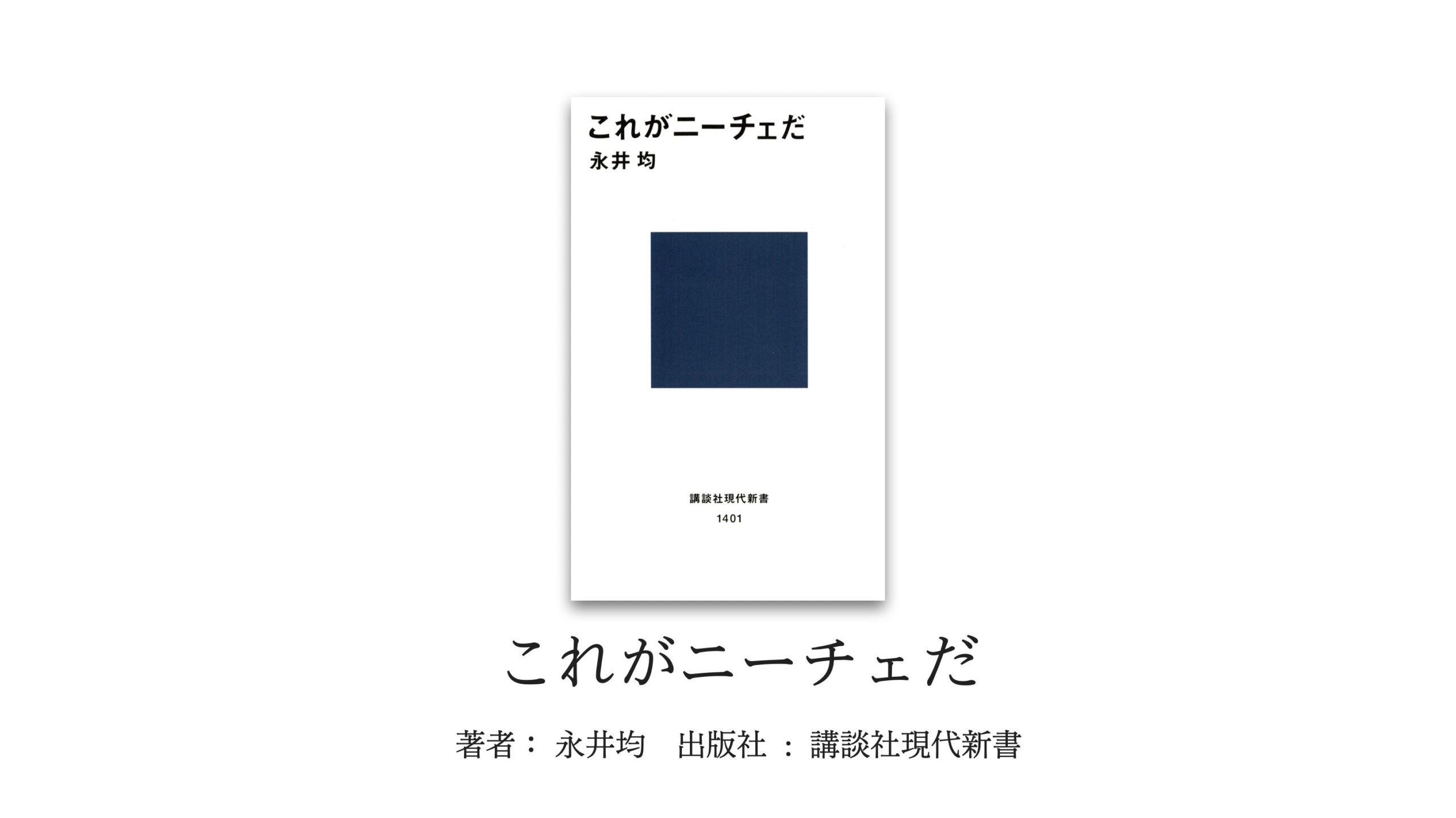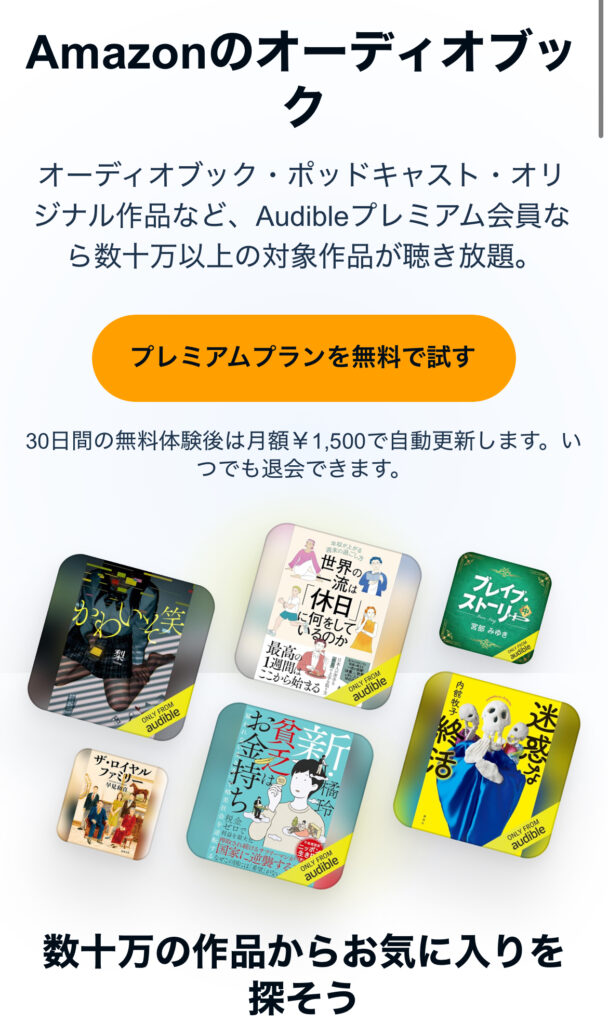これまでニーチェについて書かれた多くの書物に不満がある。それらはたいてい、ニーチェという人物とその思想を、何らかの意味で世の中にとって意味のあるものとして、世の中の役に立つものとして、描き出している。私には、そのことがニーチェの真価を骨抜きにしているように思える。ニーチェは世の中の、とりわけそれをよくするための、役に立たない。どんな意味でも役に立たない。だから、そこにはいかなる世の中的な価値もない。そのことが彼を、稀に見るほど偉大な哲学者にしている、と私は思う。
『これがニーチェだ』(永井均著・講談社現代新書)p7
この挑発的な言葉から、『これがニーチェだ』(永井均著・講談社現代新書)は始まる。ニーチェに惹かれて3年。何度も読み返している愛読書である。
『これがニーチェだ』が開く思索の扉|固定的な理解を拒む危うい対話
第一空間 ニヒリズムとその系譜学
永井は、ニーチェの思想を「3つの空間」として描き出す。
第一空間は、私たちがよく知る世界だ。「こうあるべき」「ああすべき」という声が響く。
人は善くあろうとし、できないときは自分を責める。他人の行動を裁き、時に憎む。
ニーチェはここに、弱者の強者への怨み、ルサンチマンを見出す。しかしそれは単なる批判ではない。むしろ、私たちの価値観そのものが、この怨みから生まれたことを明らかにする。
この洞察は、私たちの「善悪」の感覚を根底から揺るがす。それは既存の社会規範や道徳的価値観をすべて打ち砕く破壊力を持つ。
私たちが「正しい」と信じてきた判断の根底には、実は怨みや憎しみという感情が潜んでいる―この発見は、社会を支える基本的な価値観を根こそぎにしかねない危うさを持つ。
第二空間 力への意志とパースペクティヴ主義
固定的な「善悪」は消え、すべてが力の関係として現れる。そこから第二空間が開ける。
たとえば、朝の目覚め。「起きよう」という力と「まだ眠っていたい」という力が絡み合う。眠気は徐々に薄れ、目覚めは少しずつ強まり、時には深い眠りに引き戻される。
「私が意志した」なんて、後からつけた解釈に過ぎない。実体としての「意志」など存在しない。あるのは、絶え間ない力関係の流れだけだ。
この力関係の視点からは、私たちの「客観的な理解」さえも1つのパースペクティヴ(観点)として現れる。
たとえば、科学者は実験と観察から世界を理解しようとし、芸術家は感性を通じて世界を捉える。それぞれの見方は、その生き方から必然的に生まれる世界の解釈なのだ。
これらの異なるパースペクティヴは、互いに影響を与え合い、時に対立し、時に協力しながら、より大きな影響力を求めて争う。私たちが「真理」と呼ぶものも、こうした解釈の1つにすぎない。
このような力への意志の思想は、多くの人々を魅了してきた。
既存の価値観や道徳を超えて、自らの生を力強く肯定する道筋として。ニーチェが語る「超人」は、まさにそのような存在として理解されることが多い。
道徳という重荷を投げ捨て、自らの価値を創造する強者。自分の人生を自分の意志で切り開く者。「より強く生きよ」「自分の価値観を持て」―こうしたメッセージとして、ニーチェは読まれ続けてきた。
しかし、この理解もまた1つの固定化された解釈に過ぎない。
「強く生きる」「自分の価値観を持つ」という新たな命令が、いつの間にか生まれている。力への意志という解釈すら、新たな「正しい理解」として固定化される危険性を持つ。
第三空間 永遠回帰=遊ぶ子供の聖なる肯定
この行き詰まりを突き抜けるところに、第三の空間が開ける。永井は書く。
永遠回帰思想の最大のポイントは現実肯定にある。この世界を、外部からの意味づけによってではなく、現実であることそれ自体によって、この瞬間を、過去や未来の視点からの意味づけによってではなく、今であることそれ自体によって、この人生を、他者や外部の視点からの意味づけによってではなく、自分であることそれ自体によって、そのまま肯定することを、それは教えるのである。だからその肯定は、この世界を、この瞬間を、この人生を、それ自体として、奇跡として、輝かしいものとして、感じるがゆえに、おのずとなされる肯定でなければならない。
『これがニーチェだ』(永井均著・講談社現代新書)p180
この肯定は、単なる「そのまま受け入れる」という態度ではない。むしろ、この瞬間がそのまま永遠に繰り返されるとしても、なお肯定できるような生の充実を示唆している。
ニーチェはこの境地を『ツァラトゥストラはかく語りき』で「幼子」として描く。
幼子は無垢だ。忘れる。新たな始まりだ。遊ぶ。みずから回る輪だ。最初の運動だ。聖なる「然りを言うこと」だ。
『ツァラトゥストラはかく語りき』(ニーチェ著・河出文庫)p42
幼子は「自然に遊ぼう」なんて考えない。ただ純粋に遊びに没入している。
この境地で示唆されているのは、すべての価値づけが消え去る「大いなる正午」の時である。
それは太陽が頭上に来て影が消えるように、主体と客体、善と悪、といったあらゆる二元的な区別が溶解する瞬間だ。
それは仏教の「空」に通じる。固定的な実体も、永遠の価値も存在しない。ただ在るがままに在る。
“理解” から “対話” へ
しかし、このような第三空間を「理解」しようとする瞬間、私たちは奇妙なパラドックスに直面する。
「価値づけから自由になれ」という新たな価値観を作り出してしまうのだ。
「理解しよう」とすれば、その瞬間に理解から遠ざかる。私たちの「わかりたい」という欲望自体が、理解を妨げる壁となる。
私たちは通常、何かを理解することで、それを活用したり、生活に役立てたりしようとする。
しかしニーチェの思想は、そうした「役立て方」自体を疑問に付す。それは「より良い生き方」を教えてくれるわけでもなく、「正しい理解」に到達させてくれるわけでもない。
だからこそ永井が示唆するように、ニーチェの思想は1つの芸術作品として読むことができる。
それは最終的な解釈を拒み続ける作品として。私たちはニーチェの投げかける問いと向き合い、時に戸惑い、時に反発しながら、自分なりの仮説を組み立て、また崩していく。
その終わりのない思考の運動の中で、私たちは新たな可能性に触れる。
それは時に不安定で危うい道のりかもしれない。しかし、その不安定さこそが、思考を生き生きとしたものにするのだ。