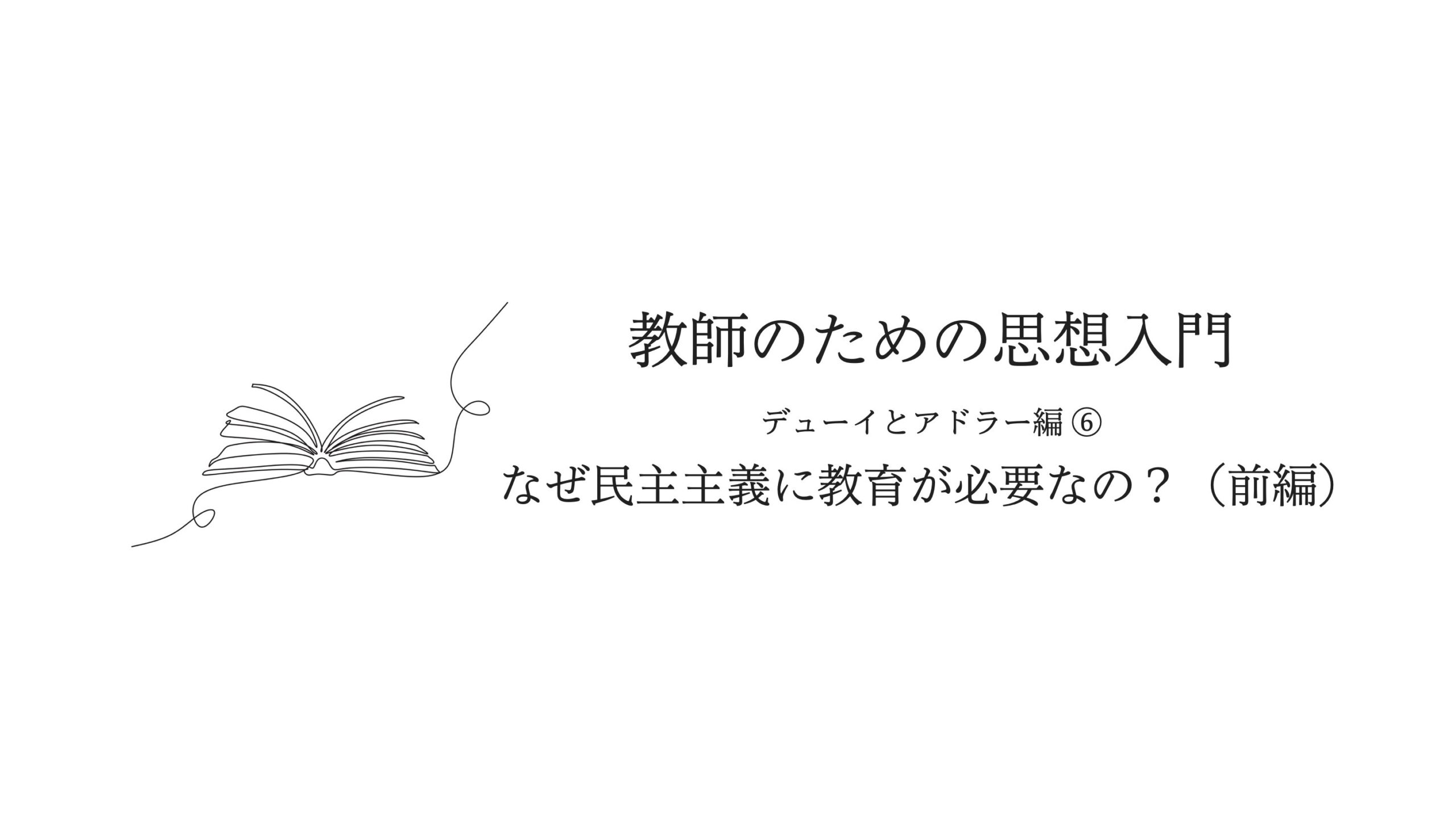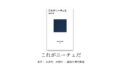▼ 前回の記事はこちら
デューイの「生き方としての民主主義」について語り合う中で、その実現には一人一人の成長が不可欠だと気づいたことは。そこから自然と、教育の役割への関心が深まっていく。果たして、民主主義を育む教育とは、どのようなものなのだろうか…。
ことは:(考え込みながら)あつゆるさん、さっきの話を聞いていて気になったんですけど…。
あつゆる:うん?
ことは:民主主義が「生き方」だとして、その生き方って、どうやって身につけていくんでしょうか?
あつゆる:そこにたどり着くとは鋭い!実はデューイはまさにその点を突き詰めて考えていて、「教育」の役割を強調してるんだ。
ことは:教育ですか…。でも、最近の子どもたちを見ていると、環境の変化についていくのが難しそうで…。SNS の問題もあるし、価値観も多様化してるし…。
あつゆる:そうだよね。デューイも、社会が複雑化する中で、人々の接触点が増え、対応しなければならない刺激も多様化していくって言ってる。だからこそ、計画的な学校教育が必要不可欠なんだって。
ことは:(不思議そうに)どうして「計画的」なんですか?
あつゆる:その答えは、デューイの人間観の中にある。彼は、人間を「環境との相互作用の中で絶えず自己を更新し続ける存在」として見ていたんだよ。
ことは:自己を更新…?
あつゆる:そうだね。身近な例で考えてみよう。新しいクラスを持った時のこと、覚えてる?
ことは:(少し表情を明るくして)ああ!最初は緊張して、自分のやり方が通じるか不安で…。でも、少しずつ生徒の反応を見ながら、自分のスタイルを作っていった気がします。
あつゆる:それこそが「環境との相互作用」なんだ。でもデューイが面白いのは、それを一方通行じゃなく見てるところなんだよ。
ことは:一方通行じゃない?
あつゆる:そう。環境に合わせて自分が変わるだけじゃなくて、自分の目的のために環境の方を変えていくっていう側面も。
ことは:あ!それって、私が授業の雰囲気を少しずつ作っていったみたいな…?
あつゆる:(うなずきながら)デューイはそれを「改造の主体」って呼んでる。でもね、そういう変化って、実はすごく大変なプロセスなんだ。
ことは:(深くうなずいて)それ、すごく分かります…。新しい取り組みを始めると、最初はすごく居心地が悪くて。つい、慣れた方法に戻りたくなって…。
あつゆる:そうそう、デューイはそれを「習慣の再調整」って呼んでる。「重苦しい努力」を伴う「不愉快な状況」だって。
ことは:まさにその通りです!でも…その不快な状況から逃げ出したら、成長できないですよね。
あつゆる:そう。だからデューイは「一時的な失意に耐え、障害に直面しても屈しないで、楽しいことも苦しいことも共に引き受けることのできる」生き方を大切にした。
ことは:(少し考えて)そう考えると…子どもたちの成長って、すごく大変なプロセスかもしれません。新しい環境に適応しながら、でも自分らしさも失わずに…。
あつゆる:特に今の複雑な社会では、子どもたちの最初の能力と、求められる環境との間には大きなギャップがある。それを埋めていくのが教育の役割なんだ。
ことは:なるほど、だから「計画的な」教育が必要なんですね。でも、その計画って具体的には…?
あつゆる:デューイは「教育の過程は連続的な再編成、改造、変形の過程」だって言ってる。つまり、一気に大きな変化を求めるんじゃなくて…。
ことは:少しずつ、でも着実に…?
あつゆる:その通り。学校は、個人が「連続的に」成長していける場所。大きすぎず小さすぎない、適度な葛藤を引き起こしていく場になることが期待されるんだよ。
ことは:(目を輝かせて)そういう学校って、具体的にはどんな場所なんでしょう?
あつゆる:それこそがデューイの教育論の核心にある。学校は単なる知識を教える場所じゃなくて…。
ことは:(少し考えて)あ、そういえば…。さっきまで民主主義の話をしてましたよね。その民主主義と教育って、具体的にどうつながるんでしょう?民主主義を育む学校って、どんな場所なんですか?
あつゆる:その問いこそ、デューイが最も大切にしていたものなんだ…。
▼続きはこちら