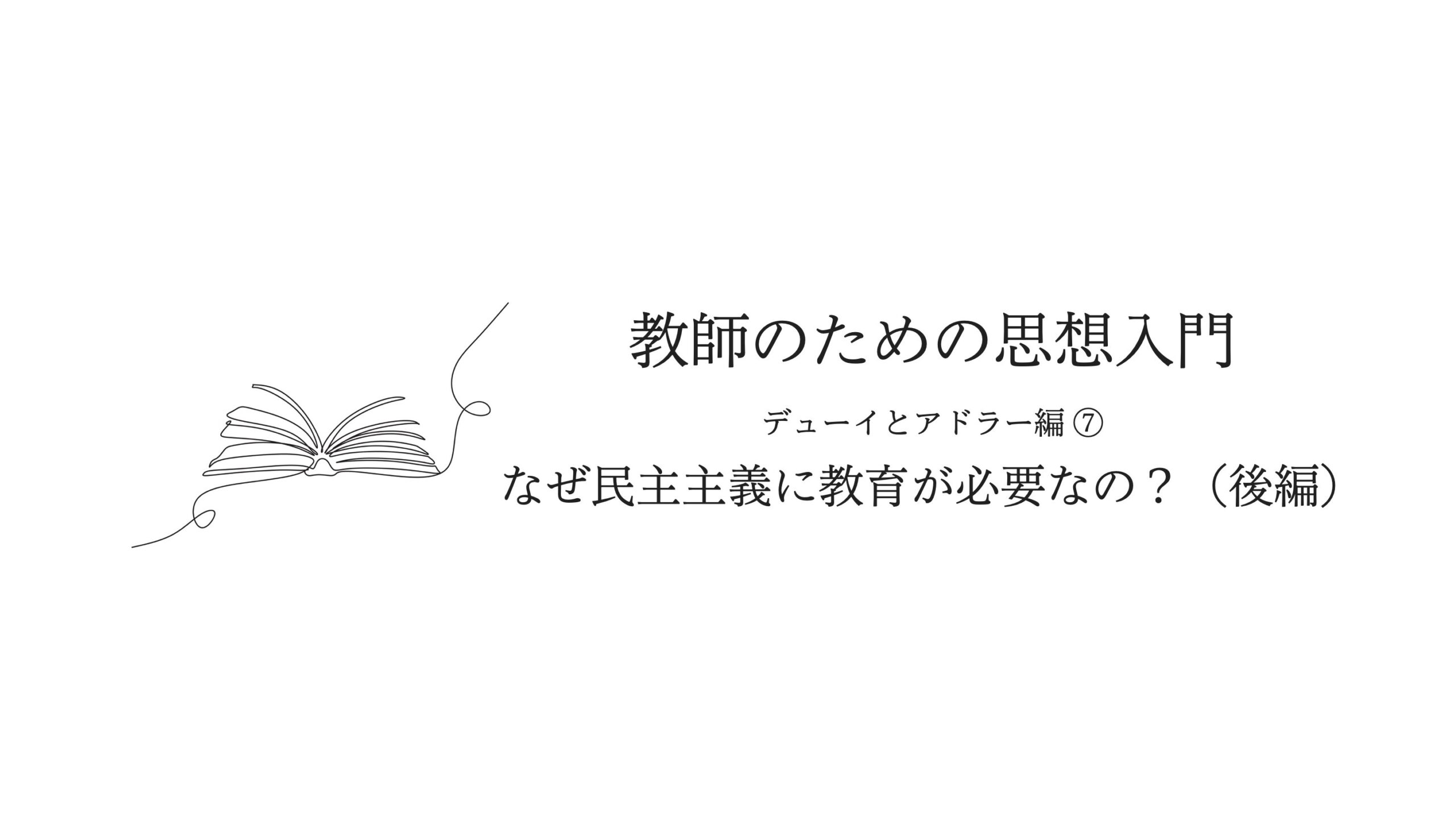▼ 前回の記事はこちら
デューイの教育論について語り合う中で、ことはは「民主主義を育む教育」への関心を深めていく。それは単なる知識の伝達ではなく、「生き方」の実践の場としての学校の姿だった…。
ことは:民主主義を育む学校って、どんな場所なんですか?
あつゆる:デューイによれば、学校は「小さな社会」になるべきだって考えたみたいだよ。
ことは:(少し困ったように)小さな社会…?でも、学校って基本的に勉強する場所ですよね。生徒も教師も、成績、成績って…。私なんか最近、「宿題忘れたの誰!?」って声、だんだん高くなってきちゃって…。
あつゆる:(微笑んで)ちょっと考えてみよう。教室で起きていること、本当に「勉強」だけ?
ことは:そうですね…。班活動とか、給食当番とか…。あ!この前、教室の机の配置を変えようって話になって。「コの字がいい」「分散がいい」って意見が分かれて。結局、一番後ろの山田くんが「季節で変えればいいじゃん」って言い出して…。
あつゆる:へぇ、それで?
ことは:みんな「おぉ!」って。私も「なんでそれに気づかなかったんだろう」って。いつも大人しい山田くんなのに…。
あつゆる:そういうの、デューイ先生も喜びそうだね。「学校そのものが、社会生活というものの意味するすべての点において、社会生活でなければならない」って言ってるから。
ことは:でも…それって単なる仲良しクラブじゃ…。
あつゆる:待って、その机の配置の話、もう少し聞かせて?
ことは:えっと、そうですね…。最初は「前向きが一番集中できる!」って譲らなかった生徒もいたんですけど、実は家で勉強する時はソファに寝転がってることを告白したり…。(笑)
あつゆる:それこそが民主主義の実践かもしれない。違う意見と出会って、時には自分の矛盾も見つけて、でも新しい可能性を見つけていく。
ことは:(少し考えて)でも、そういう経験って教室の中だけじゃ限界がありそうで…。
あつゆる:ところで、前に話した民主主義の2つの条件、覚えてる?
ことは:(パッと顔を上げて)はい!
- その集団の中で共有している関心がどれだけ多様か
- 他の集団とどれだけ自由にやりとりしているか
この2つですよね!
あつゆる:よく覚えてたね。
ことは:(嬉しそうに)実は、最近それを実感する出来事があって…。総合学習で地域の環境問題について調べ始めたんです。最初は「めんどくさい」って言ってた生徒が、地域の人にインタビューしたら、急に饒舌になって…。「先生、うちの町にこんなすごい人いたんですよ!」って。
あつゆる:それ、素敵な変化ね。塀の中の学校から、開かれた学校へ…。
ことは:(急に不安そうに)でも、そうやって社会性ばかり求めると、もともと持っている個性は失われていくのでは…?
あつゆる:面白いこと言うね。実はデューイは、まったく逆のことを考えていたみたい。学校が外に開かれて、いろんな刺激に触れるからこそ、個人は自分の殻を破れるって。
ことは:(少し黙って)…あ。さっきの山田くんみたいに?
あつゆる:そう。社会的な活動の中で、思わぬ個性が花開く。デューイ流に言えば、社会的目標に向かって次第に成長するうちに個人の能力を自由にしていく。
ことは:(ため息をつきながら)でも、現実は「将来のため」って言い過ぎかも…。テストのため、入試のため、就職のため…。私も「将来役立つから」って、つい言っちゃって。生徒の目が死んでるの分かってるのに…。
あつゆる:それってね、デューイがもっとも警戒していたこと。「教育の過程はそれ自体を越えるいかなる目的ももっていない」って言ってるの。
ことは:それって?
あつゆる:「将来のために今を犠牲にするな」ってこと。大切なのは「現在の経験をできるだけ豊かに」すること。
ことは:(急に思い出して)あ!この前の数学の授業で、教科書と違う解き方出てきて。私、一瞬「テストではこう書かないと」って言いかけたんですけど…。その子の考えを聞いてみたら、まさか証明の新しい方法が見つかるなんて。
あつゆる:クラスの反応は?
ことは:(嬉しそうに)最初は「何言ってんの?」って感じだった子たちも、だんだん「あ、確かに!」って。私も一緒に学んでる感じで…。その日の放課後、数学科の先生たちと「これ、面白いかも」って盛り上がっちゃって。
あつゆる:それこそがデューイの言う教育の本質かもしれない。「学習とか訓練とかいわれているものはみな、それ自体に価値がなければ教育的じゃない」って。
ことは:(目を輝かせて)分かった気がします…!最初、私「個」と「協働」って相反するものだと思ってたんです。でも、山田くんだって、環境問題を調べた生徒だって、数学の新しい解き方を見つけた子だって…。みんな、他の人と関わって、新しい刺激を受けて、そこで初めて自分の個性を発揮できた。
あつゆる:(静かにうなずいて)そう。だからこそデューイは、学校を閉ざされた箱にしちゃいけないって…。
ことは:(深く考え込んで)なるほど…。学校を「小さな社会」にしていく。いろんな関心、いろんな刺激を受け入れていく。そうすることで、一人一人の可能性が開かれていくんですね。
(目を輝かせて)あつゆるさん、私、少し見えてきた気がします。山田くんが思いがけないアイデアを出してくれた時も、生徒が地域の人との出会いで生き生きしてきた時も、教科書とは違う考え方から新しい発見が生まれた時も…。どれも、「個」と「協働」が出会う瞬間だったんですね。
▼続きはこちら