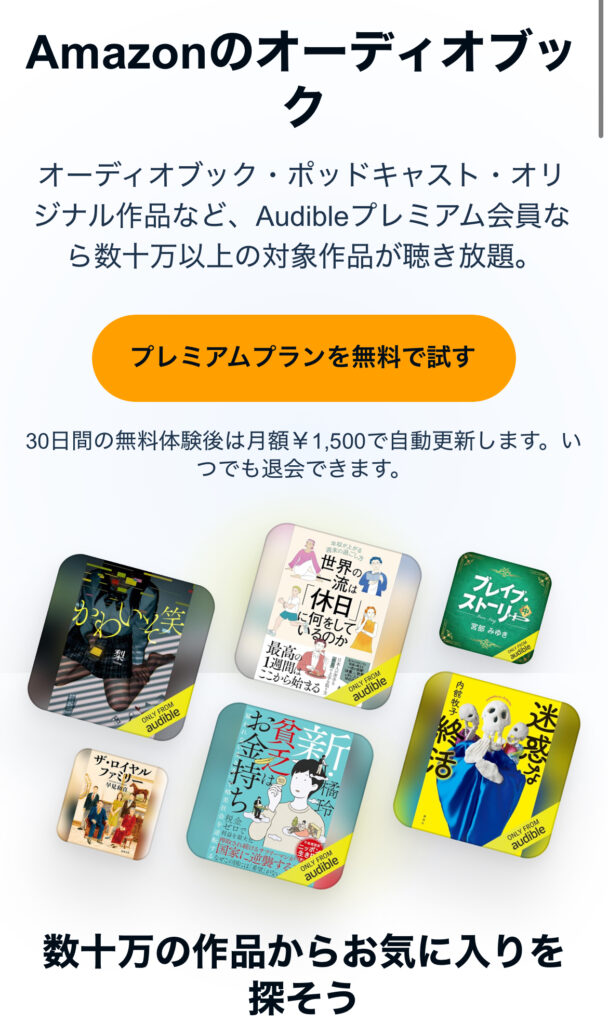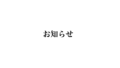前回、ブーバーの「出会い」について書いた。
意のままにならない異質な〈他者〉との出会いが、私たちの固定化された物語を根底から揺さぶるという話だった。
この記事では〈他者〉と出会った後のはなし、ブーバー哲学の「対話」について書く。
なお今回も、吉田敦彦『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』の第二章後半の議論をベースにする。
「対話?相手の話をきちんと聴いて会話するってことでしょ?そんなのやってるよ」
そう思う人もいるかもしれない。しかし、もしかしたらあなたが日常で「対話」だと思っていることは、ただの「独白」だとしたら?
手垢にまみれ、すり減らされた「対話」というコンセプトに、「ブーバーが心血を注いで授けた純然たる強い意味を救い出したい1」と、吉田は熱く語る。
この記事が、あなた自身の日々のコミュニケーションを振り返るきっかけになることを願って、心を込めて書いていきたい。
ブーバー対話論から、日々のコミュニケーションを見つめ直す。
私たちは対話しているつもりで、実は独白している
会話をしているようで、会話になっていない。そんな場面を見ることはないだろうか?
実家での食事の時間。家族の各々が好きなことを喋っているのに、お互い大して聞いてもいない。
SNS での議論を眺めていると、みんな熱心にやり取りしているように見えて、実際は自分の言いたいことを言っているだけ。
そんな様子を冷ややかに見てしまう瞬間が、一度ならずあったはずだ。
職場での会議も同じ。みんなが発言しているのに議論が深まらない。恋人や友人との話で、何時間話しても分かり合えた気がしない。
ここで、ふと思う。
「あれ、自分も同じことをしているのではないか?」
いや、間違いなくしてしまっている。
ブーバーは、この疑念に明確な答えを与える。私たちが「対話」だと思っているもののほとんどは、実は独白の交換に過ぎない、と。
一見対話しているように見えて、実はただ独白しているだけの者を、ブーバーは痛烈に「鏡の前の独白者」と呼んだ。
「何事かを伝えたいとか、聞き知りたいとか、誰かにはたらきかけたいとか、誰かと交わりを結びたいとか、そういった願望からではなくて、むしろ結局のところ、自分の話から相手が受けた印象を読み取ることによって、自信を裏づけたい、あるいはぐらついている自己を安定させたい、という欲求によってうながされている会話….」([1930a]:204)
『ブーバー対話論とホリスティック教育—他者・呼びかけ・応答』(吉田敦彦 著)p64
SNSでの議論、職場での会議、恋人との喧嘩、友人との飲み会。そこで本当に起きているのは何か。
- 相手が自分のことをどう思っているんだろう…
- ぐらついている自己を安定させたい…
結局のところ、関心があるのは相手ではなく、自分なのだ。相手に向かって語っているようで、実は自分自身に向かって語っている。
これは痛烈だ。でも、誰もがきっと思い当たる節があるのではないだろうか。
ため池の言葉、川の言葉
何が「独白」と「対話」を分けるのか?
ブーバー思想において、それは「〈他者〉に向かって出て行く」ことができるかどうかに懸かっている。
例えば、同じ価値観を持つ者たちが、互いに傾聴し、共感しあって、一見すてきな会話をしていたとする。
しかし、彼らが共通の物語の中をぐるぐる回り続けている限り、それはまだ「独白」にすぎない。
〈他者〉と出会い、沈黙する。自分の物語の外側に出る。それが「対話」のスタートとなる。
対話は、言葉を失う沈黙にあってその深みから湧いてくる言葉に耳をすませて待ち望み、それに応答するところから始まる。
その静寂の中で、私たちは物語の彼方から語りかけられる言葉を待つ。「ひたすらに待ち望む沈黙」の中で、新たな言葉が生成されるのを待つのである。
だが、そもそも「言葉」とは何なのか。
後期ブーバーは、この根本的な問いに答えるため、言葉を2つに分類した。
- 財としての言語
- 語られる言葉
吉田はこれら2つを、
「財としての言語」=「ため池の水」
「語られる言葉」=「川の水」
というメタファーを用いて解説する。
まずは「財としての言語=ため池の水」について。
よどんだ水をため込む貯水池。
確かに水はある。いつでも使える。便利で、安全で、枯渇することもない。
しかし、そこには新鮮さや生命力がない。
私たちが普段使っている既成の表現、決まり文句、テンプレート化された感情表現。
「お疲れ様です」「頑張って」「愛してる」
これらはすべて「ため池の言葉」だ。流れを止められ、蓄積され、固定化された言葉たち。
一方の「語られる言葉=川の水」とは何か。
それは「対話」において絶えず生成される言葉である。
「湧き出て延々と流れ続ける川」から、新鮮な言葉が汲み上げられる。
川の中に身を浸し、流れに身をゆだねることで、その都度新たに創造される言葉を受け取る。
深い会話の瞬間。問われてすぐには答えられず、しばらく沈黙した後、ふと浮かんでくる言葉。
「こんなことを考えていたんだ」と自分でも驚くような言葉が口から出てくる。
それは決して貯水池からではない。川から汲み上げられた、その瞬間生成された、生きた言葉なのである。
「語られる言葉」は「間の場」で生成される
対話において「語られる言葉」が湧き出てくる時、その言葉がどちらか一方から発せられたものだと、もはやブーバーは考えない。
対話の深みにおいては、話し手、聞き手という常識すら溶解する。
語られる言葉は、むしろ私が〈間 Zwischen〉と名付ける、個人と個人との間の波打ち振動する場に生起する
つまり、あなたが語るのでもなく、相手が語るのでもない。「間の場」そのものが語りかけているのだ。
深い会話で、自分でも予想しなかった言葉が口から出てくる。相手の一言で、まったく新しい視点が開ける。
気がつけば、1人では決して辿り着けなかった理解に到達しているあの瞬間。
「間」で何かが生成されている。 私たちは言葉を「発する」のではない。生成される言葉を「受け取り」、それを「贈る」のである。
吉田はブーバー思想を「2人ずつ主義」だと説明する。社会の最小単位は個人ではなく、「2人ずつ」でワンセットだという考え方だ。
この視点は、対話の深みにおいても見て取れる。つまり、個人が主体なのではなく、2人セットで初めて言葉が生成される。
そこにあるのは、予測不可能で創造的なプロセス。それが、ブーバーの描く対話の世界なのである。
出会い、対話、そして新たな物語へ
ブーバー思想における「対話」は〈他者〉との出会いから始まる。
自分の枠組みでは捉えきれない他者と向き合う時、私たちはまず沈黙する。そして、その深みから新たな言葉が生成される。
我と汝の「対話」において、2者の「間の場」で「語られる言葉」が生まれる。
さて、このブーバーの洞察は、私自身のカウンセリングを支える、1つの大事な思想となっている。
カウンセラー養成講座で学んだ、カウンセリングの3つの段階:
軽聴:カウンセラーが聞きたいことを聞く段階
傾聴:クライアントが語りたいことを語ってもらう段階
敬聴:カウンセラーとクライアントで何かを創り出す段階
この最後の段階「敬聴」こそ、ブーバーの言う「対話」であると理解している。
対話のあるカウンセリングは、まさに協働。
そこではクライアントだけでなく、カウンセラー自身もまた変化し、成長していく。
私自身、そんな深いカウンセリングを目指し、これからも研鑽を重ねていきたいと願う。
また、カウンセリングのみならず、「対話」とはつねに「教育的」である。
ブーバーの有名な言葉に「教育的な関係は純然たる対話的関係である」というのがあるが、対話とはすなわち既存の物語の破壊と、新たな物語の再構築なのだ。
その意味で、広い意味で「教育」に少しでも関心のある人—— 自分自身や他者の成長を少しでも願っている人であれば、ブーバーの言葉に耳を傾ける価値がある。
ただ、すでにお気づきかと思うが、ブーバーの道はなんというか…….実にヘビーだ。
語りかけられた言葉には、応答する責任があるとブーバーはたたみかける。
「間の場」で生まれる言葉は、私たちに応答を求めてくる。
その瞬間、選択が迫られる。貯水池にたまった既成の言葉で反応するのか、それとも川から湧き出る生きた言葉で応答するのか。
私たちは日々、この応答的責任と向き合っている。
家族との会話、職場での議論、友人との語らい。そこで語りかけられる言葉に、どう応答するか。
1つ1つの選択が、あなたの人生を形作っていく。