「運動、勉強、ダイエットetc. 継続しようとするけど続かない」
「何度もチャレンジしてきた“習慣化”にもう失敗したくない」
そんなあなたへ。数ある“習慣本”のなかでも「もうこの1冊だけでいいんじゃない?」と思える、習慣術のバイブルを紹介します。
- 書籍名:ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣(原題:ATOMIC HABITS: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad One)
- 著者:ジェームズ・クリアー
- 出版社 : パンローリング 株式会社
- 発売日 : 2019/10/12
- 単行本(ソフトカバー) : 328ページ
ニューヨークタイムズのNo.1ベストセラー。 本国で400万部突破!
Amazon内容紹介より、一部抜粋
日々の小さな変更が、驚異の結果をもたらす。
本書は学術研究論文ではなく、実践マニュアルである。
その根幹をなすものは、習慣の4つのステップ――きっかけ、欲求、反応、報酬――と、このステップから生まれる4つの行動変化の法則である。わたしが提案する枠組みは、認知科学と行動科学の統合モデルである。
良い習慣を身につけるのに唯一の方法などないが、著者の知っている最善の方法を紹介する。どこから始めても、変えたいものがなんであろうと効果のある方法である。
ここで取りあげる戦略は、目標が健康、お金、生産性、人間関係、もしくはその全部でも、段階的な方法を求めている人なら、誰にでも合うはずだ。人間の行動に関するかぎり、本書はあなたのよきガイドとなるだろう。
オーディブルは30日間無料で体験できます。オーディブルで、あなたの日常に刺激とインスピレーションを。
\『複利で伸びる1つの習慣』も“聴き放題”/
【書評】『複利で伸びる1つの習慣』要約・まとめ・感想・口コミ
【書を読む】要約・ポイント
本のなかで印象に残った箇所を5つ引用します。難しいと感じる人は、要約・ポイントだけでもお読みいただき、本書のアイデアにぜひ触れてみてください。
1. 徹底的な仕組み化によって、最小習慣を積み上げよ
もし習慣を変えるのに苦労しているなら、あなたに問題があるのではない。問題があるのは仕組みである。悪い習慣が勝手に何度も繰りかえすのは、あなたが変えたくないからではなく、変えるための仕組みが間違っているからだ。目標ばかり追っていてはいけない。仕組みから取りかかろう。〔…〕
習慣は生活の原子のようなものだ。ひとつひとつがあなたの改善全体に貢献する基本単位となっている。はじめのうちは、その小さな繰りかえしは取るに足らないように見えるが、やがて互いに組み合わさって、最初の苦労をはるかに上回るほど大きくなった勝利を引き起こす。それらは小さくて強力だ。「最小習慣」という言葉の意味は − 小さくて行いやすいだけでなく、信じられないような力の源でもある日常的な練習やルーティンであり、複利的に成長する仕組みの構成要素である。
『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』p38~39
2. すべての習慣は、必ず4つのプロセスを踏む→各プロセスを制御すれば、習慣は自在にコントロールできる
習慣形成のプロセスは、シンプルな4つのステップに分けることができる ー きっかけ、欲求、反応、報酬である。
『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』p62
このように基本的な要素に分解することで、習慣が何であり、どのように働き、どう改善すればいいか理解しやすくなる。この4つのステップのパターンは、あらゆる習慣の根幹であり、脳は毎回同じ順番でこのステップを踏んでいく。
3. 〈いつ〉〈どこで〉〈何を〉するのかをはっきりさせれば、習慣はほぼ自動化が可能
あなたの習慣に、この世界で生きる時間と場所を与えよう。目標は、時間と場所を明確にして何度も繰りかえすことによって、ふさわしいときに、理由もなくふさわしい行動したくなることだ。 作家のジェイソン・ツヴァイクはこう語っている。「たしかに、意識せずに運動するようなことはない。しかし、ベルの音を聞いてよだれをたらす犬のように、いつもの運動の時間が近づいたら、そわそわする事はあるだろう」
『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』p88
4. 自制心や意志を当てにするな、環境を作りこめ
非常に自制心がありそうな人々を分析すると、そのひとりひとりは、自制できずに苦しんでいる人と大して違いがないことがわかった。そのかわり、「自制心のある」人は、たいそうな意志や自制心がいらないように、生活を設計することに長けていた。いいかえれば、誘惑的な状況には、なるべく身をおかないということだ。
もっとも自制心のある人は、たいていもっとも自制心を使わない人だ。自制心は、あまり使わなくていいときに練習しやすい。そう、たしかに、忍耐力や根性や意志の力は成功するのに不可欠だ。だが、こういう資質を向上させる方法は、もっと自制心のある人間になりたいと願うことではなく、規律正しい環境を作ることである。
『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』p112-113
5. 習慣は最初の2分間で決まる!身につけたい習慣の入り口のハードルはとにかく下げよ
小さく始めるべきだとわかっていても、つい大きく始めてしまいやすいものだ。変わりたいと夢見ているときは、どうしても興奮が抑えられず、多すぎることを早すぎる時期にしたくなる。こういう性向を和らげるのにもっとも効果的な方法は、「2分間ルール」を使うことである。これは、「新しい習慣を始めるときは、2分以内にできるものにする」というルールだ。
ほぼどんな習慣でも、2分間バージョンに縮小できる。
・「毎晩寝るまえに読書する」は「1ページ読む」に
・「ヨガを30分する」は「ヨガマットを取り出す」に 〔…〕
・「5キロ走る」は「ランニングシューズの靴ひもを結ぶ」にこれは、習慣をできるだけ始めやすくするためのアイデアだ。1分間の瞑想や、1ページの読書、1足の靴下をたたむことなら誰にでもできる。 そしてすでに述べたように、これは強力な戦術だ。いったん正しいことを始めたら、とても続けやすくなるからだ。 新しい習慣が試練のように感じられるようではいけない。あとに続く行動はたいへんかもしれないが、最初の2分間は易しいものであるべきだ。 あなたに必要なのは、もっと生産的な道へと導いてくれる「入り口の習慣」である。
『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』p185-186
【思考する】書評・感想
これまで読んだ自己啓発本のなかで5本の指に入る“名著”
近年稀に見る名著。これまで読んだ自己啓発本のなかでは、間違いなく5本の指に入ります。
私はこれまで「目標をくりかえしノートに書くだけで夢が叶う」とか「目標から逆算して計画を立てよう」みたいな本も読んでみましたが「やってみたけどイマイチ効果が感じられない」「計画を立てるのがそもそもムリ!!」となりがちでした。
しかし、この本はそういうありがちな習慣術・目標達成本とは一線を画します。なんなら「目標や意志、モチベーションに頼るのはもうやめません?」と言っているくらい。
本質的で、科学的で、合理的で、実践的で、しかも簡単。タバコや暴飲暴食など悪習慣を断ちたい人、運動や勉強など良習慣を身につけたい人、勉強がなかなか習慣化できないお子さんを持つ親などにも全力でオススメしたい1冊です。
モチベーションを上げなくていいんだと気づけたとき、心がすごくスッキリした
第1章は「最小習慣」「複利で伸びるとは」などの総論ですが、個人的に目からウロコだったのは「目標を忘れて、仕組みに集中しよう1」というメッセージ。この本にのっている習慣術は、目標も、モチベーションも、意志もいらないというんです。
じゃあその代わりに何をしろというかというと、徹底的な仕組み化です。たとえば第5章にのっている「習慣の積み上げ」。これは、あなたがすでにやっている習慣に、“身につけたい習慣を+α”するもの。コーヒーを淹れることがすでに習慣化されていて、スクワットの習慣を身につけたいなら「コーヒー淹れるタイミングで10回スクワットする」というルールを作る感じ。
日常の中にマイルールを散りばめ、積み上げていく。規律ある環境を整えていく。そこに意志がまったくいらないというのは言い過ぎかもしれませんが「よっしゃやったるで!」と毎日モチベーションを高める必要は皆無です。
「うまくいかないのであれば、仕組みを見直せばOK」「モチベーションを上げないと!と焦る必要なし」「自分はなんて意志が弱いんだ!と自己嫌悪に陥らなくていい」そんなことに気づけたとき、心がすごくスッキリしました。
自分がいかに無意識の反応に踊らされているかに気づかされた
この本は、第3章で紹介される「きっかけ→欲求→反応→報酬」という“習慣形成の4ステップ”が理論的なバックボーンとなり、その後の論が展開されていきます。これはつまりどういう話かというと、私たちの行動は気づいてないだろうけど自動化されまくってるよということ。

冷蔵庫のビールが目に入る(きっかけ)→ビールが飲みたい(欲求)→ビールを飲む(反応)→うまい!!(報酬)
はい。こういう駄目パターン、みなさんもありますよね?(私はすごくあります)こうした無意識に埋もれている習慣のステップを意識化して、各ステップで制御していきましょう!そしたら習慣を身につけるのも止めるのもやりやすくなるよ!というのがこの本で言っていること。すごく納得感がありませんか?
このあたりの論は『反応しない練習』とも通じます。「人間はこれまでの経験から、反応が自動化されている。今まで無意識にやっていた反応をやめればもっと生きるのが楽になるよ」というのがこの本のポイント。“心の自動的な反応”って、つくづく本質的なテーマだと改めて実感しました。
ハードルは低く、楽しく、その代わり毎日続けようと思った
習慣化においてありがちなのが「1日3時間勉強する」「毎日10kmランニングする」みたいに、デカい目標を掲げるものの、あえなく三日坊主になることですよね。
この本には「2分間ルール」「易しくする」「即時報酬を用いる」など、いろんな仕組み化のアイデアが提案されているわけですが、とにかく「ハードルは低く、楽しく」やること(その代わり、必ず毎日続けること)。それが、まず何より大事なのだとわかりました。
そして、この本に書かれている原則を1つ1つ当てはめていったとき、リングフィットアドベンチャーってすげぇ!!と、気づきました。
リングフィットアドベンチャーは、ゲームをクリアしながら、楽しくエクササイズできる任天堂の人気ソフト。
- 外に行かず、家で手軽にできる
- アイテムを手に入れたり、レベルアップしたりと即時報酬がある
- キツすぎず、ラクすぎない適度な負荷がかけられる
- 毎日の努力が記録される
- 家族と一緒にやれる、応援してもらえる
など、リングフィットアドベンチャーがいかに習慣化の理に適っているか、この本を読めば理解していただけるはず。ちなみに今まで運動習慣が定着しなかった私自身も、リングフィットアドベンチャーだけは毎日続けられています。
「〇〇がうまくいかないんですよ…」という悩みに対して「がんばれ!自分に負けるな!」とモチベーションを上げてくれるのがよくある自己啓発本だとしたら、この本は「え?それはこう仕組み化すればいいだけじゃん」みたいにスマートなアイデアをくれる本。
目次を見てもらえればわかりますが、とにかく情報量も大事なポイントも多い1冊です。私自身、また行き詰まったとき、アイデアをもらいにくり返し読みたいと思います。
まとめ
意志や根性論にたよらない、超合理的な習慣術。
ほかにも習慣術の本はいろいろ目を通していますが、これを超えてくる本にはなかなか出会いません。今日が人生で一番若い日。この記事を読んで「今度の今度こそ、絶対に習慣化に成功して人生を変えてやる!」と思われた方は、本書を手に取ってみられることをオススメします。
基本 ~なぜ小さな変化が大きな違いをもたらすのか
第1章 最小習慣の驚くべき力
第2章 習慣がアイデンティティーを形成する(逆もまた真なり)
第3章 シンプルな四つのステップで良い習慣を身につける第一の法則 ~はっきりさせる
第4章 人は正しく見ていない
第5章 新しい習慣を始める最善の方法
第6章 モチベーションを過大評価せず、環境を重視する
第7章 自制心を保つコツ第二の法則 ~魅力的にする
第8章 習慣を魅力的にする方法
第9章 習慣作りにおける家族と友人の役割
第10章 悪い習慣を見つけて直す方法第三の法則 ~易しくする
第11章 ゆっくり歩もう、でも後退してはいけない
第12章 最少努力の法則
第13章 二分間ルールで先延ばしをやめる方法
第14章 良い習慣を必然にし、悪い習慣を不可能にする方法第四の法則 ~満足できるものにする
第15章 行動変化の大原則
第16章 良い習慣を毎日続ける方法
第17章 見張ってくれる人がいればすべてが変わるさらなる戦略 ~改善するだけでなく、本物になるには
第18章 才能の真実(遺伝子が関係するときと、そうでないとき)
第19章 ゴルディロックスの原理――生活や仕事でモチベーションを保つ方法
第20章 良い習慣のマイナス面
結論
『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣』は“聴く読書”Audible(オーディブル)の無料体験で聴き放題。聴き放題には『新版「続ける」技術』、『超習慣術』など習慣についての本もたくさんあります。
オーディブルは30日間無料で体験できます。オーディブルで、あなたの日常に刺激とインスピレーションを。
\『複利で伸びる1つの習慣』も“聴き放題”/

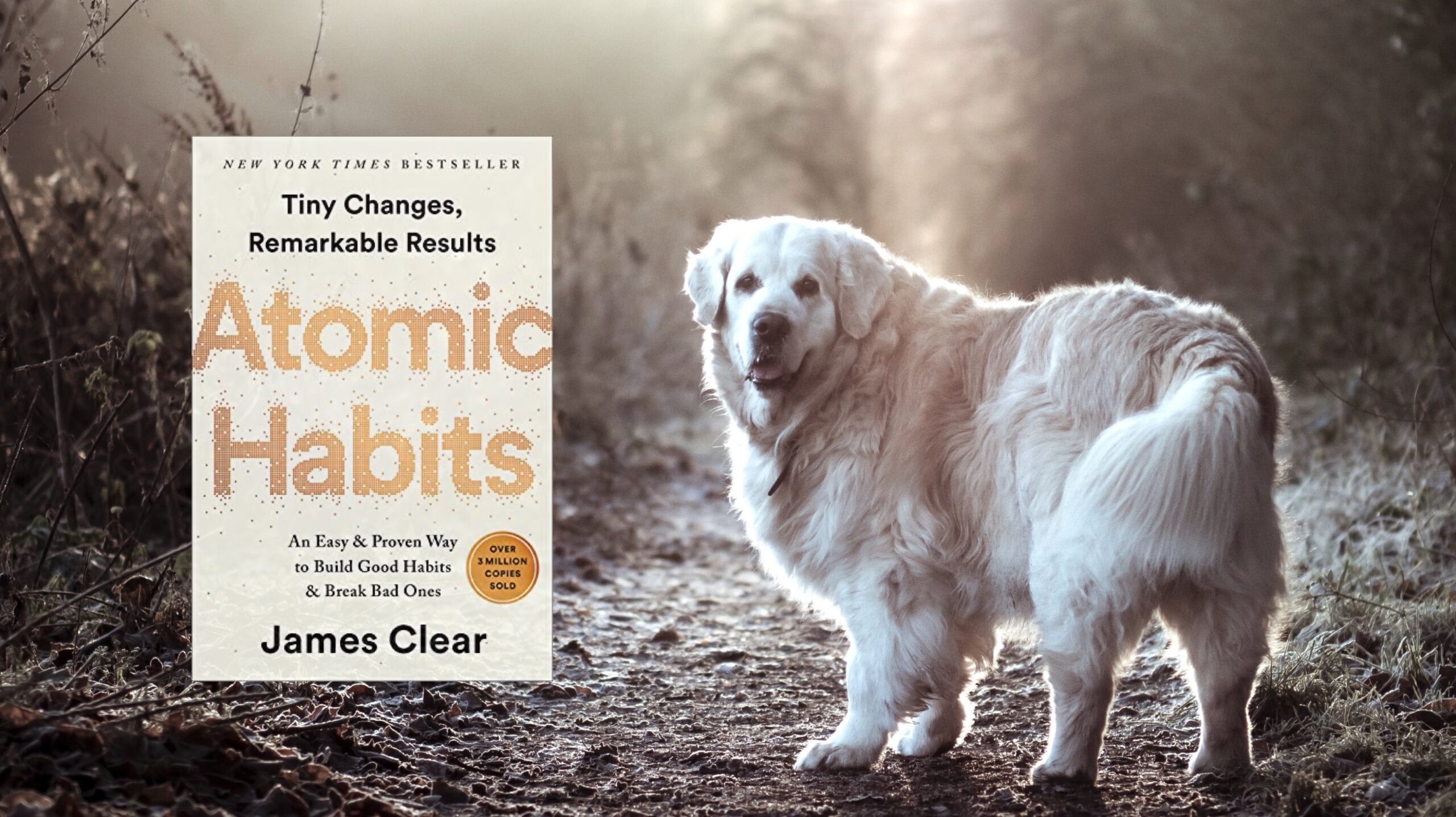

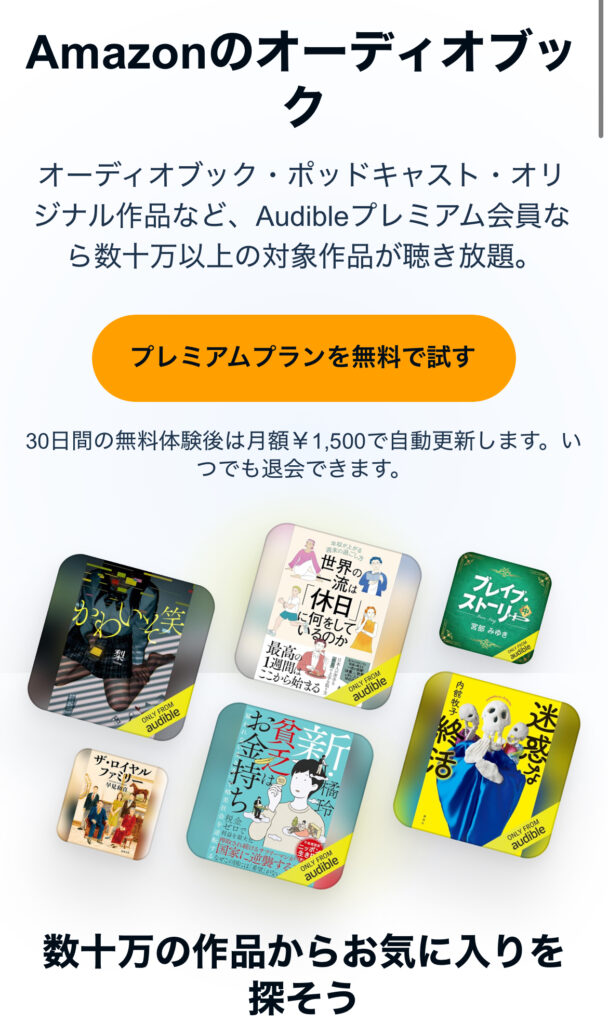
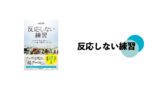


-120x68.jpg)