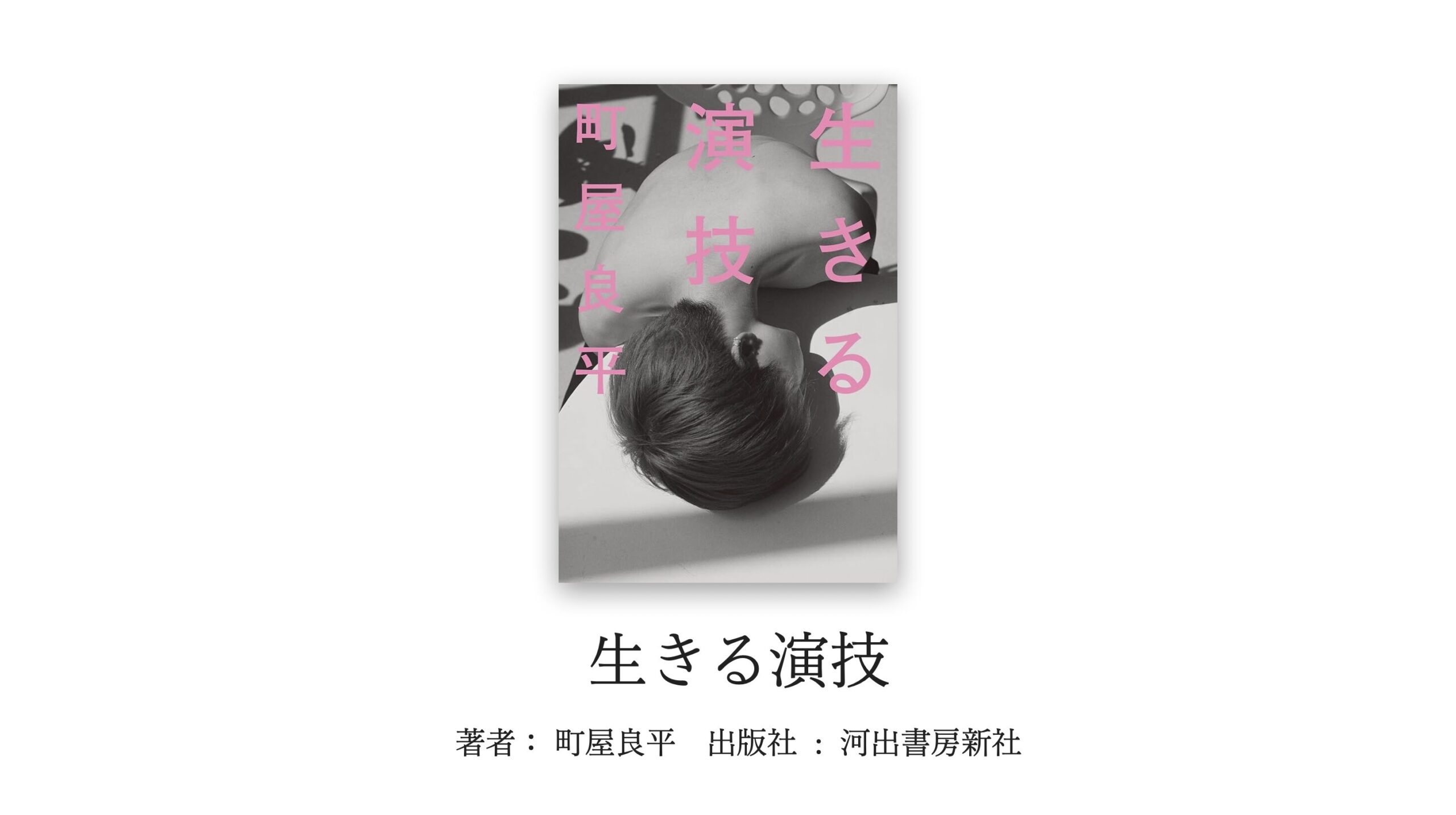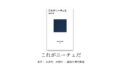「暗闇の解像度を上げると光った。かれは午前四時の公園にいる。あたりは暗く、視覚だけでは捉えきれない場を感じる。景色が五感に混ざっていく。土の匂いや風の音で風景をかきわけ、さわる樹皮の感覚で補う視界はまるく、重々しい塊のような世界が迫ってくる。」
冒頭の一節を読んだ瞬間、「すごいものを読まされるのだ」と直感した。
視覚、聴覚、触覚、嗅覚が混ざり合い、読者の知覚そのものが揺さぶられていく。それは単なる情景描写を超えて、この小説全体を貫く特異な体験の予告であった。
『生きる演技』(町屋良平著・河出書房新社)は、2024年もっとも印象的だった1冊。
重層的な物語構造
本作は、高校生の演劇部の物語を軸に展開する小説である。一見すると、これは文化祭の演劇準備を通じて友情を育んでいく青春小説に見える。
物語の中心にいるのは、2人の男子高校生だ。母親の自死という傷を抱えた元子役の生崎陽と、両親の逮捕歴という影を背負う「炎上系」俳優の笹岡樹。
彼らは文化祭で上演する、戦時中の暴力をテーマにした演劇の準備を通じて、特別な絆を育んでいく。
しかし、これが “普通の” 青春小説でないことは、すぐに明らかになる。五感をフルに使った表現が独特で、「かれ」と「われわれ」を行き来する視点の揺らぎに戸惑い、圧倒される。
だが、その独特のリズムに身を委ねていくうちに、不思議とページは進んでいく。
読み進めるうちに、この作品の重層的な構造が見えてくる。
表層には高校生活や文化祭準備、友情の発展という親しみやすい物語が広がる。
その下には、「演技」と「素」の境界、個人と集団の関係、現在と過去の接続など、複雑な哲学的テーマが潜んでいる。
「青春小説」という親しみやすい形式を「容器」として、その中に深い思索を注ぎ込んでいく―この手法は作者の周到な戦略なのだろう。
初読時、私は「なんだか深いことを考えさせられる」という漠然とした印象を抱いただけで、その本質は十分に理解できなかった。
今回、年末年始の時間をかけて再読した。「中間」「幽霊」「恥」などのキーワードを軸に、この作品が私たちに投げかける問いについて考えてみたい。
演技と存在の中間性
この作品の最大の特徴は、私たちの日常に満ちている「微妙なもの」を鮮やかに言語化する試みにある。
身体感覚、意識の揺らぎ、人々のコミュニケーション―すべてが曖昧で捉えがたい。しかし、その曖昧さこそが、現代を生きる私たちの実感に深く響いてくる。
この曖昧さは、2人の主人公の対照的な在り方を通して具体的に描かれていく。生崎は人との直接的な関係を避け、場所や環境との交感を重視する。
一方の笹岡は、自己を過剰なまでに晒すことで関係を求めていく。自分の傷をさらけ出し、それを見る他者の視線を通じて、逆説的に自己の存在を確かめようとする。
リストカットが痛みを通じて存在を確認するように、笹岡は自分を傷つけることで、かえって自己を実感しようとする。
しかしそれは単なる自傷行為ではなく、他者とつながりたいという願望と、自己を確かめたいという欲求が複雑に絡み合った表現なのだ。
演技者である2人が見出すのは、「演技」と「素」という区別自体が意味を持たない地点だ。
「カメラが回れば役にはなれる。しかしカットがかかったときに中途半端に戻れる人格がある、戻る先があるから安心して遠くへ行き、遥かの感情に繋がれる」という生崎の言葉は示唆的だ。
この「戻る先がある」という感覚は、演技を通じて自己を拡張していく可能性を示している。
完全な「役」でも完全な「素」でもない、その中間にこそ、新しい存在の可能性が開かれているのだ。
私たちは日々、こうした微妙な駆け引きの中で生きている:
- 本当の気持ちを率直に話しているはずなのに、それ自体が防衛となる
- 正直であることを演技として使い、本当の自分を隠す
- 「素」であろうとすることが、最も巧妙な演技となる
SNSでの投稿、職場での振る舞い、友人との関係―そのどれもが、完全な「素」でも完全な「演技」でもない曖昧な領域で展開される。
この曖昧さは、現代社会を生きる私たちの宿命であり、同時に可能性でもある。
幽霊と恥の感覚
この「中間的な存在」は、作品の中で「幽霊」という形象と「恥」という感覚によって表現される。
「だれしも目の前の相手の幽霊役をやってあげる。それがうまくいったときだけ生者同士は仲良くなる」
この一節は、現代における他者理解の本質を表す。
私たちは日常的に誰かの「幽霊役」を演じているのかもしれない。
友人の悩みに寄り添うとき、恋人の気持ちを理解しようとするとき、家族の言葉にならない思いを受け止めようとするとき―そこでは常に、相手の感情や経験を「演じる」ように想像し、自分の中に取り込もうとする。
それは表面的な共感を超えて、相手の中の見えない部分を受け入れようとする瞬間だ。
この存在の仕方は、同時に深い「恥」の感覚とも結びつく。「おれは生きていてずっと恥ずかしいんだな」という笹岡の言葉は、特定の出来事に対する羞恥心ではない。
それは存在そのものから生まれる感覚であり、私たちの中にある「自分であって自分でないもの」との出会いがもたらす違和感だ。
職場や学校で「空気を読む」ことを強いられ、家族や友人との関係で「期待される役割」を演じる―そんな現代人の存在の仕方そのものが、「恥」として表現されているのだ。
意識の重層性と場との共振
作品が描き出す「微妙なもの」は、意識の領域にも及んでいく。
「演じるときになる身体みたいに、この場にボけていく、風景に、歴史に、この教室の温度や質感に、この身が引いていく」
この描写は、単なる演技でも現実でもない、その境界が溶解していく瞬間を捉えている。
意識は複数の層を持ち始め、それらは互いに浸透し合う。観客でありながら演者であり、現在にいながら過去を生きる―そんな多層的な存在の形が浮かび上がってくる。
生崎と笹岡は、場所の持つ記憶や気配を、言葉による理解を超えて、身体的に受け止めていく。それは定着することのない、流動的な自己のあり方。
この重層的な意識は、時として予期せぬ形で暴力性とも共振していく。彼らが文化祭で上演しようとする演劇は、戦時中の暴力をテーマにしたものだ。
そこで彼らは、様々な暴力と共鳴していく:
- 学校という空間に潜む暴力性
- 家庭が抱え込んだ闇
- 日常の底に沈殿する「悪」
これらの暴力は、決して過去のものではない。むしろ、現代の日常に潜在する暴力と歴史的な暴力が、演技という行為を通じて不可分に接続されていく。
意識の重層性は、時間さえも超えて、現在と過去を結びつける。そこには私たちの社会に潜む暴力性の連続が、不気味な形で浮かび上がってくるのだ。
そしてこの暴力の連鎖は、2人の演技者の身体を通じて、現代の私たちの日常へと接続されていく。
おわりに
『生きる演技』は簡単な作品ではない。視点は揺れ動き、誰の声なのかも曖昧になり、時に読者を戸惑わせる。
しかし、この「難解さ」は決して自己目的的ではない。むしろ、現代を生きる私たちの存在の複雑さそのものを映し出すために選ばれた表現なのだと思う。
特筆すべきは、この作品が読者の知覚体験そのものを揺さぶる力を持っている点だ。
単に「理解する」のではなく、身体的な次元で作品と共振するような読書体験を提供している。
それは私たちが日常的に経験している「演技」と「素」の境界の曖昧さ、他者との関係性における「幽霊」のような存在のあり方、そして「恥」という実存的な感覚を、より深いレベルで体感させてくれる。
だが、一度の読書ですべてを理解しようとする必要はない。まずは文化祭に向かって奮闘する2人の高校生の物語として読んでみてほしい。
そして読み返すたびに、少しずつ自分に引きつけながら読めることだろう。この物語は、「今この国の空気」を生きるすべての人へと問いかけている。