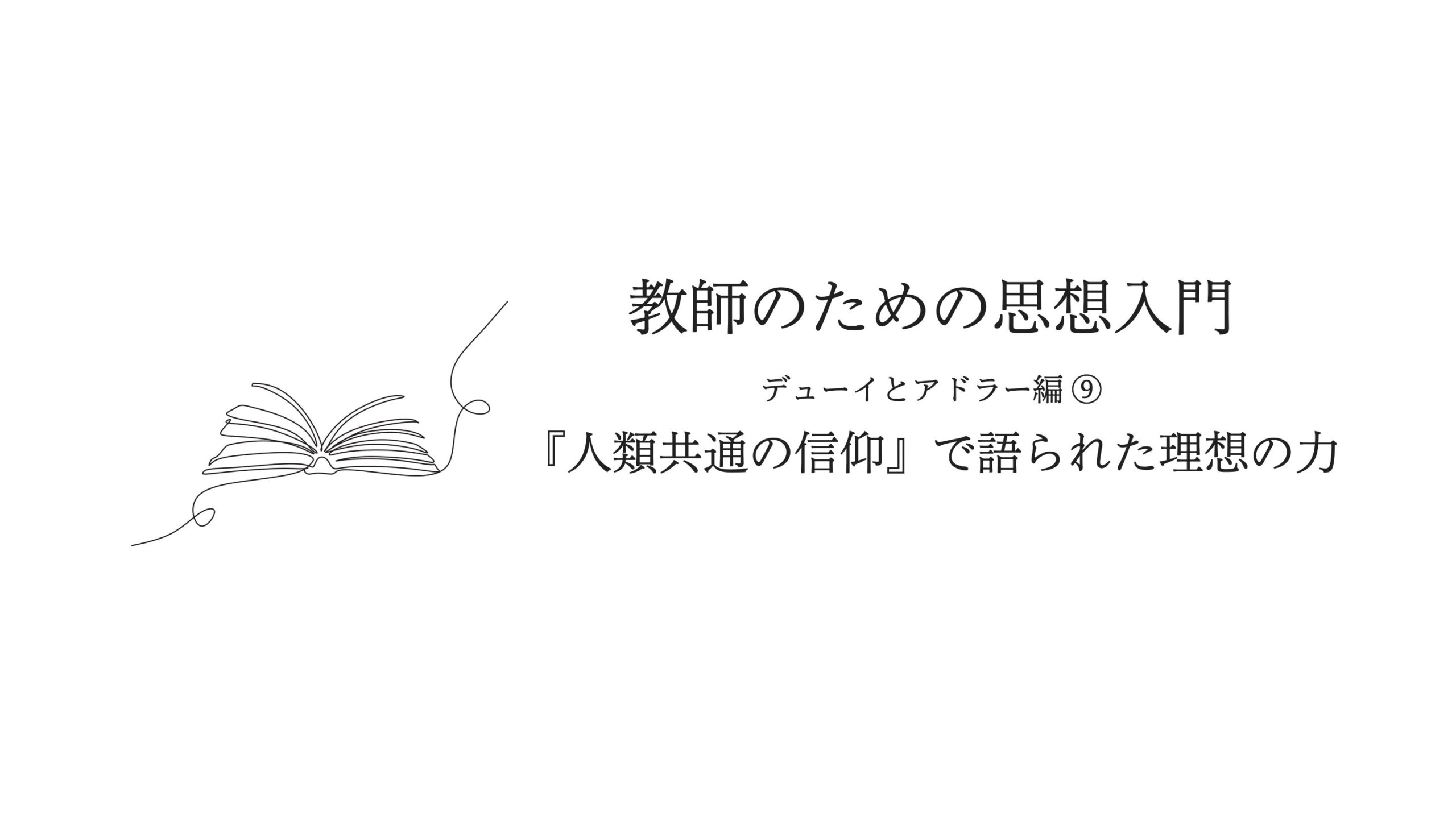理想とコミュニティの関係について語り合う中で、「理想には不思議なパワーがある」というデューイの考えに興味を抱いたことは。理想とは単なる観念ではなく、人間の行動を動かす力を持つという。その力とは一体どのようなものなのか…。
ことは:
(身を乗り出して)理想のもつパワーについて、もっと教えてほしいです!
あつゆる:
そうだね。ちょうどいい本があるんだ。(立ち上がって本棚に向かう)
ことは:
どんな本ですか?
あつゆる:
(1冊の本を取り出しながら)デューイが1934年に書いた『人類共通の信仰』という本なんだ。彼の唯一の宗教論なんだよ。
ことは:
信仰?宗教論?デューイって宗教家だったんですか?
あつゆる:
いや、そういうわけではなくって、デューイは形式的で固定的な宗教から「宗教的な性質」を解放しようとしたんだよ。
ことは:
(首をかしげて)宗教と宗教的な性質って、違うんですか?
あつゆる:
そう。デューイにとって「宗教」というのは、制度化された形式的なものなんだ。
一方「宗教的な性質」は人間経験の中にある本質的なもの。彼はこの「宗教的な性質」を「感情に彩られた道徳性」と呼んでいるんだ。
宗教(religion):制度化された形式的な宗教
宗教的な性質(the religious):目的や理想に向かって行動へと駆り立てる、強烈な感情を引き起こす宗教的なパワー
ことは:
感情に彩られた道徳性…?(考え込んで)単なる「こうあるべき」という頭での理解じゃなくて、心が動くような…。
あつゆる:
その通り!デューイはその感情について、「ただ単に強烈であるだけでなく、自我を統一する、きわめて包括的な目的によって発動され、支えられている」って言ってるんだ。
ことは:
自我を統一する、きわめて包括的な目的….。(ハッとして)あ!今年の合唱コンクールで体験したことに似てるかも…。
あつゆる:
おー、どんなふうに?
ことは:
最初はみんな「賞を取りたい」という動機だったんです。でも練習を重ねるうちに、だんだん「本当にいい歌を歌いたい」という思いに変わって…。
そしたら不思議と、いつも音程が外れていた子が急に集中し始めたり、引っ込み思案だった子がソロパートに挑戦したり…。(目を輝かせて)みんなの気持ちが1つになった瞬間があって、鳥肌が立ちました。
あつゆる:
素敵な瞬間だね。それこそがデューイの言う「理想のパワー」なんだ。彼はそこに「われわれの運命を支配する目には見えない力」があると言っているんだよ。
ことは:
目には見えない力…。
あつゆる:
そう。デューイによれば、それは「イマジネーション」という内的な機関によって感知されるんだって。
ことは:
イマジネーション?単なる空想のことですか?
あつゆる:
(頭を横に振って)そうじゃないんだ。デューイの言うイマジネーションとは、「現実にはまだ実現されていない事柄が、我々の心にとどき、我々を行動に駆り立てる力をもつということ」なんだ。
ことは:
(目を輝かせて)あ!「こんな音楽を創れたら素敵だな」という思いが、実際にみんなを動かしていったような…?
あつゆる:
その通り!デューイは「理想は、イマジネーションが、思考と行為とに提示された可能性をしっかりとらえ、現実を理想化するとき、現れる」って言っている。
つまりね、私たちの心が「今はまだないけど、こうなれたら素晴らしい」という可能性を明確に感じ取った時、理想が生まれるんだよ。
合唱コンクールでいえば、今の歌声と「理想の歌声」のギャップを感じつつも、その「理想の歌声」がはっきりとイメージできた瞬間に、本物の理想が生まれたということかな。
ことは:
あ!だから子どもたちも変わっていったんですね。ただの「勝ちたい」という願望じゃなくて、「こんな音楽を実現したい」という明確なイメージが共有できたから…。
あつゆる:
そういうことだね。理想は単なる願望とは違うんだ。現実を見つめた上で、その先にある可能性をはっきりと描き出したものなんだよ。
ことは:
(少し迷いながら)でも、イマジネーションって、現実とかけ離れた夢想みたいなものに陥る危険もありませんか?
あつゆる:
いい質問だね。デューイは、理想は「空想的な素材からつくられる超越的な何か」ではないと言っているんだ。それは「自然と社会においてなされる人間経験の世界がもつ確固とした素材からつくりだされる」もの。
ことは:
つまり、現実が基盤にあるんですね。
あつゆる:
そう。例えば、歴史上の偉人たちの話を聞いてみたい?
ことは:
(興味深そうに)はい!
あつゆる:
ナイチンゲールって知ってるよね?
ことは:
もちろん。近代看護学の母と言われる人ですよね。
あつゆる:
そう。彼女はクリミア戦争で負傷した兵士たちの悲惨な状況を目の当たりにしたんだ。そこから彼女の中に「より良い看護のあり方」という理想が生まれて、それが彼女を行動へと駆り立てた。
ことは:
現実の苦しみから理想が生まれて、その理想が彼女を動かした…。
あつゆる:
もう1人、ウィルバーフォースという人物もいる。彼は奴隷貿易の実態を知り、その廃止のために一生を捧げたんだ。
ことは:
(少し考えて)最近読んだ本にも、似たような話がありました。難民キャンプでボランティアとして働いていた普通の大学生が、その経験から国際支援の仕組みを変える活動を始めて…。
あつゆる:
まさにそれ!現実の問題から、「こうあるべき」という理想が生まれ、それが人を行動へと駆り立てるんだ。
ことは:
あ!私自身も、教師になったのは、自分が中学生の時の担任の先生に憧れて…。でも最初は「私にはできない」って思ってたんです。でも、その理想があるから、今でも頑張れている気がします。
あつゆる:
(温かく)そうだよ。デューイは理想について、それは「人々に強烈な感情を引き起こし、行動に駆り立てる力をもつ」と言っている。
それは「芸術家も、科学者も、市民も、子をもつ親も、誰であっても、彼らが自分に課せられた使命(callings)の精神によって動かされているかぎりは」同じなんだって。
ことは:
使命…。確かに、理想に導かれるとき、何か大きな使命を感じることがありますね。あつゆるさん、でもそういう強い力って、どこか宗教的な感じがしませんか?
あつゆる:
(うなずきながら)デューイはまさにそこに注目したんだ。理想が持つ強烈なパワーは、確かに宗教的な体験に似ている。だからこそ彼は、制度としての宗教ではなく、人間経験の「宗教的な性質」に注目したんだよ。
ことは:
(理解が深まるように)なるほど…。だから『人類共通の信仰』という宗教論になったんですね。理想のパワーが、人を超えたものに導くような…。
あつゆる:
その通り。デューイは理想のパワーこそが、真の意味での宗教的な経験の核心だと考えたんだ。それは特定の宗教を信じるということじゃなく、理想に導かれて全身全霊をかけて取り組むという経験そのものなんだよ。
ことは:
(感慨深く)理想って、単なる頭の中の思いじゃなくて、私たちの行動を実際に動かしていく力を持ってるんですね…。
あつゆる:
そう。そして、「理想のもつ見えない力によって支配された人々の献身的努力によって」、その理想は「晴れて現実のもの」になっていくんだ。
ことは:
前回、理想はコミュニティの中で生まれると教えてもらいました。そして今、理想には人を動かすパワーがあることも分かりました。理想って人それぞれ違っていて、多様であることも大切なんですよね?
あつゆる:
そうだよ。デューイは多様な理想があることを肯定しているんだ。
ことは:
(急に目を見開いて)あ!でも待ってください。理想が多様だとして…例えば、ある人は「世界平和」を理想としていて、別の人は「力による支配」を理想にしていたら…。
そういう場合でも「多様性」として認めるべきなんでしょうか?理想がバラバラの方向を向いていたら、社会はどうなるんでしょう?
あつゆる:
鋭い質問だね。実はデューイは、多様な理想が単に共存するだけではなく、それらが収斂していく共通の方向性があると考えていたんだ。彼はそれを「すべての理想的目的の総合統一」と呼んでいて…。
ことは:
すべての理想的目的の総合統一!?なんですかそれは!?
▼ 続きはこちら