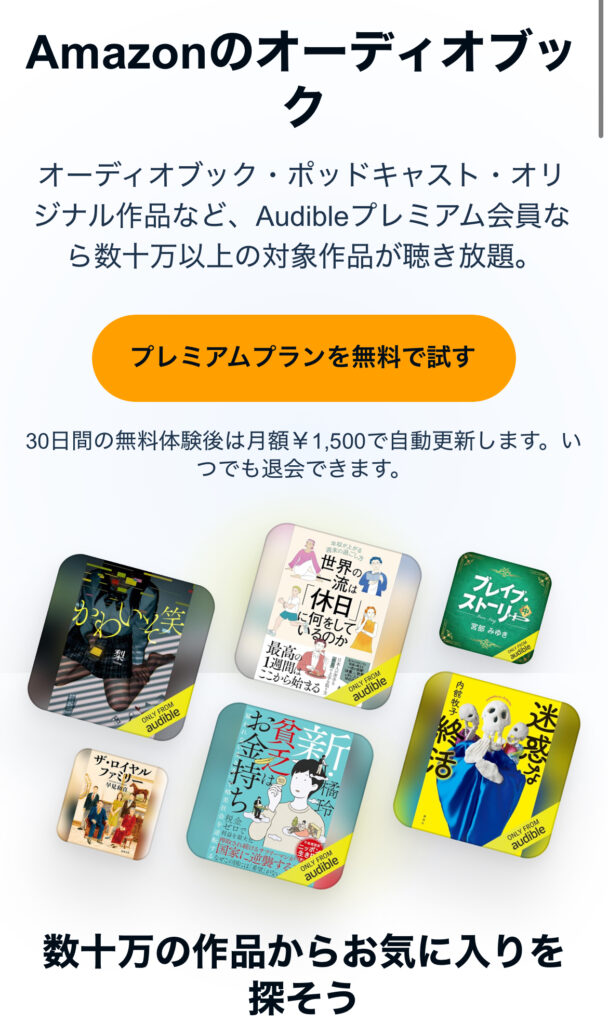「なぜ自分の夢や記憶には、いつも “乗り物” が出てくるのだろう?」
先日、アドラーカウンセラー養成講座の同期による「世界に一つだけの物語」のモニターに参加させていただき、自分自身の早期回想を語る機会があった。
語った3つの回想すべてに、共通して登場していたのが「乗り物」であった。
言われてみると、ライフスタイルを覗くための窓として有用とされる「夢」においても、飛行機の墜落や車での移動といった乗り物の場面がくり返し現れていることに気づく。
最初はあまり気に留めていなかったが、今回カウンセラーの助けもあり、自分の中にくり返し現れる「乗り物」のメタファーが意味するところ気づくことができたので、記録しておきたい。
くり返されるメタファーとライフスタイル
普段からいろんな方のライフスタイル調査表を取得させていただき、早期回想を大量に読んでいると、同じクライアントが、ある特定のメタファーを伴う物語をくり返し語ることがあることに気づかされる。
例えば、あるクライアントはドアや窓が登場する物語ばかりが出てくる。
別のクライアントはどこかに落下して、それを誰かに助けてもらう話ばかりが出てくる。
ライフスタイル診断において、特定のメタファーをどう意味づけ、解釈するかは決して一義的に決まることはない。
けれども、くり返し語られるメタファーが、クライアント自身が人生でくり返しているテーマ、クライアント自身のライフスタイルにどこかしら関連があるのは間違いないと見ている。
同じように、私の中にもくり返し出てくるメタファーがあると、最近になって気づかされた。
そのメタファーとは「乗り物」だ。
今回語った3つの早期回想では、1つは自動車に乗っていた記憶、残り2つは自転車に乗っていた記憶について語ったが、早期回想に限らずこれまで見てきた印象的な夢にも、乗り物が何度も出てきている。
例えば、人生で何度どなく見てきた夢に「自分の乗っている飛行機が墜落する夢」がある。
また、夢解釈の記事にも書いたが、昨年末、普段はあまり車を運転しないのに、自動車に乗る夢を何度も見た。
私のなかにくり返し現れる「乗り物」のメタファーが意味することとは一体なんなのだろうか?
「コントロール」というテーマの発見
「もしかしたら、”乗り物” のメタファーは、コントロールすることへのこだわりに通じているのではないでしょうか?」
カウンセラーのこの一言に、ハッとさせられた。
そもそも私は元々かなりの完璧主義で、ライフスタイルもコントローラー寄りなところがあるという自覚があった。
それが乗り物に乗るメタファーと通じるとは思ってもみなかったが、同時にカウンセラーの指摘には強い納得感を感じた。
改めて自分の早期回想と夢を振り返ってみると、確かに一貫したパターンが浮かび上がってくる。
自分で思ったように乗り物を運転(自分でコントロール)できていると “OK”。
逆に、他者の介入によって予期せぬ事故に巻き込まれたり、途中で強制的に降りさせられたり、知らないところに連れて行かれたり(他者にコントロールされている)と “Not OK”。
たとえば、幼い頃の自転車の記憶。自分でペダルを漕いで、行きたいところに行けるのは楽しかった。
一方で、飛行機墜落の夢では、いつも私は乗客として座っているだけで、機体をコントロールすることはできない。墜落していく中で感じるのは、圧倒的な無力感と恐怖だった。
昨年末に何度も見た車の夢でも、運転席にいるときは比較的平穏だが、他の乗客に振り回されたり、意図しない場所に連れて行かれそうになったりすると、強い不安や怒りを感じていた。
乗り物というメタファーを通じて見えてきたのは、私にとって人生とは「自分で運転(コントロール)して、目的地に向かう旅」なのだということ。
同時に、他者に運転される(コントロールされる)ことへの深い恐怖や抵抗感。
これが、私のライフスタイルの根幹にあるのではないかと気づかされた。
人生を貫く「コントロール」の物語
ライフスタイルは人生の運動法則であり、早期回想で語られることはくり返される人生のテーマだとされるが、自分の場合でもそれは見事に当たっている。
父の価値観に抑圧されてきた幼少期。
父のコントロールから脱出したい(自分の人生を自分でコントロールしたい)という思いが、中高時代の反抗期、大学受験に向けての努力、進学を期に家から遠く離れた福岡で一人暮らしをするというアクションの原動力になっていたのではないだろうか。
そこから、大したしがらみもなく、自由に好きなことをできていた大学時代。原付にまたがり各地を旅行した日々は、まさに自分の意志で行きたい場所に向かい、自分のペースで人生を楽しむという理想を体現していたように思う。
同時にすべてを自分でコントロールできるはずもなく、ちっぽけな自分ではどうしようもない、“アンコントローラブル” なものだって存在し続ける。
社会人になるタイミングがリーマンショックや東日本大震災と重なり、さらには足に原因不明の腫瘍ができて全身麻酔の手術をした。
アンコントローラブルで抗えない時代の流れや病気に翻弄され、就職のタイミングで大きな挫折を味わった。
けれども、そのときに「時代に負けたのは、結局自分に力がないからだ」と奮起し、それ以来15年間、社会人になってからもストイックに自己鍛錬を続けてきた。
そして現在。
サラリーマンとして組織に所属しながらも、自分の人生を誰かにコントロールされている感じから解放されたいと強く望んでいる。
独立して自由になりたい一方で、自分はアンコントローラブルなものに耐性が低いという弱点もあるわけで、サラリーマンとして働いていた方が、少なくとも金銭面では安定する(コントロールしやすい)側面も否めない。
これは今後乗り越えるべき、人生のジレンマだと思う。
私はプロフェッショナルとして物事を探究すると同時に、自分らしく自由に生きていくことに憧れがある。
その原動力となっているのは、リスク(アンコントローラブルなもの)を、実力(コントローラブルなもの)でねじ伏せていくという、ライフスタイル・人生のテーマがあるのだと腑に落ちた。
このライフスタイルとどう付き合うか
どんなライフスタイルにも一長一短があり、自分の持っているものを、いかに建設的に使うかを考えればいいと自分は思う。
- 自分の人生を自分で舵取りしていくための努力を惜しまないところ
- それに向けて完璧主義なまでのクオリティで邁進できること
それらは私の強みなので、建設的に使っていきたい。
一方で、
- アンコントローラブルなものへの耐性の低さ
は自分の大きな弱点である。
人生の全てをコントロールできるはずもなく、アンコントローラブルな物事に気を揉みすぎない。
自分でコントロールできることを謙虚に見極め、そこだけに集中する知恵を身につけたい。
さらに、アンコントローラブルなことが起きた時の対処方法や心の持ち方も身につけていく必要があるわけだが、ふり返ると「アンコントローラブルなものへの分別や対処」そのものが、自分の学問探究のモチベーションになっているようにも感じた。
アンコントローラブルなものは人生のスパイスであり、全てひっくるめて楽しむ境地にいけたらいいなと願う。
…とここまで書いたところで、ラインホールド・ニーバーの祈りの言葉を思い出した。
THE SERENITY PRAYER
O God, give us serenity to accept what cannot be changed,
courage to change what should be changed,
and wisdom to distinguish the one from the other.
Reinhold Niebuhr
ニーバーの祈り
神よ変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。
変えることのできないものについては、それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。
そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、識別する知恵を与えたまえ。
ラインホールド・ニーバー(大木英夫 訳)
まとめ
思い出や夢の中で、くり返し登場するメタファー。
それは単なる偶然ではなく、その人のライフスタイルや人生のテーマを映し出す。
「乗り物」というメタファーを通じて見えてきた私の人生のテーマ。それは「コントロール」への強いこだわりだった。この気づきは、今後の人生をより建設的に歩んでいくための貴重な道しるべとなるだろう。
あなたの早期回想や夢の中に、くり返し現れるメタファーはないだろうか?
それが語りかけているメッセージに耳を傾けてみることで、新たな自己理解への扉が開かれるかもしれない。